火打ち石
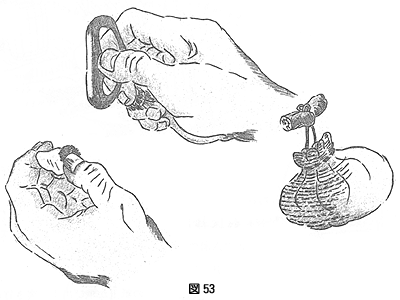
(図53)火打ち石-俺が最終に見たのは瀞ホテルの祖母(現主人茂文氏の祖母)が、根付けに木の根瘤を用い、巾着袋へ煙草、火打ち、かど石、かんやを入れて腰に吊ってゐた。
(俺の少年時代、1912年頃)
・かど石……六方石(水晶石)
・かんや……綿に火藥を浸めたもの
・火打ち……鋼鉄
かど石とかんやを一緒につかんでゐて、かど石に火打ちを打ちつけて、火花を出し、かんやに点じて、それを煙草包み入れて喫う。この發火させることは慣れぬと、なかなか点火しないものだと云ふ。(俺……直晴65歳、昭和43年10月4日、曇天の日)
材木を通す道…すらの図解
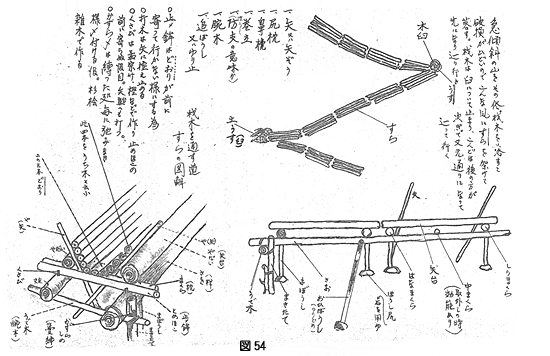
(図54)材木を通す道……すらの図解
急斜面の山をそのまま材木を落とすと破損がひどいので、こんな風に「すら」を架けて落とす。材木は臼(土臼・木臼)に着いて止まり、今度は後の材木が先になり辷り行き、またその次で元通りになって辷って行く。
・止め鉾はドオリが前に寄って行かない様にするため
・打ち木は矢に控え止める。
・くさびは、孟宗竹・樫などで作り止め鉾の前に寄らぬ役目。矢台へも打つ。
・かずら〆は、縛った処ごとに弛みなきよう締めつける役。杉・檜や雑木で作る。
瀞の筏場回想
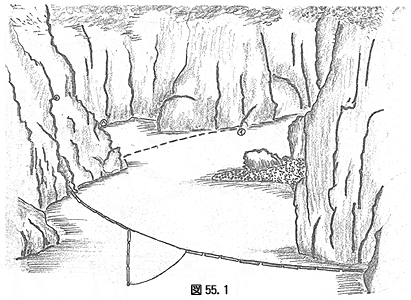
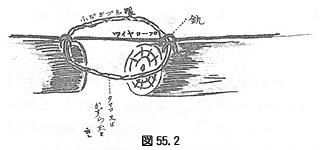 (図55)瀞の筏場回想
(図55)瀞の筏場回想
西紀1935年頃は、釜嶋前(この砂地あたりを「オー岩」と呼ぶ。)の砂礫が集積して川原があり、そこで筏作りの床組みが行ひ易かった。ところが、その後どうした水流の作用か、砂礫の流下減少によるか、逐次なくなった。現在(1969年)は砂礫が皆無である。川原のあった事実は、筏組み作業の終わりまで就業した人の家に寫眞がある。
画面下方斜線は、「アバ」と云ひて流下してくる材木を止めるもので、是は4m材21本で丁度よかったのだ。和歌山県側も三重県側も岩の狭間に繋いである。「アバ」の中程に切り開いてあるのは、大沼方面上流から来る筏の通路で通り過ぎると、また締めておく。
「アバ」は、まず四分程度のワイヤーを引いて、それに藤かずらの輪で繋いだ材木を添えて力ン(?)で止めてあった。上の方の点線も「アバ」で、是は左方のわだ奥に入って集村に手間取ることを防ぐもの。また流木が終わって組み場に集結するとき、イ点の所を曳いてくるのに便せり。藤蔓の輪は、大抵は三重に重ね廻してある。是は、「タマコ」と云ふ。ロは釜嶋、ハはかめ壺である。
荷舟乗り
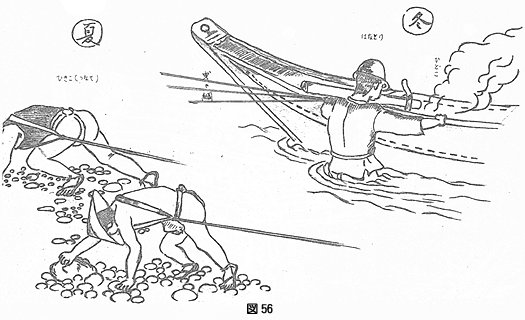
(図56)荷舟乗り
舟一艘に二人のカ子(舟夫)、二艘で一もやい(ヒトモヤイ)と云ふ。この一もやいで三人が綱引きをし、一人が鼻取りをする。
父が若い頃は、新宮通ひの荷舟乗りであった。団平舟(ダンペイブネ)に米や塩、雑貨を積み込んで、一晩又は二晩泊まりで登って来たのだ。引子(ヒキコ=綱手)は夏の眞っ盛り、やけ入って陽炎の立ってゐる磧を石に噛りつく様にして、重い舟を引っ張る苦しさ。それに引換え、舟の鼻取りは水へ這入り、荒瀬を越してアラ(川水が静かなところ)では、舟に乗って棹で操作だから至極楽なり。だが、眞冬になると水量が減り、川辺が遠浅になり、舟の座礁度が多いので水中深く入らねばならぬ。だから大抵の場合、素足である。それで舟の中に火床と云ふて、鍋の古いものなどに石礫を入れて、その上で焚き火をしてゐた。そこで使ふ薪を「火の子木」と云ふた。主に樫、馬目(バメ=バベ)の堅木の半枯れに少々生木を加へて焚いてゐた。
鼻取りは、背丈の高い人又は力の強い人が当たる。鼻取りと引き子は、夏冬に於いて苦労さが反対だ。冬季遠浅の為、舟が岸に接岸できず引子の足が濡れる時は、鼻取りに負ぶさって岸に渡してもらふ程なり。
鼻取りの使ふ張り出し棹は、遠浅のところでは差し棹よりずっと長いものを使ふが、特に急流の荒瀬で力のいるところでは、図の様に短いものを使ひ、肩にかけ精一杯の力業である。
筏
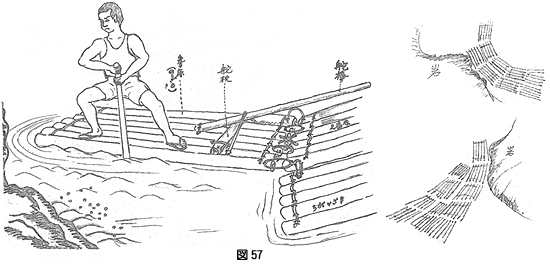
(図57)筏師の乗ってゐる床(材木を組んだもの)を「乗り先き」と云ふ。その次のを「違ひ先き」と云ふ。図の左方の岩鼻を漸く避け得て、少し腰をあげ一息のところ。右でも左でも、一番先端さへ岩に突き当たらねばよい。舟や車と違ひ中程の当たるのは、一向差し支えない。