(71) 大池の御前若の宮
 今から二百年ほど前のことである。
今から二百年ほど前のことである。
上野地の川向い、なかしまというところは、そのころ人家も多く、豊かな田畑が広がっていた。ところがいつの頃からか、何者かによって作物が荒され、収穫も少なくなった。
なかしまに「中根[なかね]」という金持ちがいた。この家にお若という美しい娘が、女中として働いていた。その立ち働く姿は、まるで野中の百合[ゆり]のようで、村の若い男たちのあこがれの的であった。
ところが、このごろどうしたことか、あれほどよく働いていたお若が、物思いに沈み、ため息まじりに、ぼんやり川面をながめていることが、目立つようになった。
こうしたお若のようすに気づいた中根の主人は、
「お前は、このごろどうしたんじゃ、何か悩んでいるように思うんだが、心配ごとがあるんなら、わしに打ち明けてくれんか、お前の力になることができると思うんじゃあが……。」
お若は、顔をうつむけたまま、何も話さなかった。そんなお若を見て主人は、少し声をあらげた。
「お若、お前は、わしが何も知らんと思っとるんじゃろう……。お前のところへ毎夜たずねてくる男は、一体、どこの誰なんじゃ。
わしは、お前を預っているんじゃから責任もある。教えてくれんか。丸くおさめてやろう。」
ところが、お若は黙ったままである。それもそのはず、お若は自分をたずねてくる男が、どこの誰だか、まったく知らなかったのである。
しかし、お若は、その男が、ただ者ではないことを初めから知っていた。男が訪ねてくるとき、戸を開け閉めすることはなく、スーッと煙のように現われるからである。
困りはてた主人は、
「どこの誰ともわからん男に、預かった大切なお前を会わすわけにはいかない。どこの誰なのか、お前も知りたいじゃろう」
お若は、こっくりうなずいた。
「よいか、男の気付かぬうちに麻糸をつけた針を、たぶさの中に差し込んでおくのじゃ。その糸を追っていけば、どこの誰かは、すぐにわかるじゃろう。お前もわしも安心というもんじゃ。」
さて、その夜のこと、お若は主人の言いつけどおり、縫い針に白の麻糸をつけ、男のすきをみつけて、たぶさの中にそっと差し込んだ。
夜が明けた。中根の主人は、起き抜けに、お若の部屋の裏に出た。
麻糸は朝露に濡れ、垣根越しに畑に降り、そして昼なお薄暗い薮の中を通り、やがて、なかしまのはずれにある、油を湛[たた]えたような大池の底深くへと沈んでいた。
アッと叫んだ主人は、腰も抜かさんばかりであった。こけつまろびつ、真青になって家にたどり着いた。
主人から糸の行方を聞かされたお若の驚きは、大変なものであった。お若が夜な夜な語り合ってきた相手がなんと、大池の主であったとは。悲嘆にくれたお若は、その日から部屋に閉じ込もり、一歩も外へ出ようとしなかった。食事もとらず、日に日にやせ細り、人々のあわれをさそった。
お若の顔付きは、日毎に何かにとりつかれたようになった。あの初々[ういうい]しいお若とは、似ても似つかなくなっていった。
ある嵐の夜のことである。ガタガタと戸を開ける音に気付いた家人が部屋にとびこむと、開けられた戸の向こうの薮へ走り込もうとするお若の姿が、キラッと光ったいなずまの中に一瞬見えた。そして、闇の中に吸いこまれていった。
その後、嵐の夜は決まって、青い火がただひとつ大池の周りをさまようのであった。
このことがあってから、なかしまの田畑が荒れることはなかった。
お若をあわれに思った村人は、大池のほとりに小さな祠[ほこら]を建て「大池の御前若の宮(お若大命神)」として、毎年、祭を行った。付近の村では、
「かわいい娘は、なかしまへやるな
上は立崖[たちくら]、したも崖[くら]
中に蛇[じゃ]の巣の池がある」
と、謡[うた]われた。
明治二十二年の大洪水で、なかしまは厚い土砂の下になってしまった。が、大池だけは、わずかにその跡を残していた。
毎年行われる国王[こくおう]神社の祭礼の日、行列が、なかしまの真向いの一本松付近に来ると、そこから大池の御前若の宮に向って、感謝の一礼をするのがならわしであった。
「大塔十津川時報」から
再話 松実 豊繁
(72) 幽霊にもらった幸せ
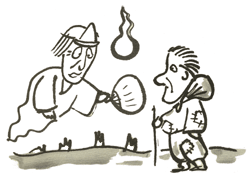 ある百姓家[ひゃくしょうや]のことである。母親は、長い間患っていたが、とうとうなくなってしまった。
ある百姓家[ひゃくしょうや]のことである。母親は、長い間患っていたが、とうとうなくなってしまった。
残されたのは、父親の安蔵[やすぞう]と息子の安太郎[やすたろう]だけで、毎日、寂しく暮らしておった。しかし、悪いことは重なるもので安蔵までが病気になってしまった。やがて、この家の食べ物も底をついた。
あわれに思った庄屋は、二人を自分の家に連れてきてめんどうを見始めた。
庄屋の親切で、父親はずい分と良くなった。
ある日のこと、安蔵は、
「おかげ様で、もうすっかり良くなりました。たいへん気ままなお願いですが、私を旅に出して下さい。四国参りに行きたく思います。途中で死んでも構わぬ覚悟で参ります。息子の安太郎は、くれぐれもよろしくお願いします。」
真剣な安蔵の願いに心優しい庄屋は、胸を打たれてしまった。
本当に、この病み上がりの体では、途中でのたれ死にしてしまうかもしれない。しかし、安蔵の本望であれば仕方のないことだ、と庄屋は思った。
安蔵は遍路[へんろ]の姿となって、旅立って行った。
残された安太郎は、しばらく元気をなくしておったが、これではいかんと思ったのだろう。
「庄屋様、ずい分長い間お世話になりました。このまま毎日、ただ飯をいただいておりますと、申し訳ありません。何でもいたしますので、仕事をさせて下さい。」
と頼んだ。
庄屋も、
「なかなか感心な心掛けじゃ。働けば体にも良いじゃろう。
どうじゃろう、この屋敷の向こうに低い丘があろう。あの丘をいつまでかかっても良いから、この前にある畑と同じ高さになるまで掘り下げてくれんか。」
と言った。
早速、安太郎は仕事にかかった。毎日少しずつ丘を掘り下げていった。そんなある日のこと、ガチッと鍬[くわ]の先が一個の壷を掘り出した。ふたをとってみると中に大判が三枚入っていた。
すぐ、庄屋にそれを見せた。庄屋は、
「それはどれくらいの深さにあったか。三尺(一メートル)より上だったら地主のものだが、三尺より下だったらお前のものだよ。」
という。
「庄屋さま、三尺より上でした。どうぞ、お受け取り下さい。」
と言うと、
「いや、お前は、きっと嘘を言っておる。わしに、どうしても受け取らせようとしておるのじゃろう。それは、お前のものじゃ。」
と言って、どうしても受け取ってくれなかった。
困った息子は、代官所へ大判をもっていった。そして、代官に、
「庄屋様がどうしても受け取ってくれません。なんとかして下さい。」と訴えたのであった。代官は、庄屋の言い分も聞いたが、すっかり感じ入って、判断を下してくれなかった。今度は、お寺にもちこんで坊さんに訳を話し、
「寺の宝として受け取って下さい。」
と言うと、坊さんは、
「では、寺の宝として預っておこう。」
と、言うてくれた。
一方、四国へわたった父親は、二年間で四国中を巡礼し、ついに三年目、国元へ帰ることになった。四国を離れ、そして、とある村に入った。一夜の宿を求めたが、四国とちがって、どこへ行っても泊めてくれず、
「あっちの在所へ行け。」
「いや、向こうの在所へ行け。」
と、追い払われた。
仕方なく隣村へ行こうと三十町(約三キロ)ばかり登り切った休場[やすば](休憩所)まで来た。そこで大きな松の木にもたれて休んでいると、突然、もたれておる木の上から、
「おお来てくれたのか、待ちかねたぞ。」
と、叫ぶ者があった。すわっ、追いはぎと、びっくりしてはね起きた目の前へ、一人の男が音もなく降りてきた。
それは、六十歳ばかりの爺さんであった。
「あんたは、誰ない。」
と聞くと、
「いやあ、おどろかしてすまんすまん。実は、おれは幽霊なんじゃ。わしは、あんたが行く次の村に住んでいた者じゃが、何の罪もないのに、そこの大庄屋[だいしょうや]に殺されたんじゃ。恨みをはらそうと思うて、毎夜、大庄屋の門前まで行ってみるんじゃが、門にお札がはってあるんで、どうしても中に入れんのじゃ。一緒に来てくれ、あんたの来るのを、ずっと待っていたんじゃ。」
と言った。
そこで連れもうて、また三十町ばかり下りていくと、大きな屋敷の前に出た。幽霊は、
「そこのお札をはがしてくれ。」
と言った。
それをはがしてやると、
「おれが敵を討ってくるまで、ここで待っていてくれ。」
と、屋敷の中へ入って行った。
しばらく木の陰にかくれて待っておると、
「やれ、よかったよ、長年の恨みをはらしてこれたよ。実は明日、大庄屋が死んだという触れが出るから、二、三日おれの家に泊まっていってくれんか。」
と言う。
そして、一本の団扇[うちわ]をくれた。
「この団扇はな、孫がおれのガンバコ(棺)へ入れてくれた渋団扇[しぶうちわ]じゃ。これをもって行けば、孫はわかってくれるはずじゃ。あんたに団扇をやったのじゃから、わしにも何かくれんか。」
と言った。
そこで、安蔵はフダバサミのお札を一枚やると、
「ああ、ありがたい。ありがたい……。おお、そうじゃ。おれの家は、ここから二町ばかりのところにあるが、一軒屋じゃからすぐわかる。」
そういって、両手でお札をパリッと割いて、握ったかと思うと姿を消してしまった。
幽霊に言われたとおり、一軒の貧しげな家があった。門口に立つと、婆さんが孫を負うて出てきた。安蔵が遍路姿であったので、手の内(銭)をくれようとした。すると、背中の孫が安蔵のもっている団扇に気付いて騒いだ。そこで、婆さんに、これまであったことを話すと、婆さんは、たいへん喜んでくれたのであった。
翌日、幽霊の言ったとおり、大庄屋が死んだという触れが回って来た。安蔵は婆さんに二、三日やっかいになったのち、再び故郷へ向かって旅に出た。
一方、安太郎は、その正直さがお城にまで聞こえて、殿様に呼ばれることになった。殿様は安太郎の心根[こころね]にほれて、二百五十石の扶持[ふち](給料)をつけてくれた。
「武芸も学問もありませんから、どうか、お許し下さい。」
と断ると、
「人間は、正直が第一の宝じゃ。」
と、ますます気に入られて、若党や馬の口取り(けらい)までつけ、おまけに大きな家まで村の中に建ててくれた。
妻がないというので世話する人があって、ある侍の娘をもらった。やがて二人の間に男の子が生まれた。ところが、嫁さんは、安太郎にちっとも赤子の顔を見せなかった。安太郎は、侍というものは、自分の子どもも見られないのかと、変に納得して、そのままに幸せな時は過ぎていった。
さて、父親の安蔵であるが、ようやく故郷にたどり着いた。息子が世話になっている庄屋の屋敷に入る前に、もうこれで遍路としての修行はできないのだからと、村内[むらうち]を一回りしてこようと思った。
村の中に入ってびっくりした。自分が村を出るとき、こんな大きな家はなかったはずだ、と思いながら門前に立つと、美しい嫁さんが出てきて手の内を与えてくれた。そこを出てゆくと、向こうの方から立派な侍がクツワ取りと若党を連れて馬に乗ってやってきた。あわてて脇道によって近づいてくる侍をながめた。どうも見おぼえのある顔だが…はて…。
侍が近付いてきたので、思わず頭を下げた。侍は、安蔵のそばまで来ると、馬をとめてじっと見つめていたが、いきなり馬からとび下りると、じっと安蔵の顔をながめた。
「お父さんではありませんか。よく、まあご無事で…。」
あとはことばにもならず、むしゃぶりついてきた。安蔵は、夢かと一瞬思ったが、自分の胸に顔をうずめている侍は、確かにわが子安太郎であった。
安太郎は屋敷へ父親を案内した。その屋敷というのは、さっき、手の内を受け取ったところである。
嫁が出迎えに出て来た。けげんそうな顔をしている嫁さんに、安太郎は、
「お前に初めて会わすが、三年近く四国参りに行っておったわしの父上じゃ。」
と紹介した。
嫁さんは「エッ。」と驚きの顔付きとなり、そして、突然、泣いて泣いて、
「お父様とも知らずに手の内を出してしまって誠に申し訳ないことを致しました。本当に私はどうしたらよろしいのでございましょう。」
「いやいや、そんなことを気にせんでもよろしい。お互い親子ということがわからなんだんじゃからのう-。それよりも孫が生まれておるというが、見せてくれんか、早よう見せてくれんか。」
こう安蔵が言うと、嫁さんはまたまた泣き出した。
「一体どうしたのじゃ。」
と安蔵が問うと、
「申し訳ございません。実は不具[ふぐ]の子を産んでしまったのです。それで、まだ旦那様にも見せていないのです。こんな子を産んでしまって、本当に申し訳なく思っているのでございます。」
「なに、不具だと、不具でもよい。わしのかわいい初孫じゃ。さあ、早よう見せてくれ。」
「生まれて三十日もたつというのに、まだ目も開かず、手も握ったままなんです。」
と、涙ながらに言う。
「そうかそうか、とにかく会わせてくれ。初孫を見たいのじゃ。」
涙をうかべたまま嫁が離れ座敷に案内すると、赤ん坊はスヤスヤと眠っているふうだった。目は閉じ、両手もしっかり握ったままであった。安蔵は持っていた数珠を赤ん坊の目に当てた。そして、何やら文言を誦[とな]えると、目はパッチリ開いた。また、文言を誦えて数珠を両手に当てると、両手はゆっくり開いた。その開いた手の中に何やら紙きれのようなものがあった。安蔵がそれをつまんで開いてみると、なんと、それはあの幽霊に与えたお札であった。
話者 谷垣内 上垣 なお
記録 林 宏
再話 松実 豊繁
(73) ソウハン渕の怪
 奥里(大字内原)から三キロほどのところにソウハン渕がある。この渕は、そそり立つ絶壁の下にあって、どんよりと深く水をたたえている。渕は畳が何十枚も敷けるほど広く、ちょうど壷のような形をしている。おまけにこの渕は、周りがつるつるで、いったんはまりこんでしまうと溺れ死んでしまうとおそれられ、近付く者は今もいない。
奥里(大字内原)から三キロほどのところにソウハン渕がある。この渕は、そそり立つ絶壁の下にあって、どんよりと深く水をたたえている。渕は畳が何十枚も敷けるほど広く、ちょうど壷のような形をしている。おまけにこの渕は、周りがつるつるで、いったんはまりこんでしまうと溺れ死んでしまうとおそれられ、近付く者は今もいない。
ソウハンというのは坊さんの名前らしく、この人が過[あやま]って、この渕に落ち込んで亡くなったという。それ以来ソウハン渕とよばれるようになった。
昔々、この奥里にたいそう孝行な息子がいた。長い患[わずら]いの父親がいたが、貧しい暮らしでは、ろくに薬も手に入らなかった。何とかして、早く元気になってもらいたいものだと、息子は気をもんでいた。
そんなある日のこと、朝から雨降りだった。こんな日は、一日中家の中で縄をなったり、ぞうりを作ったりすることになる。息子は、土間でぞうり作りを始めた。一段高いところに囲炉裏[いろり]があって、その近くに父親を寝かせている。
息子がふと表を見ると雨が止んでいた。青葉若葉がキラキラ光っているのをぼんやりながめていた息子は、
「父よ、おれ、今から釣りに行ってくるわ。ちょっと待っとってくれえよ。」
「雨上りの川は、そらあアメノウオがよう釣れるが、足元があぶないぞ。すべらんように気いつけて行ってこいよ。オイ、ソウハン渕だけには絶対行ったらあかんぞ。お前にもしものことがあったら……気いつけて行って来いよ。」
息子は、やせた父親の顔が、明るい外からはっきり見えなかったが、泣いているのだろうと思った。なんとしてでも父親に滋養のあるものを食べさせたかった。元気になってもらい、一緒に山仕事や畑仕事がしたかった。
雨の降ったあとは少し水も増し、ささにごりになっている。ミミズをつけて、チョンとゆるい流れに入れると、サッと一匹かかった。それからあとなかなか釣れない。奥へ奥へと移っていった。そしていつの間にかソウハン渕の上に来てしまっていた。
目がくらむ思いがした。みずかさも増し、水音も高い。どろりとした渕の底から水が沸き出すように渦まいているのだ。自分が吸い込まれそうな気持ちに襲われながら、懐からアワモチをとりだしてかじり始めた。気を落ち着かせる為もあった。じっと水の落ち口をながめていると、時々流れてくる川虫をねらっているのだろう、木の葉にまで飛びつくアメノウオが見えた。
釣ったものかどうか迷っていた。まだ、五・六匹しか釣っておらず、もう少しほしかった。このソウハン渕のアメノウオは、釣ってはならんと言われている。しかし、どうせ同じ川のアメノウオだ……。どうしたもんじゃろう。アワモチを口に入れたまま考え込んでいた。
そのとき、軽く肩をたたくものがあった。驚いて振り返ると、そこに旅を続けているらしい、一人の坊さんが立っていた。
「いやあ、驚かせてすまんのう。そなたがあまりに考え込んでいなさるようすなんでのう。一体、何を考えていなさる。」
「お坊さまは旅をしておいでですか……。別にたいしたことを考えているわけではありません。この渕の、ほれ、今、とびあがったアメノウオを釣ろうかどうか迷っておるんです。」
「どうして迷うのじゃ。」
「迷信だと思っておるんですが、昔から、この渕のアメノウオを釣ってはならんと……。」
息子は、自分だけがもちを食べていることに気がついて、あわてて坊さんにも渡した。
「おお、これはかたじけない。これはなんというものじゃ。」
「アワモチです。あんまりうまいもんではありませんが……。今朝方[けさがた]焼いたもんで、ちょっと堅いかもしれません。」
「いや、いや、けっこうけっこう。めずらしいもんじゃ。」
そういって、食いにくそうに食べていた。坊さんの姿をよくよく眺めてみると、墨染[すみぞめ]の衣の裾は裂け、破れた貴賤帽[きせんぼう]を冠[かぶ]っている。全身、雨に濡れてしまっている。
「ひとつ、そなたに頼みがあるんじゃが……。のう、もう幾匹か釣ったのじゃろう。それだけで満足してもらえんか。無益な殺生はするもんじゃない。この渕にそんな話があるんなら釣らん方がええと思うが……。昔から、してはならんということには、きっと何かわけがあるもんじゃ。」
「ウン、それはわかるのですが……。あと一匹だけ、と思うとるんです。……家では長い煩[わずら]いのお父が待っとるんです。……」
「わしは、先を急ぐんで、これで……。ごちそうになりました。では、くれぐれも頼みましたぞ。」
坊さんは丘を回って見えなくなった。
「どうしたもんかなあ……。よし、いっペんだけ竿を入れてみよう。それだけで終わりにしよう。」
そう決心した。丁寧にエサをつけて落ち込みの中へそっと投げ入れた。入れたとたん、すぐに強い当りがあった。なかなか上がってこない。相当な大物らしい。姿も見せない。小半時[こはんとき](三十分)も頑張って、やっと水面にその姿が現れた。それは、今まで見たこともないほど大きなアメノウオであった。ゾクゾクするほどの嬉しさが、体中を走った。糸を切られないよう、
「あばれるなよ、あばれるなよ。」
と、魚に話しかけながら、ゆっくりひっぱりあげた。とてもぼうつり(びく)に入るようなものではなかった。樫の枝を折って、えらに通して、かついで帰った。喜びが足元からはいあがってくるようで、胸もわくわくした。
「お父、今帰った。ほれ見てくれ。こんなどえらいもんが釣れた。」
それがどこで釣れたものかは、父親に言わなかった。
「じきに焼いたるよって、ちょっと待っとってくれえよ。」
そう言って、まず小さいアメノウオのはらをし、串にさし囲炉裏のふちに並べた。
さて、大物である。しばらく、その姿に見とれていた。包丁を入れるのが惜しい気がした。ちょっと迷っていたが、白い腹に思い切って包丁を入れた。手をつっこんではらわたを取り出す。これだけの大物だとはらわたも大きい。中でも胃袋が大きくふくれている。息子は気になった。
「いったい何を食べているのだろう。」
そんな興味もあって胃袋を裂いてみた。川虫に混じって黄色いものがたくさんある。
「これはなんだ。」手についたものをしげしげと見つめていた息子は、アッと息を飲みこんだ。アワモチなのだ。あのソウハン渕で
「頼みましたぞ……」と、
言い残して、去っていった坊さんが食べたアワモチであった。
息子は包丁をにぎったまま、破れた貴賤帽と裂けた墨染の衣を着て、濡れて去っていった坊さんを思い出していた。
話者 内原 亀田 文子
再話 松実 豊繁
(74) 京都三十三間堂の棟木
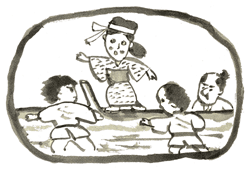 桑畑に柳本というところがある。そこには、古い柳の木があったが、道路が広げられたとき切られ、今では柳本という地名があったことさえ、知る人は少ない。
桑畑に柳本というところがある。そこには、古い柳の木があったが、道路が広げられたとき切られ、今では柳本という地名があったことさえ、知る人は少ない。
むかしむかし、この山奥の柳本へ都から役人と大勢の人夫がやってきた。当時、この柳本には、天にも届くかと思われる柳の大木が一本立っていた。役人は、この柳の大木を切って都へ運ぶというのだ。
「都の天子様が大病にかかっているのじゃが、どんな祈祷[きとう]も薬も一向に効き目がないのじゃ。ところが天子様の夢枕に、み仏が現れて『熊野川の上流に柳の大木がある。それを都に運び、寺の棟木とし、わたしを祀[まつ]るがよい。』と、告げたのじゃ。われわれ一行は、三月[みつき]もかかって柳の大木を探し求めて、やってきたのじゃ。
ようやくここまで来て、この大木を見つけたというわけじゃ。ウーン、実に見事な柳じゃ。さすが、お告げの柳の大木だけあるわい。さっそくあすから切り倒しにかかることにしよう。」
そのとき、柳の葉が風もないのにかすかに揺れたようだった。
この柳の大木の近くに、老夫婦と一人娘が住んでいた。娘の名をおりゅうと言った。
この家に、以前から一人の若者が時おり通ってきていた。実にりりしい若者で、老夫婦は、二人をいつか夫婦[めおと]にしようと考えていた。若者は口数の少ない人だったが、「川下の者です。」と、いったことがあった。だから萩か本宮の人だろうと話し合っていた。
若者は鮎やアメノウオ、茸[きのこ]など、季節の土産を欠かすことはなかった。
今夜はどうしたことであろうか。若者の、あのにこやかな笑顔はなく、青ざめ、ふさぎこんでいた。まだ初秋ではあったが、山の夜気[やき]は冷たい。若者は黙ってチロチロ燃える囲炉裏の火を見つめていた。そして、思い切ったように、
「実は、今日、お別れにやってきたのです。全く突然ですが、急に都へ行かねばならぬことになりました。長い間、本当にお世話になりました。」
と、言うと板戸を開けて外へ出た。あまりにもす早い行動で、三人は声をかけることもできなかった。あわてて後を追った三人は、柳の大木の付近で姿を見失ってしまった。三人は悲しみに沈んでしまった。特に娘おりゅうの悲しみは大きいものであった。晴れて夫婦になることを夢見ていたのに、急に都へ行くのだという。
それも一切の理由を明かさないままに、である。裏切られたようにくやしく、身を裂かれるようにつらかった。その夜、誰も眠ることができなかった。
翌日から柳の大木を切る準備が始まった。都から来た人夫たちは、スルスルと大木をよじ登り、手早く枝を落としていく。むらの人たちの中には、手伝う者もいたけれど、めずらしげに見物している者が多かった。二、三日すると近在[きんざい]のむらからも、うわさを聞きつけて見物に来た人がいたほどである。一日中、あきもせず、作業する都の人夫たちを遠巻きにして見ているのである。
「オーイ、柳が倒れるぞ。」
という声が、あれから臥[ふせ]っているおりゅうの枕元まで届いたとき、
「おりゅうさん、さようなら。」
という、耳にささやく声を聞いたように思った。
はっとして、おりゅうが戸口まで出て見ると、枝を切り落とされた無惨な姿の柳の大木が、悲鳴のような音をたてて、ゆっくりと、そして、地響たてて倒れた。あたり一面、もうもうと土煙が舞い上がった。
やがて、柳の大木は、残った小枝を切り払われた。そして、大勢の人たちの掛け声とともに十津川へずり落とされた。
柳の大木は、水辺で他の丸太と一緒に太い藤カズラで結び付けられ、筏[いかだ]に組まれた。そして、水面に重たげに浮いた。何人もの力で、ゆっくり早瀬[はやせ]に押されていったが、いかにも流れていきたくない様子に見えた。むらの人たちは、妙にもの悲しい気持ちに襲われた。
おりゅうもむら人の中にいた。早瀬にのっても重々しくゆったり流れていく柳の大木を見送っていると、わけもなく涙があふれてきた。柳の大木はワラビオの瀬を越えて、やがて見えなくなった。
人々は、大きなためいきをついて、思い思いに散り始めた。大木の切り跡はがらんと広くなって、おりゅう一人だけが、切り株の側に立っていた。おりゅうは、どうしてそうするのか、自分でもわからなかったが、柳の切り株をいとおしげにさすっていた。ふと、おりゅうは、
-あの方は、この柳の化身だったのではあるまいか-
と思った。
それから三日ばかり経った頃のことである。老母が、あの柳の大木のうわさを聞いてきた。
「なんでも楊枝[ようじ]とかいうところで柳がとまって動かないらしいよ。大勢で引っぱっても、木のまわりを掘っても、全然動かなくなったらしいよ。」
と、いうものだった。
その夜、おりゅうは、誰かが自分を呼んでいる気配に目が覚めた。起きあがったおりゅうの枕辺[まくらべ]に、あのなつかしい若者が、寂しい目をして座っていた。
「おりゅうさん、わたしです。あつかましいお願いですが、わたしと一緒に都へ行ってくれませんか。わたしは楊枝の川であなたが来るのをじっと待っております。」
-ああ、やっぱりそうだったのか。-
おりゅうの目から、涙がとめどもなく流れた。そして、こっくりうなずいた。声が出なかった。
「それでは……。」
と若者は、おりゅうの目の前から消えた。
翌朝、おりゅうは、とめる老父母の手を振り切って果無山[はてなしやま]の道を本宮へと、たどっていた。狼がいる暗い寂しい道である。けれども、おりゅうは、おじることなく山道を登っていった。まだ、誰も通っていない山道は、くもの巣がはっていて、木の枝を振りつつ登っていかねばならなかった。
頂上付近で日の出であった。そこから尾根づたいに一気に八木尾[やきお]へ下りた。山ん婆の出るという山中であったが、今は、そんなことを考えている暇はなかった。
そして本宮。ここまでは、両親と来たことがあった。
本宮からまた山へ入った。この山を越えれば、楊枝である。しかし、中腹の小さなむらで日はとっぷりと暮れてしまった。おりゅうは、この名も知らぬむらのお宮に泊めてもらった。
あくる朝、まだ夜のあけきらぬうちに、おりゅうは楊枝を目指した。昼を過ぎたころ、ようやく、楊枝の川原に着いた。
川原では、なんとかして柳の大木を動かそうと、大勢の人が大騒ぎしている最中であった。浅瀬では、大木にそって深い溝が掘られていたが、いくら押しても引いても動かないという。今日で七日目であった。
おりゅうには、見おぼえのある都の役人の顔があった。その役人の前におりゅうは進み出た。
「申し上げます。私がこの柳の大木を動かしてご覧に入れます。夢枕に、私が掛け声をかければ必ず動くとの、お告げがありました。どうか、わたしにお手伝いさせて下さいませ。」
今まで動かなかったものが、女の掛け声ひとつで動くとは役人には思われなかった。しかし、この女は、もしかしたら特別の力をもった者かもしれん。一刻も早く動かしたい一念の役人は、おりゅうの力を試してみようと思った。
おりゅうは、柳の大木に近寄って、そっとささやいた。
「わたしが参りました。都までご一緒致します。どうか、安心して動いて下さいませ。」
やがて、おりゅうは大木の上にのぼった。りりしく黒髪にはちまきをしめ、手には扇をもって、居並ぶ何百人かの人夫たちに、
「みなさん、私が声を掛けましたら、みなさんも一斉に声を出して、力一杯引っぱって下さい。そうすれば神仏の力を得て、必ず動き出します。」
すみきったおりゅうの声を聞いた人夫たちも、体の内から新しい力がわいてくるのが感じられた。
「それではみなさん、心を合せて……
ソーレッ、ヨーイショ、ソーレッヨーイショ」
人夫たちも一斉に声を合せた。
するとどうだろうか。六日間ビクともしなかった大木が、そろりそろりと動き出したのである。人夫たちもこれにますます力を得て、さらに力を入れた。大木は、やがて早瀬にかかる深い渕にゆったりと浮いた。人夫たちは、歓声をあげておりゅうの元に走り寄った。
こうして柳の大木は、おりゅうにともなわれて新宮へ、そして海をわたり、淀川をのぼって、京に着いた。都の人々は、この柳の大きさに、たいそう驚いたという。やがて三十三間堂の棟木にされたのである。
ところでおりゅうは都にとどまったのだろうか、それとも両親の待つ柳本へ帰ったのだろうか。
記録 柳本 弘
再話 松実 豊繁
参考 「楊枝薬子」和歌山県熊野川町立九重小学校
その他
(75) ほうそうを病んだ娘と母
私の家の近くに、奥谷[おくだに]という谷があって、その谷の奥にタラタラという傾斜の緩[ゆる]い山原がある。
そこへ、私がまだ小学生の頃、母と薪[たきぎ]こりに行ったことがある。
私はゴシ、ゴシ、鋸[のこぎり]で木を伐って、ガリガリ、バシャンと倒した。木が倒れる時は愉快であった。母はそれを鉈[なた]でこなげた。
「次郎よ、はらんへっつろうがい。ひるめしゅう食おうら。」
という母の後について、私も山原へ下りた。弁当といっても、米が二分で麦が八分である。おかずは、梅干しとだしじゃこであったが、おなかがすいているとおいしかった。昼飯のとき、弁当を食べながら母は、こんな昔話を聞かせてくれた。
昔、このあたりゃあ樫尾崎[かしおざき]村ちゅうたんじゃ。この村にほうそう(天然痘)にかかった十五、六歳位の娘ん居ったんじゃと。ほうそうちゅう病気はうつり病いで、この病気にかかったら大方の人ん死んだんじゃ。ほんで、みんなおとろしがって、この娘の家へ、よりつかんようになったそうじゃ。
ほうそうにかかると、山の中へ小屋あ建てて、そこへうつされたんじゃ。この娘もここへ(タラタラ)小屋あ建てて入れられたんじゃと。
小屋ちゅうても、樫や椎の木のはしらあ突き立てて、屋根は杉皮でふいたんじゃ。壁は、はっぱのついとる木のえだあ横木にくくりつけたんじゃ。部屋のまん中へゆるりゅう(いろり)こしらえ、そのまわりに丸太あ並べ、丸太の上へ板あ敷き、板の上へ蒲[がま]むしろう敷いたもんじゃ。娘はそこへねさせられたんじゃと。
ほうそうが、うつったらかなわんちゅうて、誰も来る人んなかった。けんど、おか(母)は、
「こがあな山ん中へ、むすみょう(娘)一人ねかせられん。」ちゅうて、いっしょにきたんじゃと。
娘は、
「おりゃ、どうせ死ぬんじゃ。おかは帰れよ。おかまでほうそうになったらわるい。」
「ほうそうちゅうのは、うつってから何日もからだん中へ、すっこんどるんじゃ。おれももう、うつっとるじゃろう。おれのこたあ心配せんと早よう治せよ。」
おかは、そがあに言うてから、
「神様どうぞ、このむすみょう(娘)助けて下さい。」
と、祈りつづけておったんじゃと。そのうちにむすみゃあ治ってきたんじゃ。けんども、今度は、おかん熱う出しそめたんじゃと。ほうそうにかかってとうどうねこうで(寝込んで)しもうたんじゃと。
娘は起きて白粥うたあて(炊いて)おかに食わしたりして、おかあみたんじゃと。
「おりゃあ、としもよっとるし、とてもよう治らん。お前は、むりゅうしたらあかん。山あ下りて行けよ。」
「おかは、なにゅう言うない。治るわよ。じっと寝とれよ。」
娘は、一生けんめいにおかあ、みたんじゃと。
山の芋は栄養になるので、娘は、病[やみ]上りの青白い手で、山芋を掘り歩いたんじゃと。山の芋ちゅうのは、地べたに深こう、たてに入り込んどるので、なかなか掘れるもんじゃなあ、娘は、そりょう掘ってきて、おかに食わしたりした。
ほんでも、おかは、一日一日と病いが重うなって、とうどう死んでしもうたんじゃと。
山の動物ちゅうものは、人が死ぬと、よう知っとるのか、おおかめ(狼)ん、上の岡から「オー」、下の岡から「オー」とうなって小屋のまわりに、寄ってきて、柴壁[しばかべ]の間へ口を差し出すんじゃと。
娘は泣きもうて、火箸を焼きあて、おおかめの鼻へひっつけて夜を明かあたんじゃと。
おかん死んでも誰もきてくれん。娘は、小屋のそばへ穴あ掘って、おかあ埋めて山をおりたんじゃと。
二、三日してから来てみたら、おおかめん掘りだあて持って行ってなかったらしいよ。
話者 重里 榊本 利清
(76) ガマ主と八人の杣師
昔、紀和(三重県)に八人の仲の良い杣師の兄弟がいた。この兄弟が、大野片川[おおのかたこう]の山奥にある中八人山[なかはちにんやま]へ仕事に行ったときの話なんだが……。
その山ふところに弁財天という大きな滝があり、その落ちこみは、深い渕になっていて、いつも青々としていた。
この兄弟は、この滝の近くに杣小屋を建て、そこから仕事に行くことにした。
ある日のこと、その夜は、よく晴れた満月の夜だった。一番上の兄が、夜中にそっとねまからぬけ出し、すうっと小屋を出ていった。朝になっても、兄の姿は見えない。兄弟達は不思議に思いながらも仕事に追われ、きっと兄は里まで買い物に行ったのか、それとも故郷[くに]へ用事のために帰ったのだろうと、余り深く気にもせずにおった。
月がかわり、また満月の夜、みんなが寝しずまった真夜中、こんどは次男が小屋を出ていった。
このようにして、七番目までの兄が次々といなくなり、末っ子の弟は、だんだんと不思議さをつのらせ、これは何かがあるにちがいないと思った。
次の満月の夜までに、まさかりをちゃんちゃんにといで、その夜のためにそなえていた。
いよいよ満月の夜がやって来た。末っ子は、兄達の事を考えながら、まんじりともせず丑三つ時(午前二時)を待っていた。
すると、外からやわらかみのある手で、小屋の戸を「トン、トン、トン。」とたたき、やさしい女の声で「おいでよう。おいでよう。おいでよう。」と、呼ぶではないか。
こんな人里はなれた山の中で、それも夜中に、女がいるはずがない。これはきっと妖怪(化物)かキツネかタヌキの仕業[しわざ]に違いなかろう。かねてより用意していたまさかりを後手に持って、こわごわ戸を押し開けたそうな。
満月の光のもとに、それはそれは美しい女が、白衣の上に長い髪をたらし、黙って手招きをしていたそうな。
弟は、手招きされるままに外へ出て、女の後へついていったそうな。
女は弁財天の渕の方へすたすた歩いて行く。後ろについている末っ子は、きっと兄達は、この女にこのようにさそい出され、弁財天の渕へつれ込まれたに違いない。これは妖怪に違いないと思い、かくし持っていたまさかりを振り上げ、背中に一振り打ちおろした。「ギャーッ」と大きな悲鳴と共に、女の姿はその場から、かき消えた。
弟は、あまりのおそろしさに一目散に小屋にもどり、戸をどうして閉めたかわからぬままに、ふとんをすっくり頭までかぶり、朝までがたがたふるえながら念仏をとなえていたそうな。
夜が明け、弟はおそるおそる外へ出た。弁財天の近くへ行ってみると、昨夜女を切りつけた辺り一面血だらけで、血のついたまさかりだけがあった。そして、弁財天に向かっておびただしい血が流れていた。それをたどって行くと渕の水ぎわに、それはそれは大きなガマガエルが、背中を断ち割られ息たえていた。
弟は、あまりのおそろしさに取る物もとりあえず故郷へ帰ったということだ。
話者 折立 玉置 藤夫
再話 折立 玉置 辰雄
(77) 弓の兄弟
むかし、むかし。朝から晩まで弓と矢を持って遊んでばかりいる兄と弟がいた。
あるとき、父親がたまりかねて、
「お前ら、それほど弓矢で遊びたいなら、粟[あわ]畑にやってくる雀[すずめ]でも射てみろ。」
と、言いつけた。
兄と弟は、粟畑にいき、群がる雀めがけて、しきりに矢を射かけた。が、いっこうに雀は獲れず、落ちるのは粟の穂ばかりだった。これを見ておった父親は、いよいよ怒って、とうとう二人を家から追い出してしまった。
家を追い出された兄と弟は、仕方なく弓と矢をこわきにかかえて、あてもなく歩き続けた。
やがて、日もとっぷり暮れたので、二人は通りがかりのお宮の祠[ほこら]に入って夜を明かすことにした。昼間の疲れがいっペんに出て、兄も弟もそのまんまぐっすり眠り込んでしまった。
やがて、何やらあたりが騒々しいのにおどろいて、外を見てびっくり。
もう、夜はとっくに明け、祠の前にはきのこだの、柿の実だの、魚だのがいっぱいに供えられ、境内では村びとたちが大勢集まってガヤガヤにぎわっているではないか。
「は、はあん、どうやらきょうは村の祭じゃな。」
「これは、このままのんきにはおられん。」
「おい、弟、見つからぬうちに、ここを逃げ出すのじゃ。」
「いいか、おれが扉を開けて、いっきに飛び出すよってに、すぐ後に続くんじゃ。」
「うん、いいとも。」
「いくぞ。」
ギーッ、扉を押し開けた二人はパッと外へ飛び出した。村びとたちはびっくりぎょうてん。
「お、お、神様が飛び出したぞ。」
「や、や、神様が逃げるぞ。」
口ぐちにわめきながら、二人の後へついてきた。
二人は、これには目もくれずに、いちもくさんに逃げた。やっと村びとからのがれて、気がついてみると、もう日は西に傾き、見知らぬところへ来ておった。へとへとに疲れた足を引きずり歩いていると、一軒の古びた家にたどりついた。トントンと表戸をたたくと、
「どなたじゃな。」
しわがれ声の腰をかがめた老婆が現れた。二人が一夜の宿を頼むと、
「あいにく、ひとりしか泊められん。」
と、いう。
「おれたちは、弓の名手じゃ。」
と、いえば、
「それなら、庭の柿の実を落とせ。先に落とした方を泊めよう。」
と、いう。
さっそく兄と弟が思い思いに矢をつがえ、まっ赤な的めがけて射かけた。兄が柿を落として泊まり、弟はしくじって、また先へ進むことになった。弟が日暮れの道をとぼとぼ歩いていくと、行く手にちらちら燈が見える。近よってよくよく見れば、今にも崩れ落ちそうなあばら家[や]。
「旅の者じゃが、泊めてくださらんか。」
と、言えば、またも老婆が現れ、
「泊めてやってもいいが、ま夜中になると鬼がやってくる。それでもいいかな。」と。
「おれは弓の名手じゃ。その鬼を退治してやるから泊めてくれ。」
やっと宿にありついた弟は、あばら家に入って足腰を伸ばした。
やがて、夜も更け、老婆は長持に入って寝ることになり、弟は戸棚にかくれることになった。暗い戸棚の中に入って、そっと細目に戸を開け、弓に矢をつがえたまんま、今か今かと待っていると、ズシン、ズシンと大きな足音をたてて、どうやら鬼がやってきたらしい。弟は力いっぱいに弓のつるをひきしぼってかまえているところへ、表の戸がガラッと開いた。鬼の毛深い胸ぐらめがけてヒョウと矢を放った。矢は的を外れて柱にグサリと突きささった。
少々おどろいた鬼は、怒って弟を戸棚から引きずり出し、しゃにむに肩にかついで出ていった。
一夜が明けると、弟の後を追って兄があばら家にやってきた。
「もしや、若者がひとり来なかったか。」
「弓の名手じゃいうて泊まったが、鬼に見つかり連れ去られたぞ。」
「よし、弟の仇、きっとうってやる。」
兄は、あばら家で夜になるのを待った。
やがて、日が暮れ、夜も深まったので、老婆は長持にかくれ、兄は戸棚に入って鬼を待っていた。ま夜中になると、またしても、ズシンズシンと大地をひびかせて鬼がやってきた。鬼が表戸をガラッと開けたとき、戸棚から兄の放った矢が飛び出し、グサッとぶ厚い胸板に突きささった。「ギャオ」と一声高く、吠えた鬼は、どっとばかりに土間にくずれ落ちた。
兄はあくる日、弟を探して鬼の隠れ処[が]にやってきた。が、弟の姿はなく、途方にくれていると、一羽の烏が現れて、しきりに啼[な]くので、そのあたりを探してみると、弟は死んだようにころがっていた。さっきの烏がまたやってきて、「ヨーモギ。ヨーモギ。」と啼き出した。
兄は、
「よもぎの汁を飲ませろというんじゃな。」
と、近くの草むらからよもぎを摘んで、その汁を弟の口にふくませると、弟の体に血の気がよみがえって、息を吹き返した。
兄と弟は、鬼のすみかに押し入ってたくさん宝ものをもって帰ってきたと。
話者 小森 西田 ワサノ
再話 湯之原 大野 寿男
(78) 国宝院義廣
椎平[しいだいら]の小高い丘に、国宝院様とよばれている小さなお墓がある。
墓の両側には、大きなサルスベリの木が植わっており、夏ともなれば桃色の花が咲きほこり、あたりをいっそう明るくしているのである。
今から二百五十年以上も昔のこと、重里に一人の年老いた山伏がやってきて住みついた。村人は、この山伏を温かく迎え入れた。粗末であるが、一軒の空家が彼に宛がわれた。村人たちは、山や川でとれたもの、作物などを持ち寄って、何くれとなく世話をやいた。
山伏も作物の育て方を教えたり、加持祈祷[かじきとう]で村人を救うこともたびたびだった。また、薬草の知識も深く、村人の多くが助かった。子供たちにも好かれ、遊び疲れた子供たちは、申し合せたように山伏の家によって、昔話をせがんだ。読み書きを習った子供もいたようである。
老山伏の名は、左海義廣[さかいよしひろ]という。泉州は堺の生まれで、延宝[えんぽう]四年生まれ、今から三百年以上前の人である。幼い時から、神童と騒がれるほど、すぐれた才能をもっていた。十四、五歳頃、天台宗比叡山に登り、出家した。出家の理由は明らかにされていないが、仏門に入った彼は、悟りの道を求めて、厳しい修行に耐えた。勤行[ごんぎょう]も熱心であった。また、寝ることも惜しんで、古今の書物を読破した。まことに鬼気迫まる彼の生活であった。このような努力で持ち前の才能は、ますます磨きがかかって、とんとん拍子に、その地位があがっていった。三十代を過ぎた頃は、すでに僧都[そうず]の位になっていた。
彼はあるとき、ふと気がついたのであるが、自分が全く、たった一人であるということだった。そして、年若いにもかかわらず高い位置にいるために、周りには、他の僧侶たちの嫉妬、排斥の動きが、ドロドロと澱[よど]んでいることだった。一切の衆生[しゅじょう]を救うのが仏道に従う者の使命で、その世界は清らかに澄んだところである、と思っていたのに、俗世間とまったく同じ権謀術数[けんぼうじゅつすう]の渦巻くところであった。
このことを知った義廣は、その日のうちに比叡山を去った。彼が、その後、山伏となって諸国の名山・山岳で修行していることが、風の便りで比叡山にも届いた。が、彼のことは、いつしか忘れられていった。
義廣は、比叡山時代、国宝院にいたのであろうか、自らを国宝院と称して、山岳をさまよった。日の出、日の入りを拝み、霧を吸い、木の実を食い、狼や猿を友として諸国をめぐりめぐった。
しかし、彼の安住の地はなかった。いつしか、彼は、老人になっていた。そして、ついに十津川郷重里に入った。この村は、米は穫れないらしく、人々の生活は貧しげであった。貧しすぎて死に際の病人に、
「おい、しっかりせえよ、今、飯を作ってやるよって、元気出すんじゃあぞ。」
と、わめき、家族が米粒を入れた竹筒を病人の耳元で必死に振る場面に出会ったこともあった。
義廣は、はじめ哀しい村だと思った。そして地獄のような村とさえ思った。
しかし、この義廣の考えは、だんだん変わってきた。確かに村人の生活は、貧しげであった。木を切り、炭を焼き、わずかな畑を耕やし、雨が降ればわらじを作り、縄をない、あるものだけで満足し、しかも村人同士は貧しいにもかかわらず、助け合っていた。
村人は、上・下の隔てが全くなかった。だから村人のことばづかいは、荒々しくわめいているようで、言いたいことははっきり言うが、腹の底をさぐり合う必要はなかった。人々は正直で、人をだますことも嫉妬しあうこともなく、仏の世界そのものの村だと思われた。義廣には、これこそ、仏門でいうところの三千世界[さんぜんせかい]の極楽浄土であると思えた。彼は、この地こそ自分が安住すべき土地であると悟って、ついに法杖[ほうじょう]をとめたのであった。
数年ののち義廣は重い病にかかってしまった。もう、自分の命は、わずかしかないと感じた彼は、枕辺[まくらべ]に集まった村人に、この村へ来てから世話になった礼を一人一人に述べた。そして、何もできなかった恩返しをしたかった。
「のう、村の衆、この村に温泉を出してやろうか、それとも火事のない村にしてやろうか。村の衆の望みどおりしたいのだが、どちらが良いか……。」
枕辺に集まっていた村人たちは、しばらく相談していたが、
「火事の出ない村にしてほしい。」
と言った。義廣は、ほほえんだ。
「わしの墓に二本のサルスベリの木を植えてほしい。その木が栄えている間は、村から火事が出ることのないようにしよう。」
と、遺言した。
彼は、椎平の丘に葬られた。
このことがあってから、重里の村には、火事が起こることはなかった。
彼の死後も、彼を慕う村人は、彼が好きだった柴巻きタバコを供えた。
サルスベリの木は、今も元気に天にむかって伸びている。この木は、高い山にある木であって、山岳を巡っているとき、彼をなぐさめたものかもしれない。あるいは、比叡山の国宝院の庭にあった木かもしれない。
「大塔十津川時報」から
再話 松実 豊繁
(79) 高森重蔵
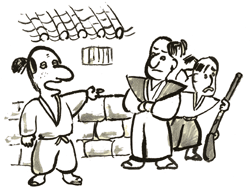 何でも明治維新前の人らしい。その人は高森重蔵と呼ばれていたが、その出生地も本名もわからない。何か都合があってかくしていたものらしく、高森(地名)の巽屋[たつみや](屋号)に住まわせてもらっていた。木挽[こび]きが本職だったらしいが、動作に隙がなく、剣術のたしなみもあったようだ。というのは、木挽き仲間の一人がいたずらに昼寝をしている重蔵の顔の上へ、ぼくっとう(棒)をいきなり振りおろしたら、ムクッと起き上がった重蔵は、サッとその棒をつかんで、ものすごい力で仲間を引き寄せてしまったという。
何でも明治維新前の人らしい。その人は高森重蔵と呼ばれていたが、その出生地も本名もわからない。何か都合があってかくしていたものらしく、高森(地名)の巽屋[たつみや](屋号)に住まわせてもらっていた。木挽[こび]きが本職だったらしいが、動作に隙がなく、剣術のたしなみもあったようだ。というのは、木挽き仲間の一人がいたずらに昼寝をしている重蔵の顔の上へ、ぼくっとう(棒)をいきなり振りおろしたら、ムクッと起き上がった重蔵は、サッとその棒をつかんで、ものすごい力で仲間を引き寄せてしまったという。
まだ、新宮に殿様がいたころ、重蔵はたまたま鉄砲の線習をしている侍たちにいきあわせた。侍たちの稽古があまりにおかしかったのでカラカラと笑ってしまった。笑っただけでなしに、
「あれで的にあたるのかよ。あれでは役にたたんぜよ。」
と、聞こえよがしに言ってしまった。これを聞いた侍たちは青筋たてて怒り、殿様の前にひきずり出した。
「そちは、なにゆえにあのようにあざけったのじゃ。わけを申せ。」
と、殿様。
殿様の前に出ると、ちよっとは遠慮したものの言い方でもするのか、と思ったらそうではなかった。
「わしはおかしかったから笑うたんじゃ、あんなぶざまなかっこうでは的に当たりゃあせん。体が泳いでしもうとる…。」
「そうか、そうか。そちの言うことはもっともかもしれん。では、腰をしっかりすえて的をねらわせることにしよう……。的はおぬしにする。よいか。」
そういって、殿様はいじ悪く笑った。
「元はと言えば、わしが播いた種。喜んで的になりましょう。しかし、今、というわけには参りません。わしは十津川郷は高森の住人、重蔵と申す者。三日の猶予を下され。連れ合いも子供もないが、隣近所の親しい者と、せめて別れの杯[さかづき]でも交わしてきたい。」
「十津川郷は猪や猿の棲まう奥深い山の中、お主が逃げこむには、まことに都合の良いところじゃ。」
「めっそうもない。わしは嘘はいわん。恥となることは断じてやらん。」
重蔵が大声で呼ばわるので、殿様はしばらく黙って重蔵の顔をしげしげとながめていた。
しばらくして、
「的になるに、武器はいらぬか。」と、
たずねた。
「武器……。お殿様、お情けを下さるのですか……。ならば、槍をお貸し下さい。先は要りません。石突[いしづき]がついておるだけで結構です。」
重蔵の堂々とした態度に、
「さすが十津川の郷士だけはある。石突だけの槍を与えよう。しかし、後悔するのではないか。」
けらいが先のない槍をもってきた。重蔵はそれをもらい受け、風のように高森へもどった。
高森にもどった重蔵は、心配気に取り囲む村人たちを尻目に、石突きをていねいに磨きたてた。
三日後に重蔵は、それをもって新宮の射場[いば]に向かったのであった。
射場の東側に立った重蔵は、鉄砲がまさに火を吹くという寸前に、持っていた槍の石突きを西日に反射させて、射手の目をくらませてしまった。いずれの弾も当たらず、鉄砲が鳴り終ったとたん相手の懐に飛びこみ、鉄砲をたたき落としたという。重蔵の知恵とその豪胆[ごうたん]さとに殿様は、大層感心されて、許したのである。
さて、その頃、この広い十津川郷では、郷寄[ごうよ]りという会合があった。十津川郷内の代表者が川津(地名)に集まったのである。
このとき猿飼(高森は小字)の森定蔵(屋号北村)が庄屋をしていて、重蔵を供にして川津へ出掛けたのである。
ここで郷寄りをしている最中、数人の浪人が剣道の試合を申し込んできた。ところが代表者たちの中には、あいにく腕のたつ者がいなかった。どうしたものかと思案していると、森定蔵が、
「わしの供として連れてきた高森重蔵と申す者だが…この者にそなたたちのお相手をさせよう。」
と、言った。
供の者が相手とは…。少々不満気な顔付きであったが、定蔵は浪人たちにおかまいなく、重蔵を呼びにやった。重蔵は、谷川から水を桶で汲み上げていた。浪人の相手をせよ、といわれた重蔵は、水汲みのおうこ(天秤棒)で立ち向かった。たちまち浪人たちを打ちすえて、また、何事もなかったように、水汲みに精を出していたという。
供の男でもこれほど強いのであるから、これから十津川郷中奥深く入っていけば、さぞかし強い者がいるにちがいない、と考えた浪人たちは、ほうほうの体[てい]で逃げ帰ったということである。
記録 林 宏
再話 松実 豊繁
(80) 飛ぶお椀
これは果無[はてなし]にあった話じゃ。
果無に果無谷ちゅう谷があって、そこに果無滝があるのを知っとるか。あんまり大きい滝じゃないけんどのう。
むかしむかしのことじゃった。いつの頃からか月に一回、昼すぎくらいになると、この滝からお椀が飛んでくるんじゃ。「ウウーン」という音をかすかにたてて飛んでくるんで、すぐわかるんじゃ。迷惑かけてはならんと思っていたのか、同じ家に続けて飛んでくることはなかったらしいよ。
飛んできたお椀は、まるで目が付いているようで、めあての家の人が外で働いておれば、その人の側に、家の中におれば、その空いた窓からスーッと入って目の前にとまるんじゃ。
お椀は何しに来たと思う。
お椀の着いた家の人は、その中へ麦飯や粟飯をてんこもり(山盛)についでやるんじゃ。漬物があればそれもつけてな。そうするとお椀は、フアーと浮いて「ウウーン」と果無滝へ帰っていくんじゃよ。
あるときのことじゃ。いつものようにお椀は飛んできたよ、そしてちょうどマヤゴエ(牛の糞)を出している男の前に止まってしまったわ。その男は、大層なめんどくさがりやであった。ちらっとお椀を見たが、臭さは臭し、おまけに暑い日であった。
「ええい、このくそ忙しいのに、しちめんどうくさいお椀じゃ、この牛の糞でも食らえ。」
いきなり、お椀の中へ糞をほうり込んでしまったんじゃ。おわんはそれでもゆっくり浮き上がると、「ウウーン」と小さい音をたてて、いつものように滝へ帰っていったんじゃ。
それっきりなんじゃよ。お椀は、もう二度と飛んでこなかったんじゃ。
話者 高森 森 隆
再話 松実 豊繁