(121) 笠成島のごうら
ずいぶん昔のことである。ある夏の土用時分に、良い天気が続いた。川の水はうんと少なくなり、川水がくさってきた。(藻がついてきた)どうやらごうらが住みついたらしいと、村人が言いだした。
もともと、折立山崎の川向こうの笠成島の大きな石の下には、ごうらが住んでいるといわれていた。
折立山崎の中元に鉄四郎という者がいた。鉄四郎は天気続きの昼さがり、牛に水浴びさせようと思い立ち川へ連れていった。
牛を川に入れ、体を洗い、しばらく泳がせていた。やがて牛を川から上げ、川岸にある椿の木に牛をつないで、木陰で休んでいた。
ひとねむりして、ふと気がつくと、ごうらが川から上がってきて、牛の足を引っぱっている。こいつはおもしろい。ごうらのやつ、牛を川の中へ引き込もうとしているのだな。しばらく様子を見ていてやれ。
ごうらのやつ、この牛ぐらいは川へ引っぱり込めるわいと思っているらしい。ごうらはいっしょうけんめいに引っぱっている。一方の牛は引かれまいとがんばっている。
しばらく戦いは続いた。やがて、様子が変わってきた。牛の力が強かったのか、あまりの暑さにごうらがまいったのか、ごうらは、力が尽きて倒れそうになった。鉄四郎は、すばやくかけ寄り、ごうらを生けどりにしたということじゃ。
話者 折立 玉置 藤夫
再話 那知合 後木 隼一
(122) 和田渕のゴウタロウ
 明治二十二年の大洪水までに奥里に(大字内原)下平という家があった。家は川の近くにあった。家族が山へ出掛けてしまうとばあさん一人になってしまうんじゃ。すると、どうしてわかるのかしらんが、和田渕から一匹のゴウタロウがはみ上がってくるのじゃ。ゴウタロウは、下平の家にあがりこんで、なべに残っているイモやムギかゆやらをひっくり返しもうて食べてしまいようる。ほんでから外へ出ると八手場[はでば](手場)にかけのぼり、つるしてある干しかイモをたたきおとす。それを食いちらすと、飼っている鶏のカゴを川までまくって喜ぶのである。もちろん、鶏を追い回して遊ぶのである。とにかく、ばあさん一人だと悪さの限りを尽くすのである。
明治二十二年の大洪水までに奥里に(大字内原)下平という家があった。家は川の近くにあった。家族が山へ出掛けてしまうとばあさん一人になってしまうんじゃ。すると、どうしてわかるのかしらんが、和田渕から一匹のゴウタロウがはみ上がってくるのじゃ。ゴウタロウは、下平の家にあがりこんで、なべに残っているイモやムギかゆやらをひっくり返しもうて食べてしまいようる。ほんでから外へ出ると八手場[はでば](手場)にかけのぼり、つるしてある干しかイモをたたきおとす。それを食いちらすと、飼っている鶏のカゴを川までまくって喜ぶのである。もちろん、鶏を追い回して遊ぶのである。とにかく、ばあさん一人だと悪さの限りを尽くすのである。
さて、ある夏の日のことじゃった。今日もばあさん一人しかいない。ゴウタロウが家の裏に回ると、ばあさんは畑でキュウリをもいでいた。
「ハハア、おれにとられると思って、こんなとこにも作ってあるのか。」
「ばあさん、ばあさん、おれも手伝ってやろう。」
と、声をかけると、
「おの(お前)みたいな悪さばっかりするもんに手伝うてほしいことはないわい。」
「ほれ、これでも食ろうて早よう川へいね(帰れ)よ。」
と、ひねた黄色いキュウリをポンと投げてよこした。
それでもゴウタロウには、ごちそうらしい。ボリボリ食べてしまうと、
「もっとくれ。」
と、言うた。
「あきれた 食らいびっしょじゃのうら、もう、おのにやるもんはないぞ。」
「ばあさんよ、そこのつけかごにいっぱい入っとるがいだ。」
「それはあかん。わしらの食うもんじゃ。」
「それがあに、いろうに。おれにちいと分けてくれ。」
と、言ったかと思うと、つけかごにとびついてひっくり返してしもうた。ぶち撒いたキュウリを半分食ってはほうり投げ…その早いこと早いこと。あっけにとられていたばあさんは、
「まったくおのれはよう食らうのうら。」
と、おめきもうて、えらい勢いで畑をかけ下りて来た。びっくりしたゴウタロウは、
キャッキャッ、笑いながら下の川原へ逃げて行ってしもうた。
業を煮やしたばあさんは、ゴウタロウをやっつける方法をいろいろ考えた。
またまたある日。ゴウタロウは、下平のばあさんの家にのぼっていった。表に立って中に入りかけたところ、かまどの横にばあさんが座っていた。何だかうまそうな、香ばしいにおいがする。どうしようかなあと迷っていると、中からばあさんが、
「まあ、遠慮せんと入れよ。」
と、笑いかけてきた。
これはまあ、どうした風の吹き回しかいなと、怪しんでいると、
「のう、ゴウタロウよ、なんぞ食いたいじゃろう。ここにキリコを煎ってあるよって食うてみらんか。」
キリコというのは、もちを賽[さい]の目に切ったものである。
「ハハア、さっきの香ばしい臭いは、キリコを煎っていたのか。」
「食うてみらんか。」と言われて遠慮するようなゴウタロウじゃない。トコトコと入り込んで、右手をめっぱの中へつっこむと、キリコをわしづかみにして食うたんじゃ。もちろん立ったまんまじゃ。
「のう、おのよ、うまかろうが。」
「口の中でごろごろするわい。けんど食えんもんでもないな。」
ぼろぼろ口からも手からもこぼしながらそう言った。
「ちょっとばあさんよ、のどが乾いてきたぞ。」
「ああ、そうか、ほんなら茶をやろう。」
ばあさんは、すりばちにたっぷり入れた茶を差し出した。
「ばあさん、いやに黒い茶じゃのう。」
「さあ、グッと飲め、精がつくんじゃぞ。」
「そうかそうか。」
ゴウタロウは、一息にゴクッゴクッと飲んだ。
しばらくして、
「ばあさん、にがい、にがいぞ。」
「まだほしいか入れたるぜ、飲むか。」
「ばあさんよ、にがい、にがい、にがいぞ。」
「ばあさんよ、これは煤水[すすみず]とちがうか。ああ、にがいにがい、つらいよう。つらいよう。」
と、泣きだした。
「おお、煤水じゃあぜ。にがかろうが…。人間をあほにしくさるよってに、そがな目にあうんじゃ。」
ゴウタロウは、「にがいよ、にがいよ。」と叫びもうて表へとびだしていった。
煤水は、昔からカッパの大敵だと言われている。それをばあさんは、まんまと飲ませてしまったんじゃ。このことがあってから、和田渕のゴウタロウは二度と現れなんだという。
下平家は、明治二十二年の洪水のあとに北海道へ移住して、もうかれこれ百年になる。
話者 内原 亀田 文子
再話 松実 豊繁
(123) ツユクサの花
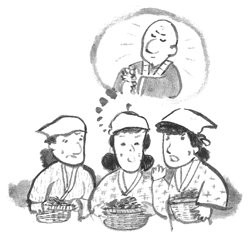 今西の中ほどに風呂の岡というところがある。
今西の中ほどに風呂の岡というところがある。
ずっと昔のこと、今西に泉昌寺[せんしょうじ]という寺があったそうだ。この寺に間佐久[まさく]という坊さんがいたと。この坊さんには奥さんがいて絹糸を撚り、薄布を織るのがたいへん好きだったと。夏になると、織り上げた布をツユクサの花で染め、美しい着物に仕立てては着ておったと。
この絹を染めるツユクサの花は、朝早く花に露のあるうちに摘まぬと、染料として役に立たぬほど、可憐でか弱い花なんだ。
間佐久坊は、奥さんのために、今西の女たちにツユクサの花摘みをさせたと。これがまた、毎朝早くからやらされるものだから、女たちにとっては大変だったと。
ある年の夏のこと、また、いつもの年のようにツユクサの花摘みが始まった。毎年こんなしんどいことが続くものだから、人々の不満は次第に高まっていったと。
「こう毎朝ツユクサの花摘みさせられちゃ、とてもかなわんのう。」
「何とかならんもんじゃろうか。困ったことじゃ。」
「みんな花摘みしとるが、ぶつぶつ怒りようるわよ。」
何人か集まれば、この坊さんのやり方に不満を出し合っていた。
「こうなったら、何とかせにゃおさまらんのう。」
「そうはいうても、なかなか良い智恵も浮かばんでのう。」
「坊さんを諫[いさ]めるいうたら、よっぽど心してかからんといかんと思うしな。」
「うん、うん。それでまいっとるんじゃよ。」
そうこうしているうちに、話は次第に険悪な方向へとすすんでいったと。
「なるもんなら、なんとかまるくおさめられんかのう。はやる気持ちは、わからんでもないが。」
「これまで、そうならんかと、みんな考えてきたんじゃよ。」
「他によい方法とかいうてもなかろう。」
「それでな、ここまできたら、こうこうしかじか………というところでどうじゃ。」
「そりゃ、ちょっと気の毒じゃないかな。」
「なら、どうせいいうのじゃ。おめえに名案でもあるというのか。」
「それがないから困っとるのじゃ。ことがここまできたら、もうしかたがなかろう。」
「そうと話がきまれば、首尾よくやることにするか。」
このようなことで、まことに物騒なことだが、みなの話はまとまり、手分けをして、仕事に取りかかったと。
話とは、お寺の古くなっている風呂を新調し、吉日[きちじつ]を選んで坊さんに初風呂に入ってもらおう。その機に手抜かりなく、坊さんにあの世へ旅立ってもらおうとの寸法であったと。
そんな事情など露知らぬ間佐久坊、寺のために風呂を新調してくれるものと喜んでいたと。
幾日かたって、風呂は完成し、坊さんに初風呂を使ってもらう日になったと。この日、若者たちは懸命に働き、日も西に傾きはじめた頃には、準備もすっかり整っていたと。
さあ、初風呂に入ってもらおうと、坊さんを呼びにやり、快く湯に入ってもらったと。
「湯かげんはどんなもんじゃ。」
「まことに結構じゃよ。風呂は新調してもろうたし、香りもよいし、こんな幸せなことはないよ。」
「それはそれはどうもありがとう。どうぞごゆっくりと。」
こんな話の中でも、風呂の下では、薪[たきぎ]がどんどんくべられ、やがて油断している坊さんに、地獄行きの風呂の蓋がされ、さらに若者たちによって蓋の上に大きな重石[おもし]まで載せられてしまったと。
人々の心が読めなかった坊さんは、憐れであった。
石川五衛門ほどの悪人ではあるまいし。ツユクサの花摘みの他にどんな罪状があったというのか。
坊さん、南無阿弥陀仏でも誦[とな]えながら、魂は昇天したであろうか。
坊さんの非業[ひごう]の死で奥さんの涙やいかに。
その後、坊さんを焚き殺した場所を、風呂の岡と呼ぶようになったということである。
話者 今西 鎌塚 恒文
再話 那知合 後木 隼一
(124) 栄宝院慈観法師
上湯川[かみゆのかわ]、大井谷の野地[のじ](家名)の近くに、栄宝院慈観法師のお墓がある。
およそ四百年余りの昔、どこからか一人の落武者がやってきて、このあたりを拓[ひら]いて住みついた。耳の不自由な人であったが、学問もあり、大変かしこい、やさしい人で、里人からも好かれていた。墓の主は、この人である。
以前、この付近には、野地・大屋野・文造・栗栖という四軒の家があった。毎年、慈観法師のお祭りとして、餅まきなどもしたらしい。今は、野地・一軒だけである。野地では、この法師の供養を続けており、大井谷開拓の祖として、大切にお祀[まつ]りしているようである。
この慈観法師のお墓に、穴のあいた耳石を供えると、不自由な耳が治ると言われている。昔は、遠くからでも耳石をもってお詣りしたということである。
また、この墓の近くの竹薮の中には、古い墓がたくさんある。このあたりが早くから拓けていたことを物語っていると言えよう。
記録 永井 勝山 やさ子