(11) 明治の大水害(2)
あの大水害が起こったとき、徳松[とくまつ](わしらの父)は十八才じゃったらしい。
明治二十二年八月十九日、やっと夜が明けてみると、たいへんなことになっていた。谷瀬[たにせ]の在所にある四つの谷は、どれもこれも目もくらむような大水で、大地がただゴウゴウと鳴るばかりじゃった。
親戚の沼部権八郎[ぬまべごんぱちろう]とこの土蔵がミシリ、ミシリと無気味な音をたてて傾きだした。「これは、あぶない。」と、権八郎夫婦が外へ飛び出したのと、上の山から鉄砲水が落ちてくるのと同時じゃった。二人はギャアと、一声残したまんま逆巻く泥水の中に巻きこまれていった。それは、まったくあっという間のことじゃった。
やがて、これを聞いた徳松は沼部宅へ駆けつけようとしたが、いつものから谷(水のない谷)も、きょうはまったく通れない。思案あまって、氏神さんののぼり竿を向こう岸に倒し、それにつかまってやっとで渡り、沼部へ来てみれば、土蔵は倒れ、その上を滝のように土水が落ちていくばかりじゃった。
その日から幾月か経ったある日、ガアガアと烏があんまりさわぐので、二、三人の男衆が近づいてみると、えぐり取られた谷底の埋もれた木の株に、白骨になった死体がかかっていた。おそるおそる近寄ってみれば、着ていたてしま(雨具)の焼印から権八郎の嫁と判った。けれど、権八郎の遺体はその後も、とうとうあがることはなかった。
この大水害で、谷瀬の田や畑はほとんど流され、家も埋もれたり倒れたりして、在所は全滅したみたいじゃった。
今日のように作り戻し、建て直すのには、何十年もの歳月がかかったということじゃ。
話者 谷瀬 森岡 良孝
再話 大野 寿男
(12) 天誅組のこと(1)
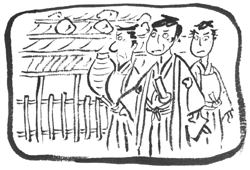 天誅組が五條代官を襲って騒動を起こしたころ、わしの祖母は、まだ十七じゃったそうな。
天誅組が五條代官を襲って騒動を起こしたころ、わしの祖母は、まだ十七じゃったそうな。
その天誅組は五條から天辻峠を越えて十津川へやってくるという。そして、その一行はこの谷瀬[たにせ]へも寄るらしいという知らせで、在所は色めきたった。いよいよ、谷瀬に立寄ることになったのじゃが、そのとき、庄屋から、いかなることがあろうとも決して無礼のないよう心がけよと、きついふれが回わされた。
どの家でも、だいじな客人じゃというので、米の飯を炊き、できるだけのご馳走をこしらえて待っていると、とうとう一行が在所の峠に現われた。きちんと列を組んで、鎧やたれの音をジャラジャラいわせながら、いかめしい様子で在所へ入ってきた。一行は二・三人ずつ組になって分宿[ぶんしゅく]することになったが、庄屋の中村宅へは中山首領が泊ると決まった。祖母の家には三人の侍が泊り、となりの家へは近侍[きんじ](おそば付きの武士)が泊り、組一行がいる間は、決して鉄砲を撃ってはならぬとの、きついおふれが回わされた。
ところが、佐田甚五郎[さだじんごろう]は、近くの山にきじがいるのを見つけ、つい、おふれを忘れて、そのきじをズドンと一発撃ってしまったのじゃ。すると、たちまち近侍がやってきて、直ぐ本陣(中村宅)へ連れていかれた。おん大将の前へ引き出された甚五郎は、
「ちょっと待ってくだされ。」、
といってそのきじを丸い盆にのせて献上したものじゃ。すると、おとがめどころか、それはでかした、とたいへんほめられ、多少の金子[きんす](お金)までたまわった。
在所の衆が、一体どうなることかと心配しているところへ、甚五郎、
「ワッハ、ハ、ハ、……」
と、高笑いしながら、悠悠と帰ってきたので、みんな、やれやれと胸をなでおろした。
天誅組はいく日か泊っていたが、やがて、つぎの土地へ転進と決まり、在所の衆は、その手伝いをさせられることになった。組本陣から、どの家からも一人ずつ人足を出すようにと、指図があったので、祖母の家からは、まだ娘だった祖母が出ることになった。
祖母が、おそるおそる本陣の中村庄屋の家へ上がってみると、いかめしいかっこうをした侍がいて、
「そちはいくつじゃ、名はなんという。」
と、ごせんぎがあったので、「年は十七、名は森岡モト。」と申しあげると、
「うん、うん。」
と、うなずき
「若いおなごに重い荷は無理じゃ。」
といって、胄[かぶと]入れの箱を持つことになったが、祖母は、いわれるままにその箱を背負ったそうじゃ。
「あの箱は、なかなか重いものじゃった。」
と、祖母はそのときのえらかったことを、後あとまでよく語っていたものじゃ。
話者 谷瀬 森岡 良孝
再話 大野 寿男
(13) 天誅組のこと(2)
 天誅組が五條代官所を襲って、何日かたったある日、谷瀬在所の若衆たちは、五條へ買いものに行くことになった。泉谷龍平[いずたにりゅうへい]は、在所の娘ら(祖母も十七才で、その中にいた。)を連れ、朝早く谷瀬をたった。
天誅組が五條代官所を襲って、何日かたったある日、谷瀬在所の若衆たちは、五條へ買いものに行くことになった。泉谷龍平[いずたにりゅうへい]は、在所の娘ら(祖母も十七才で、その中にいた。)を連れ、朝早く谷瀬をたった。
龍平たちは、おおかた一日かかって五條に着き、買いものをすませると、代官所あとへ行ってみた。すると、代官鈴木源内[すずきげんない]とその家来たちが、けさがけに切られ、張りつけになっていた。
さすがの龍平も、ぶるぶる震えが止まらなかった、ということじゃった。
その頃、天辻には天誅組の陣屋があって、通行人は、ほおかぶりはならん、というきついおたっしがあった。
けれども、龍平は、買いものを一荷[いっか]天びん棒でかつぎ、女どもを後に続かせて、ほおかぶりを取らずに平気な顔して陣屋を通ったそうな。その後に続いていた女たちは、おとがめがあったらと、ひやひやしどおしで通してもらったという。
龍平というのは、なかなかの度胸者じゃったらしい。
話者 谷瀬 森岡 良孝
再話 大野 寿男
(14) 旅籠「上西」のむかし
たしか、大正三年のこと、わしが数えの五つのときじゃった。
神納川[かんのがわ]にいる叔母は、子なしでさびしいから、連れがほしいというので、わしは、それから三年もの間、この叔母の家で暮らすことになったのじゃった。
叔母は中西ミワといって、その頃、村議会議員じゃった中西文太郎の後妻で、上西という旅籠の女将[おかみ]さんじゃった。この上西は、その昔、高野街道(高野山-野迫川-十津川-熊野)の難所、伯母子峠[おばことうげ]から五百瀬[いもせ]に通ずる街道の中途にあったのじゃ。
今から七〇年ほど前は、高野からこの伯母子峠を越えて馬が米・さかなをこの十津川へ運んだわけだ。
上西は山の上じゃったで、日の出は格別きれいじゃったし、晴れた日の見晴らしは、山々が雲の上に青く連らなって、ちょうど天の国にいるみたいじゃった。
早い朝が明けると、伯母子の方から、チリンチリンと鈴の音が響いて、二頭も三頭もの馬が、背中にいっぱい荷を積んで下ってきたものじゃった。馬子[まご]たちは、上西で一服すると、下の五百瀬へと下りていくのじゃった。そして、その帰りも馬子たちはお茶を飲んで行ったものじゃった。
この上西のあるあたりは、新宮の門新[かどしん]の持ち山で、いつも人夫たちが泊っていたようじゃった。
また、上西では、牛を二頭も飼っていたし、家の周りは広い畑で、野菜もいかいこと(たくさん)とっていた。上西のナンキンとジャガイモは北海道にも負けんぐらいうまいと、客の評判じゃった。田んぼは山を下ったところに少々あったようじゃ。
高野詣[こうやもうで]の人たちが行き来していたが、毎年、春から夏にかけては、巡礼さんがおおぜい泊り、夜の更けるまで御詠歌[ごえいか]が止まず、それはにぎやかじゃった。
上西から五百瀬へ下る途中に、たしか大師堂があったようじゃ。昔、大師様が持っていた杖を投げると地面に突きささって、その杖から芽が出て大木になったというのじゃ。ところが、その木から出る枝は、みんな逆さについたということじゃ。わしもその木を見たものじゃった。
冬の大雪で伯母子越えをしようとした旅人が、死人のようになって連れてこられたこともあったな。雪のときでも、山登りをする若い男たちが、組を組んで伯母子の難所に挑んだようじゃった。
今は、この高野街道を通る旅人はおらず、この上西という旅籠は跡形もなく、深い山の中に消え失せてしもうた。
叔父、文太郎は、先妻との間に二人の男の子をもうけたのじゃが、弟の方は若死にしたし、兄の方は、早くから家を出て帰らず、風の便りでは、勝浦方面で魚を商い、一家を成しているという。
高野街道の移り変わりとともに滅んでいった旅籠「上西」の話じゃ。
上西は、杉清[すぎせ]より五〇町も登った山の中の一軒屋じゃった。
話者 滝川 下村 タカノ
再話 大野 寿男
(15) 間引のこと
わたし(森下みな)とおない年の者が二十三歳で死んだことがあった。その葬式のときに、父が、
「あの子は、生まれたときから寿命がなかったのだ。」と妙なことを言う。不思議に思って尋ねると、その人は末子として生まれたのだと言う。ところが、生まれ出てきたとき、産湯[うぶゆ]を使わせようとした産婆の手をとめたその子の父親が、
「洗わないでくれ、わしには、もうこの子に食わせるものがない。そんで、紙を顔にはるつもりじゃ。」という。
紙をはるとは、ぬれた和紙で鼻と口をおさえて窒息させるということだ。
周りで手伝いをしていた人たちは驚いて、
「そんなむごいことをするな。」と、とめたそうだ。お産をすませた母親は、涙を流したまま横たわっていた。父親は、周りの人たちのいさめに、ついに負けて育てることにした。しかし、一度、あの世に送りこまれそうになったためか、早死にしたのだ、と父は話していた。
間引きされたのは、身上[しんしょう]つぶしといわれた女子[おなご]が多かったという。
話者 上葛川 森下 みな
再話 松実 豊繁
(16) 迫の平岡シシトリネ
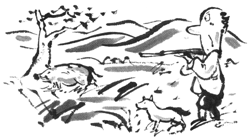 昔、旭の迫という村に「迫の平岡シシトリネ」と呼ばれた、狩りの名人が住んでいた。 ある冬の日のこと、男はいつものように狩りにでかけた。慣れた山道をゆっくり登っていくと、突然前方の茂みがザワザワと激しく揺れた。「おっ、獲物だな。」とほくそえんで銃を構えた。なんであるかわからないが、とにかく、茂みがいちばん揺れているあたりをめがけて「ズキューン」と一発うった。そのしゅんかん、何かわからんが、たいそう大きな獣[けもの]がとび出して、道を横切り別の茂みの中へ音をたてて逃げ込んだ。
昔、旭の迫という村に「迫の平岡シシトリネ」と呼ばれた、狩りの名人が住んでいた。 ある冬の日のこと、男はいつものように狩りにでかけた。慣れた山道をゆっくり登っていくと、突然前方の茂みがザワザワと激しく揺れた。「おっ、獲物だな。」とほくそえんで銃を構えた。なんであるかわからないが、とにかく、茂みがいちばん揺れているあたりをめがけて「ズキューン」と一発うった。そのしゅんかん、何かわからんが、たいそう大きな獣[けもの]がとび出して、道を横切り別の茂みの中へ音をたてて逃げ込んだ。
「確かに手応えがあったぞ。」
男は犬に後を追わせ、自分も、また、その後を追った。血が点々と枯草や葉っぱについている。林を過ぎ、やぶをくぐり、いくつかの谷をわたり、三つの峰を越した。しかし、獣の逃げ足は意外に速く、小さな谷へ降りたとき、あたりは暗くなりかけていた。「山上で陽[ひ]を見てはならない。」という鉄則を男はすっかり忘れていた。
さすがに疲れた。谷の近くに手ごろな岩屋があった。男は野宿の決心をした。「ホーイ、ホーイ。」と暗くなった山に向かって犬を呼んだ。枯れた杉の葉を拾い集め火をつけた。そして、あたりに落ちている枯木を集めてたき火を始めた。火は、夜中燃やしていなければならない。寒いだけでなしに、狼が来るかもしれないからである。やがて、犬が戻って来た。体全体で息をして、舌は土につかえるほどだらんとたらしている。
「おうおう、よしよし、腹もへったやろ。さあ、飯をやろう。」
持って来た握り飯のいくつかをおき火であぶって与えた。干し肉も与えた。よほど、腹が空いていたのだろう。犬はガツガツ食べた。
男も握り飯を食べた。おかずは、大根やきゅうりの漬け物である。それをそのままバリバリ食べた。また、岩壁にへばりつくように生えている岩チシャに手をのばし、火にあぶり、みそをつけて食べた。
風もなく何の物音もしない。谷川も音をたてずに流れている。山の上には、星がいくつもチカチカ冷たく光っている。犬は前足を枕にして、すでに眠ったらしい。夜は静かにふけてゆく。
男は、太い枯木を幾本も火の中へくべた。
「さて、そろそろ寝るか。」夜気[やき]をさけた岩陰で横になった。眠りかけてから、はっと思い出したかのように、ぶつぶつとまじないを始めた。たき火の暖かさで眠気に誘われてたまらない。男は、横になったまま、
「天くくる、地くくる。四方四面閉めくくる、ナムオンケンソワカ。」
これだけ言うと昼の疲れがどっと出て寝こんでしまった。
どれくらい時間がたっていたのか、それは、わからない。迫の平岡シシトリネは、耳元で誰かがしゃべっている声や笛や太鼓のにぎやかな音で目が覚めた。ねぼけまなこで、とろとろと燃えるたき火の方へ目を移すと、なんと、その周りで小さい人たちが、笛を吹き、太鼓をたたいてにぎやかに踊っているのである。枯木の上に腰かけて、おしゃべりに夢中になっている人たちも何組かいる。どの人たちも神主のような白い服を着、なかには、白いひげをはやした者もいる。男は、ぼんやりと、この光景を横になったまま見ていた。夢なのか現実なのか。
そのうちに、男のいちばん近くにいる二人の小さい人たちの話し声が、耳に入ってきた。
「ところで、きょうの迫の平岡シシトリネの獲物はどうだった。」
「それがな、長年この山に住んでいた大イノシシでなあ。ついに迫の平岡シシトリネにつかまってしまったよ。」
「それで、弾はあたったのか。」
「急所はそれてのー。あっちこっち逃げまわったが、とうとうあいつも判断が鈍ってなあ、この山の向こうの崖から谷へ落ちてしまったよ。」
「ほう、それで、その大イノシシは迫の平岡シシトリネにたたってゆかないのか。」
「それがだ。迫の平岡シシトリネは、なかなか律義[りちぎ]な男でな、千頭とったら千頭の供養をきちんとしておる。だからたたるわけにはいかんのだ。それに、この男は、今までに小さい動物は絶対にとってないんじゃ、実に感心な男なんじゃ。」
「じゃあ、あしたは大イノシシを見つけて、無事、山を下りることができるわけだ。」
「そういうことになるな。」
迫の平岡シシトリネは、この小さい人たちは、神様なんだろうか、と考えているうちに、また、深い眠りに落ちていった。
犬のほえ声で目が覚めた。ゆっくり目を開けると、犬は男にさかんにほえているのだった。夕べのできごとは、あれは、夢だったのだろうか。あの神主のような白い着物を着た小さい人たちは、神様だったのだろうか。……いや、そうに違いない。ぼんやり頭の中で考えていたら、犬が、またまたほえた。
「おお、おお、よしよし、お前も腹がへったか。お前も昨日の獲物が気になるのじゃな。」
どっこいしょ、と立ち上がろうとしたが、立ち上がれない。一体どうしたんだろう、と一瞬考えたが、すぐ、夕べのまじないを思いだした。そこで、
「天開く、地開く。四方四面押し開く、ナムオンケンソワカ。」
と、唱えた。体は自由になった。谷川で口をすすぎ、夕べの残り物を犬と分け合った。
白い服を着た小さい人たちの、「大イノシシは崖の下に落ちている。」ということばを信じて、谷をわたり、道のない山へ分け入った。比較的低い山で、小一時間もすると高い崖の上に出た。崖の下には谷川が流れており、その水ぎわにあの大イノシシが倒れていた。小さい人たちが話していたとおりであった。
迫の平岡シシトリネは、その一生のうちに、熊やイノシシ、カモシカなど三千頭もとった人だったという。
話者 旭 岸尾 富定
記録 上野地小学校
再話 松実 豊繁
(17) 東中の七人塚
東中の小高い丘に七人塚がある。これには、次のような伝説が残っている。
むかし、むかしのこと、玉置山に侍一家、七人が住んでいた。どこから流れてきたか、全く不明である。やがて、東中に下りて住みついてしまった。
この一家の主人は大変な弓の名人で、射た矢文は玉置山の裾を越えて、小川の徳屋に届いたほどであった。
東中に移り住んで来た初めは、良い一家であったらしい。しかし、非常になまくらな一家で、東中に、自分たちよりも強い者がいないことがわかると、しだいに乱暴をしでかすようになった。
どんなことをやり始めたかというと、対岸の山道を通る人を弓で射て、田戸[たど]や板屋[いたや]から買ってきた、わずかの米や塩を奪いだしたのである。主人は弓の名人であったから、はずれることはない。細々と暮らす山村の人達が、やっと手に入れたものを、奪って暮らそうとしたのだから、ひどい侍一家もあったものである。
小川の徳屋という者も侍だったようで、この一家も同じようなことをして暮らしていた、と言われる。
東中の住人たちは、非常に困っていた。あの一家を何とかしなければならん、と考えた人たちは、寄り合いを開いて、酔っぱらわせて殺すことに決めたのであった。そこで、村の酒屋でたくさんのドブロクを作った。
ある夕方のこと、東中の代表がおずおずと侍一家の前に出て、ごちそうと酒の用意もできたので、ぜひ出席してくれるよう頼んだ。しかし、住人のこの親切を怪しんだ一家は、なかなか来なかった。日頃、自分たちのことを地元の人たちが、良くは思っていないことを感じていたからだった。東中の代表は二度、三度と誘いに来た。代表も度胸をつけるために、少々酒を飲んでいたので、四度、五度と誘いに来る人の顔付は、いかにもめでたい様子である。どうやら村人にたくらみはないらしい、とわかってきたが、七度誘いに来ても、行こうとはしなかった。そのうちに夜風にのってにぎやかな歌まで流れてきた。とうとう八度目の誘いがあった。元々酒好きだったその一家の主人は、今来た代表が酒のにおいをプンプンさせているのにがまんできなくなった。
侍一家はすっかり警戒心をなくして酒盛りの席へ行った。そして、主人以下全員がたらふく酒を飲み、たらふくごちそうを食べた。完全に気を許したのだろう、ぐっすり寝込んでしまった。
酔って寝込んでしまうのを待っていた人たちは、わっとばかりに襲いかかって緒[ひも]や荒縄で縛りあげ、東中のはずれにある、小さな丘まで担[かつ]いでいった。そこには、すでに大きな穴が掘られていた。その中へ一家は投げ込まれた。七人は石で詰められてほうむられたのであった。一家七人であったので、侍の女房も子どももいたわけであろう。
一家が埋められたところは、いつしか七人塚と呼ばれ、小さな石が載っている。一家の住んでいた跡は、佐賀屋敷と呼ばれ、今も残っている。もしかすれば、その一家は佐賀という姓であったかもしれない。
(東中を流れる葛川に「もとどり渕」がある。これは、この一家の侍たちのもとどり(ちょんまげ)を切ったところという。現在、七人塚は、東中の人々によって、正月、盆、彼岸にまつられている。)
話者 東中 中西 勇
再話 松実 豊繁
(18) 釜中の七人塚
 今西の在所から、約一里ばかり行った所に、釜中という小字がある。今では、もう大きな杉木立の中に屋敷跡や朽ちかけた空き家が見られるだけの所となっている。
今西の在所から、約一里ばかり行った所に、釜中という小字がある。今では、もう大きな杉木立の中に屋敷跡や朽ちかけた空き家が見られるだけの所となっている。
さて、この釜中を開いたのは、奥州から来た落人[おちゅうど]釜中将監[かまなかしょうげん]だという。将監が奥州で住んでいた所が釜中だったので、今西に住み着いた所にも釜中という地名を付けたそうだ。
将監は、釜中で暮らしている間に、土地を次々に拓[ひら]いていき、大屋、下根[しもね]、今中、吉本、左垣内[ひだりかいと]、古矢倉[ふるやぐら]、馬場平[ばばんだいら]の七戸を築いたという。
将監が釜中へ来た時の事情を書いた、五尺余りの巻き物は、現在もあって、新宮のある人が持っているという。
ところで、戸数はふえていったが、各戸とも、当時の生活は相当きびしいものであった。田畑で作る作物だけでは足りず、椎の実を拾っては炒って食べ、草や木の芽を摘んではおかずとし、よもぎの葉を茶の代わりにして飲んだという。
大屋の主人は猟師で、山ではいのししやきじを捕り、川ではうなぎやあめのうおを釣って食膳をにぎわせていたそうだ。
家が川の近くにある大屋の主人は、「この細々とした暮らしを何とかせにゃならん。ようし、川向こうの馬場平の下の柿の木佐古を開墾しよう。」と思い立った。家族みんなでカを合わせて働いたので、やがて、三畝(三アール)あまりの畑を拓くことができた。
ある日、主人は畑に肥[こやし]をやるため家から馬の糞を運んでいた。何度か運んでいる途中、谷のそばで一休みした。そして、これからの生活のことを、いろいろ考えめぐらしていた。
主人の足元から四、五十メートルの下には、高さ十メートルばかりの不動滝(不老滝ともいう)があった。じっとその滝を見つめていた主人は、何を思ったのか、馬の糞を背負ったまま、谷へ下りて行き、不動滝の上に出た。
昔から、不動滝には主[ぬし]が住んでいる、といわれていた。主人もそのことは知っていた。
だが、この日の主人の様子は普段と少し変わっていた。「不動滝に主がいるという昔話なんか信用できない。もし、本当にいるというのなら、一つ試してやろうじゃないか。」と、背に負っていた馬の糞を下ろし、「もし、不動滝に、主がおるんなら、姿を見せてみい。」
いうが早いか、滝めがけて投げこんだのじゃと。
すると、これまで静かだった清流は、みるみる茶色に変わり、滝の下[しも]の青々としていた流れもにごってしまった。そのときである。渕のあたりから、突然、金色の美しい鳥が、空高く舞い上がった。そのとたん、主人の目はくらみ、異様な恐ろしさに、胸もしめつけられるようだったという。しばらくして、我に返り、恐ろしさにふるえながら家に帰った主人は、大いにおどろいた。さっきまでの和やかな雰囲気からは、想像もできない光景であった。家族はみんな、何かに押えつけられたような状態で、身体はしびれ、身動きさえできないありさまになっていた。やがて、家族は、もだえながら次々に息を引きとっていった。主人も、次第に体の苦しさを覚え、まもなくこの世を去った。また、家で飼っていた馬や猫、犬からにわとりまで全部死んでしまったということである。
近所の人はもちろん、今西全体の人たちも、「これは、偶然ではない、きっと神のたたりであろう、心すべきことだ。」と話し合い、亡骸[なきがら]を大屋の下に葬った。これが釜中大屋の「七人塚」と言い伝えられているものである。今では、わずかに墓石に月峯相信士と桂月秋雲信女の二人の名がみられるのみである。
(注、この話をまとめるにあたって鎌塚良彦氏より聞いたことも一部入れた。再話者)
話者 永井 羽根 秀壮
再話 後木 隼一
(19) 躍るタヌキ
 昔の瀞八丁[どろはっちょう]は、人気もあまりなく、青黒いふちが不気味に静まっていた。しかし、魚半分・水半分と言われるくらい、たくさんの魚がいたという。また、周りの山中には、岩穴がたくさんあって、タヌキのようにかしこい動物にとって、まったく暮らし良いところであった。
昔の瀞八丁[どろはっちょう]は、人気もあまりなく、青黒いふちが不気味に静まっていた。しかし、魚半分・水半分と言われるくらい、たくさんの魚がいたという。また、周りの山中には、岩穴がたくさんあって、タヌキのようにかしこい動物にとって、まったく暮らし良いところであった。
ある夕方のこと、里人に青石とよばれている平らな岩の上で、姉[あね]さんかぶりをした娘が一人踊っていた。それが、毎日続いた。それでも里人は、タヌキが踊っていることを知っていたので、
「ほい、また、青石で娘さんが踊っちょる。」と言って、気にもとめていなかった。
この日も、いつものように娘が踊っていた。山仕事の帰り、若者、庄右衛門[しょううえもん]は青石の方角を何気なく見ると、娘がさかんに手招きしている。あんまり手招きするもんで、おもしろ半分で近づいて行った。草をかき分けかき分け、やっと青石にたどりついたとたん、娘はふっと消えた。草の中にかくれたのか、と探してみるが、やはり娘はいない。青石をもう一度見ると、古いわっぱが置いてあった。
「やっぱり人が来ると恥ずかしいンかいな。」
と、ひとりごとを言いながら庄右衛門は
「これでも鶏のえさ入れぐらいにはなるやろう。」
と、古わっぱを拾って帰った。
次の日の夕方も娘が手招きするので行ってみたが、娘は消えて、古わっぱひとつだけが置かれてあった。それも、また、もち帰った。
三日目も同じだった。ところが、庄右衛門が古わっぱに手をかけたとたん、手を引くことも足を動かすこともできなくなった。金縛りの術にかかったのである。庄右衛門の背中を冷たいものが走った。そのときである。ドロドロと恐ろしい山鳴りが始まった。地面は、山崩れが起こるときのように、ユッサユッサと揺れ始めた。生きた心地もしなくなった庄右衛門は、
「こりゃあ、おれが悪かった。わっぱの置いてあったのは、何か食い物をくれ、ということだろう。それなら、すぐもって来てやるから、どうか勘弁してくれェ。」
と、さかんにわびた。そうすると、山鳴りも地面の揺れも静まった。体も、ようやく楽になった。
庄右衛門は、家にとんで帰ると三つのわっぱに、いっぱい食べ物を入れて青石の上に置いた。それを三日続けた。ある晩のこと、庄右衛門が仕事に疲れてうとうとと眠りかけていると、姉さんかぶりの、あの娘が夢の中に現れた。
「こないだから、お前に食べ物をねだったのは、わしが病気で困ってのことじゃ。おかげで今はすっかり良くなった。お礼申し上げます。」
と言った。そして、最後に本当の自分の姿を現して消えた。
それからしばらくして後のことである。庄右衛門は出稼ぎに行くといって、はっぴを着て家を出た。しかし、それっきり家に戻ってはこなかった。どこへ行ったのか、現在もわからない。
ところで、時々、姉さんかぶりをした娘と、はっぴ姿の若者二人が青石の上で踊っているのが見えた。あれが、庄右衛門だったのだろうか。
記録 神下 東 直晴
再話 松実 豊繁
(20) 音無川と十一面観音菩薩
沼田原[ぬたのはら]から、約一里さかのぼったところに大谷がある。そこには、三十メートルの高さの大きな滝がある。
むかし、むかし、この滝のずっと奥で、一人の仏師が、一心に十一面観音菩薩像を彫っていた。ところが、あまりの水音に気が散って思うように、のみをふるうことができない。考えあぐねた末、
「川の水よ、この菩薩様を彫る間は、どうか静かに流れてくれないか。」
と頼んだところ、願いはかなえられたらしく、水は、突然、川床から消えてしまった。それからは、心乱されることもなく、菩薩像を完成させることができた。この事があってから、この川の一部は川床を流れておらず、少し下流で、また水が流れ出している。それで、この川を音無川と呼ぶようになったのである。
さて、この菩薩像は、野瀬見[のじみ]のお寺に安置されていたが、明治初年の廃仏毀釈[はいぶつきしゃく]に人々は、村々の寺々をことごとく打ち壊し、灰にしてしまった。しかし この時、十一面観音菩薩像と黒仏[くろぼとけ]と呼ばれていた仏像二体は、心ある村の人の手で秘かに運び出された。黒仏は中井傍示[なかいほうじ]の宝泉寺[ほうせんじ]に預けられたままになっている。菩薩像は、沼田原のお堂に移された。菩薩像は、太鼓の音を聞かねば暴れる、という言い伝えがあったため、毎年、旧の正月十日と盆の十七日には踊りを奉納した。踊りは、篠原踊りをややテンポを速めたもので、詞[ことば]はまったく同じであった。現在では、踊りもすたれてしまって、中井傍示から、お坊さんが来て拝むだけである。
話者 沼田原 辻 隆章
記録 松実 豊繁