(21) 定の丘
 明治初年の廃仏毀釈[はいぶつきしゃく]のために、現在、野瀬見[のじみ]に寺はない。そのため、この伝説に出てくる坊さんの名前も年代も、わかっていない。全く謎である。
明治初年の廃仏毀釈[はいぶつきしゃく]のために、現在、野瀬見[のじみ]に寺はない。そのため、この伝説に出てくる坊さんの名前も年代も、わかっていない。全く謎である。
むかし、むかし この村の一人の男が、ふっといなくなった。そして、十数年ののち、この人は坊さんとして帰ってきた。どこで坊さんとしての修行をして来たものか伝えられていないが、とにかく、この野瀬見の寺に住まわれた。
ある年のこと大変な飢饉[ききん]に襲われた。作物は全く実らず、とちの実、おいもち(ひがん花)、葛の根、からすうりの根を掘り、松の皮まで食うありさまであった。やがて、それらも食い尽くすと、あちこちに死人が出始めた。どこの、だれともわからぬ者が、道ばたに倒れていることもあった。
このような様子を見たこの坊さんは、何を思ったのか、
「私は、定に入[い]る(僧が死ぬこと)のだ。」
と、言い出し、村人に、寺から少し離れた丘に、深い穴を掘ってくれるように頼んだ。やがて穴は完成して、何と、その中に坊さんが入るというのである。そして、
「私は、人々の苦しみを救いたい。私は、この中で錏[かね]をたたきながらお経をあげるが、この竹筒から錏の音が聞こえなくなったら、私が定に入ったと思ってくれ。」
と、言い残して、穴に入った。穴は埋められ、竹筒一本が空気穴として通されただけで、水も食物も入れられなかった。この竹筒を通して、七日七晩、錏の音と読経[どきょう]の声は聞こえた。しかし、八日の朝、ついに何の物音も聞こえなくなった。村人は竹筒を抜き、そのあとを埋めた。
月日が経ち、いつの頃か、その上に五輪塔が建てられた。
今も、沼田原へ行く道裏に五輪塔は、ひっそりと建ち、野瀬見を見おろしている。この丘のことを人々はいつの頃か、「定の丘」と呼ぶようになった。
話者 沼田原 辻 隆章
再話 松実 豊繁
(22) 男滝の龍
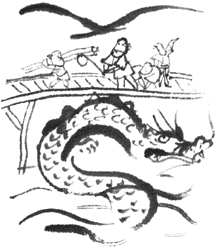 小井[こい]にある大矢の谷(親谷[おやんたき])には、いくつもの滝があって、深い渕には、水がドロッとよどんでいる。
小井[こい]にある大矢の谷(親谷[おやんたき])には、いくつもの滝があって、深い渕には、水がドロッとよどんでいる。
今から二百年も昔のことである。夏のころ大雨が降り続いて大矢の谷に架けてあった丸木橋が流されてしまった。この橋は池穴[いけあな]と小井とを結んでいた。
村の衆らは、木のひきかけた頃を見はからって橋を架けることにした。橋を架けるといっても、水はまだ恐ろしい音をたてて滝から滝へ流れおちているのである。水は真白に泡立って、今にもその中から言い伝えられている龍が、飛び出てきそうである。それでも旅の人の難儀を考えて、恐ろしさをおさえて工事にかかることにした。
このとき、一人の六部[ろくぶ](諸国をめぐる僧)が、池穴から小井へ向かっていた。雨で荒れた急な坂道を登って、やっと、大矢の谷の見える丘についた。心地良い風が吹いてきて、思わずかたわらの石に腰かけてほっと一息ついた。
汗がひくと、あたりの景色が落ち着いて見えてきた。大水の音がゴウゴウと聞こえる。谷は泡立ってところどころに見える岩は、飲みこまれていくようである。水のいきおいにおされるように、目を下へ下へ移してゆくと、村人が何人も大騒ぎしているのが見えた。どうやらこれから歩いてゆく道の橋がおちたらしい。その橋を架ける騒ぎのようだ。
「わしら旅の者のために、村の衆が難儀してくださるのか。ありがたいことじゃ。」
心の中で念仏を唱えて、じっと工事の様子をながめていた六部は、はっとした。
なんと、一匹の龍が、丸太を引き上げている村の衆を、そのヒゲで助けているのである。丸太を組み立てている人の足場は、龍の背中である。まるで龍と人間がお互いを知り合っているかのような作業ぶりである。しかし、村の衆は、龍の力を借りていることを、まるで知らないようだ。
六部は、ひどく胸を打たれた。「なんとありがたいことじゃ、なんと信心深い人たちなんじゃろう。」
ぼうぜんとしていた六部は、われにかえって山道を下っていった。念仏を唱えながら………
工事の現場は近くで見れば、ますますおそろしい。大矢の谷の水はまるで天から落ちてくるようである。水煙が雲のようである。龍のウロコのひとつひとつがはっきり見える。村の衆が、龍の背中に載ってかけやを使っている。トビで丸太を引き上げる。その男衆らの腰に、龍はヒゲを巻きつけ、転落を防いでいる。龍の目は、なんとも言えず優しげである。
村の衆は、手を上げて六部に橋を渡るよう合図した。六部にとって、この村の衆までが仏の使いのように思えた。
六部は、峯越[みねのこし]の森屋にたどりついた。そこで茶を飲みつつ、語るともなしにそこのばあさんに、
「今日は、大変いいものを見せてもろうた。」
「実はな、さっき通って来た谷でのことじゃが、村の衆が龍の背中に載って橋をかけておった。」
「へェー、そんなことがあるかねー。」
「いや、村の衆に見えなくとも、わしの目には見えるんじゃー。村の衆の引っぱる丸太へ、ヒゲを巻き付けて手伝うていたんじゃ。またな、落ちそうな村の衆の腰を、しっかりヒゲで巻いて転げ落ちんようにしておったんじゃ。なんともありがたいものを見せてもろうた。まるで夢のような光景じゃった。」
六部は、夢からさめるのを惜しむかのようである。
「そりゃ、もしかしたら男滝[おんたき]さんかもしれん。男滝さんの主[ぬし]は、昔から龍じゃちゅう話じゃあからのー」
と、森屋のばあさん。
「そうだろうなあー。」六部はつぶやいた。
夕方橋を架け終った村の衆が、森屋までもどってきた。全身ずぶぬれの男衆らに甘酒をばあさんはふるまった。ばあさんは男衆らの帰りがけに、さっきの六部の話をもちだした。
男衆らはびっくりしたようだったが、すぐ笑った。
中の一人が、
「確かに六部は通ったが……けんど、わしらは岩にのぼって作業をしたんじゃ……まあ不思議な話じゃが……」
「もう一ぺんもどって見ようらよ。もし龍が助けてくれたんなら、あの岩はないはずじゃあー。」
それもそうじゃ、ということになって、三、四人の若い衆が道を下っていった。外の者は、また茶屋にもどって、若者たちの報告を待つことにした。六部のことやら橋のことやら、大矢の谷の言い伝えのことなどが話題になった。
やがて、さっきの若者たちがもどってきた。一様に若者たちは青い顔をしていた。急いで来たばかりのせいではないらしい。
「どうじゃった。」と一人の年寄りが、心配気に声をかけた。
「ない、ないんじゃ。」
「何が、なにがないんじゃ。」
「さっき足場に使うとった岩が、全部ないんじゃ。」
「橋は。」
「橋は、ちゃんとかかっとるよ。」
そこまで聞くと、みんなは橋へ向って走り出した。
まだ半信半疑なのである。
ゴウゴウと流れおちる大矢の谷-その橋に集まった村の衆は声を忘れた。自分たちが足場に使ったりした岩は、本当にないのである。あるのは泡立って流れる水ばかりであった。
一人が手を合わせた。それにならって、そこにいあわせた者全部が、静かに手を合わせた。まるで、足が地についてしまったかのように村の衆は、いつまでも祈っていた。
話者 小井 古泉 安親
再話 松実 豊繁
(23) 東野の角左衛門の力
むかし、東野に角左衛門という、たいそう、力の強い男がおった。
ある時、この男が田戸[たど]へ来ると、米屋の主人が、冗談に、「この米俵三俵(百八十Kg)もって歩くことができたら、ただでやろうぞ。」といえば、角左衛門は本気になってしまった。田戸から東野といえば、遠いばかりでなく、額が道につくほどの坂道ばかりである。手ぶらで歩いてもしんどいくらい。米屋の主人は、まさか、いくら力があるといっても米俵三俵背負えるはずはないと、思っていた。ところが角左衛門、やにわに米屋のかたわらの竹薮に入って、青竹一本へし折ってきた。そして、枝をしごいて、足で竹をひしゃいでしまった。何にするのかと思っていると、その青竹をおいそ(太いひも)代わりにして、ひょいと三つの米俵にかけると背に負って、のっしのっしと歩きだしてしまった。
さあ、びっくりしたのは、米屋の主人。まさか、こんなに力があるとは知らなかったものだから、あわててしまった。元々、やる気なぞ小指の先ほどもなかったのだから、「オイオイ、もうわかった、おろせ、おろせ。」と、米俵にすがりついて、「どこにただで米をやるもんがおるもんか。」と、毒づいたそうだ。
角左衛門、口にこそ出さなかったが、よほどくやしかった。こたえたのだ。東野への帰り途[みち]、いきなり道の側にあった松を、片うででねじり曲げてしまった。それから、その松のある所を「ねじり松横手」と呼ぶのであるが、角左衛門の悔しさが、今もねじれたまま残っている。
角左衛門は実在の人で、東野へ降りる道端に小さな碑が建てられている。
話者 上葛川 森下 みな
記録 松実 豊繁
(24) 豆と天狗
 上葛川のうら山に天狗ぐらとよばれているところがある。そこは、岩がかべのように高く立っていて、今にもガラガラッところがり落ちてきそうである。
上葛川のうら山に天狗ぐらとよばれているところがある。そこは、岩がかべのように高く立っていて、今にもガラガラッところがり落ちてきそうである。
むかし、むかし、この天狗ぐらには、たくさんの天狗たちがすんでいた。たいへん悪さをする天狗たちで、空を飛んだり、すもうをとったり、そうかと思えばうちわで風をおこす競争をしたり、けんかをしたり、ふざけあったりして……そのたびに岩が落ちてきた。なかにはおもしろ半分に大きな石を、あっちの畑へドスン、こっちのたんぼへドスンと投げ落とすものもいた。岩や石が落ちるたびに、あたりはじしんのようにゆれる。人間の力では、どうすることもできない岩や石ばかりで、せまい畑やたんぼはますますせまくなった。いつ岩が落ちてくるかわからないので、仕事もおちおちしておられない。村の人たちは、地面にめりこんだ岩をながめては、ため息をつくばかりであった。
「これでは、外へ出てはたらくこともできん。」
「いったい、どうしたもんじゃろう。」
村の人たちは、何日も何日も相談をした。そして、とうとう天狗たちにおねがいに行くことにした。
ある日、田畑でとれたものや酒などをいっぱい持って、天狗ぐらまでおそるおそる登っていった。そして、集まった天狗たちにおみやげをわたしてから、
「天狗さん。畑でこの大豆が芽を出すまでは、どうかあばれるのはやめてくれろよ。おそろしいてかなわん。」
と、たのんだ。大豆を受け取った天狗たちも、それくらいならどうってことはないだろう、ということで、こころよくひきうけてくれた。
しかし、十日たっても二十日たっても、まいた大豆の芽が出ない。それもそのはず、わたした大豆は、いってあったのだから、いくら待っても芽が出るはずがない。天狗たちは、きょう出るか、あす出るかと、山の上で待っていたのだろうが……。
このことがあってから、天狗の悪さはなくなり、じしんがあっても小石一つころがり落ちてこなくなったそうである。村の人たちは、節分の夜、とっても注意して大豆をいる。生の大豆が、なべから飛び出て芽を出しては、たいへんだからだ。大豆をまぜるにも、かたいしゃもじでなく、やわらかいわらや小さなシュロのほうきで、そろそろとまぜるのだそうだ。
上葛川に行くと、田や畑、それに家の近くにまでたくさんの大きな岩がある。その中の、ある岩はたたみ八枚がしけるほどである。ぜんぶ、天狗が落とした岩だそうだ。
(奥吉野の山地には「天狗ぐら」というがけがたいへん多い。十津川村の笹の滝、高滝などの岩壁はふだんは白っぽく見えるが、赤くそまって見えるときは、天狗さんが来ているのだといってこわがる。)
文 松実 豊繁
(日本標準社刊「奈良の伝説」から)
(25) 葛ばば
 上葛川というところは、大きな岩がごろごろあって、夏ともなれば、そのまわりに青あおとしたクズカズラ(クズのつる)がいちめんにしげっている……そんな村である。
上葛川というところは、大きな岩がごろごろあって、夏ともなれば、そのまわりに青あおとしたクズカズラ(クズのつる)がいちめんにしげっている……そんな村である。
むかし、むかし。この村のおかには、いったいいくつなのかわからない一人のばあさんが住んでいた。ばあさんは、このあたりをまるでじぶんの庭のようにしてくらしていた。村の人たちは、葛ばばとよんで、たいへんおそれていた。
ある年のこと、山伏すがたの一人のわかものが、この村へやってきた。この村は、山伏たちが大峰山[おおみねさん]へ行くとちゅうの笠捨山[かさすてやま]のふもとにあった。そのころ笠捨山には、えたいの知れないおそろしいものがいて、だれもこの山をこえていこうとするものはいなかったそうだ。このことを知ってか知らずか、わかものはつかれも感じないように元気よく歩いていた。
とつぜん、「そこを行くお人よ。」と、よびかけたものがいた。見ると、つえをついたしらが頭のばあさんが、道ばたに立っている。
「おまえさんは、大峰に行くつもりか。」
「はい、そうです。」
「とちゅうの笠捨山はおそろしい山だ。おそろしい目にあいたくなかったら、ここから帰れよ。」
「…………。」
「もどれよ。あの山をこえたものはおらん。」
「……いいえ、もどる気はありません。こえるつもりです。」
「……そうか、どんなことがおこっても知らんぞ。」
ばあさんは、坂道を登っていくわかもののすがたをじっと見おくっていた。
山道はだんだん細くなり、道には厚く落ち葉がつもり、おまけにしめっていて、すべりやすくなっていた。道のかたがわは深い谷になっており、山がわからは草がおおいかぶさり、ときどき道がわからなくなるほどであった。聞こえていた谷川の音も、いつのまにか山にすいこまれたかのように聞こえなくなった。
それに、鳥の声も風の音もじっと息をつめたようにあたりはしんとしていた。
草をかきわけて進む音だけが、やたらにあたりへひびく。やがて、今までまったくなかったきりが、音もなくわかものの行く手を流れだし、目の前が見えないくらいになった。そのとき、わかものは、なにかにどこからか見つめられているように感じた。もうじき山をこせるのだろうか。からだがあちこちいたむのは、小えだや草で切ったからだろうか。そんなことを考えつつ足もとをさぐっていると、きゅうにからだが、くさりでしばられたようになり、動けなくなった。そのとき、聞いたこともないようなぶきみなさけび声が山やまにひびいた。そして、岩石がぶつかり、ころげ落ちる音や、大木がメキッメキッとおれる音などが近づいてきた。わかものの足は根がはえてしまったようで、一歩も動かせない。耳の底で心臓がドンドンなっているのがわかる。声はまったく出せない。なにげなく見あげたきりの中に、わかものよりもずっと上の高いところで、二つの目のようなものが光っているのが見えたとき、山がくずれるのかと思うほど大きな音がして、いなずまが走った。そして、あの目のようなものがぐっとわかものに近づいたとたん、からだじゅうから力がぬけて、気をうしなってしまった。
それからどれだけ時間がたったのか、ふと気がついたわかものはいちもくさんに、さっき登ってきた山道をかけおりた。きものをあっちこっちにひっかけて、ぼろぼろになるのも知らず、なにかに追いかけられているような気がして、必死になってにげたのであった。
さて、このわかもののようすをどこからか見ていたのであろうか。道ばたにへたばりこんでいるわかもののそばに、あのばあさんが、またあらわれ、
「おまえさんは、どうしてもあの山をこえたいのか、それとも、もう帰るつもりなのかな。」
と、たずねた。わかものはあらい息をしながら、
「はいっ、どうしてもこえたいのです。でも、どうすればあの山をこえられるのでしょうか。」
じっとわかものを見つめていたばあさんは、
「それほどの気持ちを持っているのならば、よいことを教えよう。まず、このあたりにはえているクズカズラをたくさん集めるのじゃ。それを水にさらし、たたいてすじを取り出し、けさ(お坊さんの衣の上にかけるもの)を織るのじゃ。それをかけて登れば、きっとこえることができようぞ。」
と、ゆっくりいった。
わかものは、さっそく教えられたとおりクズカズラをかり集め、谷川の水にさらした。そして、コンコンとカズラをたたいて、すじを集めた。コンコンとうつ音は、毎日毎日、葛川じゅうにこだまのようにひびいた。わかものの手にはいくつものまめやひびができた。ひびからは血がにじむようになった。
何か月かのちに、とうとう織ったこともない布を織って、ぬったこともないけさをぬいあげた。
クズカズラのけさをかけたわかものは、ふたたび笠捨山をめざして登っていった。
やはり、まえと同じようなことがおこった。きりが流れだした。しかし、こんどは歩けた。まるで、足が地面にすいついたように重いのだが、気持ちをしっかりさせて、きりをはらいのけるように手をふって、ひきずるように一歩一歩登っていった。そのときである。なまあたたかい風がふきだしてきた。と、山やまがさけてしまったかと思うほどの地ひびきがして、きゅうにわかものの行く手のきりの切れめの中に、大きな白ヘビのからだが現れた。どれほどの大きさか、けんとうもつかない。
でも、わかものはにげない。見つめていればおそろしくなるので、目をつむって一心にいのりつづけた。ちょうどクズカズラのけさでからだをつつむようにして、じっと動かずいのったのである。
どのくらい時間がたったのだろうか。ぶきみな音もいつのまにかきえて、わかものは海の底にいるようなしずけさを感じた。ああ、助かったのだなと思ったしゅんかん、バアァアーンというものすごい音が頭の上でおこって、わかもののからだは、はげしく地面にたたきつけられた。
しばらくして、わかものが気をとりなおしてあたりを見わたすと、きりも風も、そして、あのおそろしい白ヘビもきえていた。でも、まるで大あらしのあとのように木々はおれ、草ぐさはたおれていた。わかものは、このけさのおかげで助かったのだ、としっかり手ににぎって、いのるように笠捨山をこえ、大峰山をめざすことができた。
白い大蛇は、山を七まきもするほど大きかったそうだが、クズカズラのけさの力によって、頭、胴体、尻の三つに切れて、それぞれ三つの方向に飛んだといわれている。そのうちの胴体は、今の下北山村の池峯に落ちて明神池[みょうじんいけ]をつくったそうである。
このヘビがいなくなったあと、葛ばばも上葛川からいなくなった。上葛川にはふろの谷という谷があるが、これは葛ばばがおふろにつかった谷だそうである。
そして、この谷のすぐ近くに葛ばばの住んでいたおかがある。ここには、葛ばばがおふろからあがってきて夕すずみをしたという、たいらの大きな岩がのこっている。ばあさんはこの岩の上から、上葛川へ登ってくる人をながめていたのだろう。ばあさんの住んでいたあとには、秋ともなれば、ブドウのふさのようで赤むらさきのクズの花がさきほこって、おかいちめんがあまいかおりでいっぱいになる。
文 松実 豊繁
(日本標準社刊「奈良の伝説」から)
(26) 蛇の窪
昔、昔、上湯川[かみゆのかわ]の梅垣内[うめがいと]の谷奥に三本杉があった。その近くに蛇の窪[じゃのくぼ]という、今にも何かが出てきそうな古い大きな気味の悪い池があったそうな。
ある日、子供を連れた女子[おなご]が、その池の傍で子どもを遊ばせて置いて、
「今日もわらびの根掘ってわらび餅でも作って食べようか。」
と、わらびの根を一生けんめいに掘って、かごの中へ入れていた。
しばらくしていると急にあたりがうす暗くなり、ザザッというものすごい音がするので、その方へ振り向くと、おどろいたことに池の中から見たこともない大蛇が出てきて、鎌首[かまくび]を上げたかと思うと、いきなり無心に遊んでいる子供をいっきにのんでしまったのである。
女子は気が狂ったようになって子供の名を呼び続け、池の中へ持っていた鍬[くわ]をいきなり投げ込んだ。
すると大蛇は鉄がきらいだったのか、その池からおそろしい勢いで西川の小坪瀬[こつぼせ]の方へ山を崩しながら逃げて行ったそうな。
その崩した所は、今でも残っている蛇崩[じゃぐえ]という大ぐえであるという。
記録 上湯川 岡本 勝比古
再話 玉置 辰雄
(27) 牛追滝の由来
 大字小井[こい]の親谷[おやんたに]の話だが、昔は大矢の谷と書かれていたそうだ。
大字小井[こい]の親谷[おやんたに]の話だが、昔は大矢の谷と書かれていたそうだ。
この親谷に牛追滝があるが、大昔は、飛び渡りの滝ともいわれていた。その滝の少し上手[かみて]に谷巾のせまい所があり、ここを渡らなければ、小井にも池穴の方へも行けなかったそうだ。
ある時のことである。小井の若者が池穴方面から牛を追ってやって来た。
その時は、前日にかなりの雨が降っていたので、谷はこげ茶色の水となり、かなりの石が押し流され、谷間の山々にゴウゴウと水音が、こだましていた。
若者は谷を見て、渡れるかどうかしばらく考えていたが、思い切って牛を連れて渡り始めた。ところが、牛は、水の勢いに足を取られてどっと流れ出した。若者は、どうすることもできず思わず、
「恵比須姫[えびすひめ]様、助けて下さい。」
と、さけんだそうだ。恵比須姫様は、この谷の近くの神社の祭神である。
牛は見えなくなり、もうだめだと思い、その場で茫然[ぼうぜん]としていたところ、「モーン」と一声、谷水の音にも負けない鳴き声が聞こえた。若者は、はっと我にかえり急いで声のした滝の頭の所まで行って見た。どうだろう。おどろいたことに、一本の太い藤かずらが牛をひかえているのだ。若者は、その場に行くこともできずに困っていたが、不思議にも、自分がふんばって立っている足元に、藤かずらにからんだ手綱[たずな]があった。若者は急いで手綱をとり、藤づるを自分の腰にまきつけて、力いっぱい「そうれ、そうれ」とかけ声をかけて引張った。またまた不思議、牛は急に元気を出して岸へ上って来た。
「やれ、やれ、助かった、助かった。」
「男滝様、女滝様、恵比須姫様ありがとうございました。」
とお礼をいって、おがんだそうな。そうして元気をとりもどした牛を連れて帰り、この事を話すと老父母は、
「それは良かった、良かった。これも神様のおかげじゃあ。しかし、あの飛び渡りの所に、そんな藤かずらはないはずじゃ。」と言った。
そこで、お塩とお米を持ってお礼参りに行ったそうな。
その場所をよくよく見ても滝に藤かずらは無く、若者が腰をしばったかずらも見あたらず、それからというものは誰言うとはなしに牛追い滝とよぶようになったのである。
話者 小井 植田 うたの
再話 玉置 辰雄
(28) 名手の三十郎
 昔、神納川[かんのがわ]の三浦の上尾戸[うえおど](屋号)に吉村元衛門[もとえもん]一家が平和に暮らしておった。
昔、神納川[かんのがわ]の三浦の上尾戸[うえおど](屋号)に吉村元衛門[もとえもん]一家が平和に暮らしておった。
ある年のこと、その上尾戸の下屋[したや](縁の下)のいもつぼに六部[ろくぶ](諸国をめぐる僧)が、金子(お金)を奪われたうえに殺されて、ほうり込まれておったのじゃ。この降って湧いたような不幸に吉村一家はうろたえた。
「いったい、どこのどいつが、こんなむごたらしいことをしでかしたのじゃ。」
元衛門は在所の衆と大騒ぎして悪人を捜したが、まったくわからんかった。とうとう在所の衆が寄って思案したあげく、
「こうなったら、玉置山の三狐神[こじん]さまに頼んで、悪人を捜してもらおうじゃないか。」
と決まり、元衛門が、みなの衆に代わって玉置へ登ったのじゃ。
やがて、玉置に着いた元衛門は、早速わけを話して、悪人捜しに向こう三年の間、三狐神さまのお使いを借りたいと頼み込んだのじゃ。すると、どうやら願いは聞き届けられたとみえて、玉置山を下る元衛門のおいずる(背負いかご)は、ずっしりと重く背中にこたえたそうな。
元衛門が、三狐神さまのお使いを借りて在所へ戻ってみると、
「悪人捜しも、ついでに元衛門に頼もう。」
ということに決まっていた。
「それなら、やむをえまい。」
と、元衛門、早速、旅装束に身を固め、三狐神さまのお使いが乗ったおいずるを背負って、悪人捜しの旅に出たのじゃった。元衛門は、道中、三度三度の飯どきに、必ず、背中のお使いにも飯を供え、一ときもはやく悪人がみつかるようにと、祈りつづけるのじゃった。
歳月はずんずん過ぎて、旅も大和から紀州をおおかた一周りしたが、いぜん何の手がかりもない。
玉置でお頼みした三年の期限も残り少なくなったある日、元衛門は、紀ノ川沿いの名手の在所にさしかかったのじゃ。
在所に入ってみると、商売がたいへん繁昌していると見える一軒の店があった。元衛門が、そこでひと休みしようと縁側に腰を下ろした、そのときじゃった。「ドン」と、大きな音がしたかと思うと、背中のお使いが跳び上がり、店の壁にあったすげ笠を口に喰わえて、ドスンと降りてきたのじゃ。その笠には、三十郎と書いてあった。こんどは、この店の旦那の着物の裾を喰わえて放さなかった。
元衛門は、この旦那こそ、わしが捜し求めた悪人と知り、役人の前に突き出したのじゃ。とうとう、この旦那は役人の前で三浦の六部殺しを白状したのじゃ。やがて、この旦那は(三十郎)人殺しの罪で行仙岳の山頂近くで処刑されたのじゃった。
ところが、この騒ぎに三狐神さまに誓った三年の期限を、三日も過ぎてしまったのじゃ。在所の衆は、三狐神さまにお詫びし、後々のたたりをおそれて、三浦でねんごろにお祭りすることにしたのじゃった。
今でも毎月二十四日には、月参りを欠かさず続けているという。この月参りに、だんごを三つ供え、そのうちの二つを次の当番へ回すそうじゃが、それはいったいなんのまじないなのか、わしらにはわからん。
話者 那知合 後木 留若
記録 那知合 後木 隼一
再話 大野 寿男
(29) 剣客中井亀二郎
わしら、子供の頃にゃ娯楽らしいものは、何ひとつなかったわ。それじゃから、年寄りから昔ばなしを聞くのが、たったひとつの楽しみじゃった。わしらのじいさんは、ようこんな話をしてくれたものじゃった。
昔、池穴[いけあな]の中原という在所の川向こうを西熊野街道が通っていた。それは、山崎から小森・平谷へと通ずる道じゃった。その街道の途中に、「はねおき谷」という小さな谷があって、谷のそばの道下にひとかかえもあるバベ(ウバメガシ)の大木が立っていたのじゃ。そのバベは、目がくらむような崖の上に、さしでたようなかっこうで幹を伸ばし、その二十間(約四十メートル)の真下は、中原川の谷底じゃった。
ある日のことじゃ。この街道を中井亀二郎先生ら一行が通っていたのよ。今しも、そのバベのそばを一行が通り過ぎようとしたときじゃ。先頭を歩いておった先生が立ち止まって、
「おいおい、拙者[せっしゃ]、これより、このバベに登ってみせよう。」
と言い出したものじゃから、みんなは、口々に
「とんでもない。もし落ちたら命がいくつあっても足らん。」
と、あわてて止めたのじゃが、先生はさっさとそばにあった五貫(約二十キロ)ほどもある大石を片手に差し上げると、下駄ばきのまんま、
「エイ、エイ、エイ。」
気合もろともバベの大木に登り、木の叉にその石をのせると、なにごともなかったような顔をして戻ってきた、という。それは、とても人間技とは思われず、一行はどぎもを抜かれたということじゃ。
それから後、そこを通る人たちは、バベの叉にすえられた石を見ては、先生の神技におそれ入ったという。
そのバベも、長い歳月の移り変わりの中で、いつしか枯れ果て、あれから百年余りたった今は、もうそこにはない。
ご維新の後、先生は文武館に招かれ、生徒に剣術を教えたことも有名な話じゃ。
先生は、だれよりも度胸があったし、達者な腕前じゃったから、どこの藩士にも剣をとって負けたことはなかったといわれたものじゃ。
ご維新のとき、この十津川には、先生のような勇ましい郷士がおおぜいいて、京の都に参じて御所の守りについていたものじゃった。
この中井亀二郎先生は、滝川の奥の栗平で生まれた、十津川郷きっての剣客じゃったという。
話者 山崎 中畑 ケサノ
再話 大野 寿男
(30) 大植与惣左ヱ門
昔から十津川を経て高野へ通じるこの街道は、人里を離れたさびしい峠越えで、難所も多く、旅人は山賊などに悩まされることもたびたびあったという。
今から三百年余り昔のこと、慶長年間のころのことだそうだ。西中[にしなか]より坂道を登り、ひと汗かいた旅人は、みな、古矢倉[ふるやくら]の茶屋で疲れを休めるのである。そして三浦峠を越え、高野への旅を急ぐのであった。
ある時、この茶屋に山賊が立てこもり、旅人をねらって持ち物をうばい取るということがあった。旅人はもちろん、村人もこの山賊には、ほとほと困り果てていた。
そこで、各村の代表が集まっていろいろ相談した結果、この山賊を退治できるのは、与惣左ヱ門の他にはなかろうということになり、お願いすることになった。
大植与惣左ヱ門という人は、豊臣の家臣であったが、少々事情があって、十津川村の上湯川の上北[うえぎた](千葉家)の上の家に秘かに隠れ住んでいた。
人々の願いを聞いた与惣左ヱ門は、快く引き受け、さっそく山賊攻めの計画にとりかかった。綿密な計画を立てるため村の代表と話し合いをすすめていった。いよいよ計画の実行となり、手勢[てぜい]を集め、茶屋を攻め、みごとに山賊を打ちはらったということだ。
何しろ、与惣左ヱ門は、非常に知恵がある上に豪傑で、しかも、なかなかの弓の名人であったという。だから、さしもの山賊も与惣左ヱ門の知略には勝てなかったということだ。
その時、賊から奪った自在鉤[かぎ]と鑵子[かんす](つるのついた湯がま)は、上北(千葉家)に保管されているということだ。
話かわって、昔は出谷[でだに]・上湯川[かみゆのかわ]とも西川谷と一緒に玉垣内[たまがいと]の川合神社を祀っとった。ところが、川合神社のお祭りの餅投げの時になると、たびたびけんかが起こった。
慶長十年六月一日、川合神社のお祭りの時、餅投げが始まると、またまたけんかが起こった。
「これは困ったことじゃ。こうたびたびけんかが起こるようじゃ、何とかせねばならん。」
という人々の声が高まると、それぞれの村の人々の話し合いがもたれた。その結果、上湯川からは、大植与惣左ヱ門が、出谷からは千葉重左ヱ門が、それぞれ両村の代表となり、西川谷の代表と話し合い、騒ぎをしずめたということだ。
二人は、さらに西川谷の代表と話をすすめ、川合神社の神霊[しんれい](みたま)を分霊して、それをそれぞれの村に迎えて祀るということまでの了解も取り付けたそうだ。その話がまとまると、さっそく、与惣左ヱ門は杉の葉を、重左ヱ門はよもぎの葉をそれぞれもって神前に深く祈った。そうして、みたまを受けて帰り、祀り始めたのが上湯川の天神様であり、出谷の天一神社の起源だと今に伝えられている。
話者 上湯川 岡本 勝比古
再話 後木 隼一