(61) 引牛
 むかしむかし、ひとりの男し(男衆)が、一頭の牛を追うて、十津川から紀州へこえる山道を歩いていきょったと。
むかしむかし、ひとりの男し(男衆)が、一頭の牛を追うて、十津川から紀州へこえる山道を歩いていきょったと。
おてんと様が、カンカン照りつけて、とても暑い日じゃったと。
あんまり暑いすか(から)、男しは、きけてこおう(つかれてしんどく)なってきたと。
牛も、きけてきたんじゃろう。ハアハア、いいもうて(言いながら)、たらたらよだれをたらしておったと。
細い坂道を登って、あせを流しもうて、ようよう、山の峠についたと。
そこには、大きなトガの木が立っとって(立っていて)、すずしい風がふきよったと。
男しは、ぼたぼたとあせを流しもうて、
「ああ、こわかった。(しんどかった。)やれやれ、えらかった。」
と言いもうて、その大きなトガの木に、牛をつないでやったと。
牛もやれやれというように、道ばたの草をムシャムシャくうとったと。
男しは、そばの石にこしをかけて、風にふかれもうて、あせをふきふき休んでおったが、そのうちに、つい、うとうととねてしもうたと。
さあ、どれくらいねたんじゃろうか。牛が、ひょんな(へんな)声でなきたてるので、とびおきたとたん、あっとびっくりしたと。
こりゃ、どうしたことじゃ。これまで一度も見たこともない、どてらい(とっても大きい)一ぴきのクモが出てきて、その男しにも、牛にも、どんどん糸をかけてくるんじゃと。
男しが、むちゅうになってその糸をはずしたら、こんどは、牛をつなあどる(つないである)トガの木にぐるぐる糸をかけたと。
牛は、木といっしょになって、ぐるぐるぐるぐる糸をかけられて、「モー」ともなんともなけなんだと。
男しは、ただ、もうあきれてしもうて、ぼんやりとその場に立ちすくんどったと。
ほいたら(そしたら)、向こうの八重佐[やえさ]という山の下の滝のあたりで、「ドシーン」と、大きな音がしたんじゃと。
ほいたら、その音合図にして、大きなクモは、大きな地ひびきたてて、糸かけた牛も、そいて(それに)、大きなトガの木も「バリバリバリ」と根っこごし(ごと)引きおこして、
「八重佐引牛ドッコイショ」
「八重佐引牛ドッコイショ」
と、かけ声をかけもうて、みるみる八重佐の下の滝の方へ「ズシン、ズシン、ドシン、ドシン」と引っぱっていってしもうたと。
このさわぎがあってから、村では、この峠のことを、引牛といい、八重佐の滝のことを引滝というようになったと。
話者 勝山 やさ子
再話 勝山 やさ子(日本標準社刊「奈良の伝説」から)
(62) タンノクチガマの主
 松柱の弁天さんのつい(すぐ)下に、大きなガマ(ふち)があるんじゃ。うん、ガマちゅうのはな、なめた(つるつるした岩)の滝つぼのことじゃ。このガマ、じげ(むら)のしゅうはタンノクチガマちゅうとるんじゃ。そうじゃ、そこらへん、谷ノ口ちゅう地名で、そんで、そういうんじゃろ。
松柱の弁天さんのつい(すぐ)下に、大きなガマ(ふち)があるんじゃ。うん、ガマちゅうのはな、なめた(つるつるした岩)の滝つぼのことじゃ。このガマ、じげ(むら)のしゅうはタンノクチガマちゅうとるんじゃ。そうじゃ、そこらへん、谷ノ口ちゅう地名で、そんで、そういうんじゃろ。
ほんで(それで)じゃ、このガマにゃあ、ずっと昔から、ひょんげな(きみょうな)話があるんじゃ。
むかし、菊屋ちゅううちの守子[もりこ](子もり)がの、ガマの上で木をこっとった(切っていた)んじゃ。
守子は、うっかり手をすべらして、持ってたナタ落としたんじゃ。ほたら、ストン、ストン、ドボーン、あっちゅう間にナタはガマん中いしずんでしもうた。
さあ、えらいことになってしもうた。このまんまいんだら(帰ったら)、せちがあれるじゃろ。(しかられるだろう。)かちゅうて(とはいっても)、きしょくわるうて(気味わるいので)ガマへはよういかん。
守子は、うろうろ(うろたえて)しもうて思案したんじゃが、とうとう腹決めてさがすことにしたんじゃ。守子は、そろ、そろ、ガマん中いはいっていったんじゃ。ほたら、どうじゃろ、ガマのずっとおくにな、頭のまっ白けのじいさんとばあさんが、ゴロゴロ、ゴロゴロ、ひきうすで麦粉[むぎこ]ひいとるんじゃ。守子はぶるぶるしもうて、そばへいてわけをいうとな、だまっとったじいさんが、ギョロリッとこっちむいて、
「おまえのおとしたナタはこれじゃろう。二度とおとすでない。」
いうて返してくれたんじゃ。守子が、喜びかえって(よろこんで)、いのう(帰ろう)としたら、ばあさんが、
「右の道、いったらあかん、それはハコズルのふちへ行く道じゃ。左もあかん、そっちは、スイジンギ(水神さまのサカキの大木)へ行く道じゃ。おまえさんがいぬのは、まん中じゃ。」
いうて、おしけて(教えて)くれたんじゃ。
守子は、おしけてもろうたとおりにびりくそ(力いっぱい)に走ったら、やっとやっと、いについた(帰り着いた)ということじゃ。
守子は、三日ほどかかったという気じゃったのに、じげのしゅうにいわせたら、なんと三年も探して見つからんよってに、もう死んだんじゃあぜ(死んだんだろうぜ)と、あきらめかけよったんじゃと。
守子がガマん中で見たちゅう(見たという)じいさん、ばあさんはな、ほんまは主のグチナワ(ヘビ)じゃったんじゃと。
ハコズルにもスイジンギにも主がおるいうことじゃが、そこらも、タンノクチガマの主の領分でな、主はハコズルへいたり、スイジンギへ出たり、ガマへいんだりしとるんじゃろ。
なんでも、まっ白いグチナワで、五寸丸太(直径十五センチの丸太)ぐらいあって、ふたひろ(三メートルほど)の長ものじゃちゅうことじゃ。
じげのしゅうは、
「主をおこらせたら、どがあな(どんな)おとろしいことん(おそろしいことが)、おこるか知れん。」
いうて、タンノクチへは、めったなことにはいかんのじゃ。まっこと(ほんとうに)、きしょくわりいはなしじゃて。
話者 大谷 熊吉
採集者 林 宏
再話 大野 寿男(日本標準社刊「奈良の伝説」から)
(63) さんばばのはなし
 むかしむかし、どおんどむかし、上湯川[かみゆのかわ]の竹谷[たけだに]というところに、おさんというおなごがおったと。
むかしむかし、どおんどむかし、上湯川[かみゆのかわ]の竹谷[たけだに]というところに、おさんというおなごがおったと。
おさんは、毎日、山へ、ヤマイモやフドをほりに行っては、薮平[やぶだいら]というとこの日だまりで、ひるねをするくせんあったと。
おさんは、きょうも、クワをかたあで(かついで)、せどの山へフドをほりに、出かけたと。
フドというのは、ヤマイモのようにのびたつるの下に、イモがついているのじゃあよ。 フドクボちゅう(という)とこで、太いフドのつるを見つけたおさんは、
「こりゃ、いいつるを見つけたわい。ましじゃ(よいなあ)、ましじゃ。」
と、ひとりごとを言いもうて、いそいそとほり出してみたと。ほいたら(そしたら)、なんとまあ、なべのまわりほどもある、大きなフドじゃったと。
おさんは、あきれかえってみよったが、(たまげて見ておったが)
「ああ、よかった。よかった。きょうは、ひるねもしとれんわい。」
と、にこにこしもうて、「ドッコイショ、ドッコイショ」と、大きな大きなフドを持って、うちへいんだと。
ほいてから(そして)、はらいっぱい食うて、ぐうぐうねてしもうたと。
ところが、そのようさ(晩)のことじゃ。おさんがねとると、せどの山の神の大木のあたりから、だれそん(だれかが)、呼ぶ声がするんじゃ。
「今じぶん、だれじゃろう。」
と耳をすまして聞きよったら(聞いていると)、
「フドを返せ、フドを返せ。」
と、おめく(わめく)んじゃあと。
おさんは、おとろしゅうて(こわくて)、おとろしゅうて、ねや(ねどこ)の中で、よっぴて(一晩中)、ガタガタふるえよったと。
つぎのようさも、つぎのようさも、よっぴて、
「フドを返せ、フドを返せ。」
ておめくすか、おさんは、
「まてよ。こりゃ、ひょっとしたら、あの大きなフドは、山の神様のものじゃったのを、おれが知らんとほったんじゃろうか。」
「そんでも、もう、食うてしもうたものはどがあにもならん(どうにもならない)。ああ、よわった。よわった。ほんべつ(どうしょうもない)なあ。」
と、思うとるうちに、おとろしゅうて、ねれりゃあせず、とうとう、気がおかしゅうなってしもうたと。
それから、何年も何年もたって、おさんは、こしのまがったおばあさんになってしもうたと。
じげのしらは(村の人たちは)、いつやら知らんうちに、
「さんばば、さんばば。」
と呼ぶようになったと。
四月十五日は、果無山[はてなしやま]をこえた向こうの、本宮(熊野権現)さんのお祭りなんじゃ。
じげのしらは、春になると、本宮神事というて、この祭りに行くのをとても楽しみにしとったと。
そんで、おさんの家のしも、じげのしらといっしょに、朝はようから、にぎりめしゅう(おむすび)もって、果無山をこえて出かけたと。
ほいで(それで)、家に残ったのは、さんばばと、おたみちゅうおなごし(下女)と、ふたりだけじゃったと。
その日は、朝から、いい天気じゃったが、夕方からは、どえらい雨が、ざんざん降り、風もふき、大しけになり、耳をつきぬくような大がみなりが、ゴロゴロなりだしたと。
さいぜんから(さきほどから)、さんばばは、何やら、ぶつぶつ言いもうて、そわそわ、そわそわしとったが、ときどき、雨戸をあけて、外を見ては、
「まだこん、まだこん。」
と言うて、出たり入ったりしとったと。
ほいて、その日も、くれてしもうたと。
どえらいしけぶりの中で、ピカリといなづまが光って、パリパリと大がみなりが、はじけたと思うたら、まっ黒い雲が出て、そこらは、まっくらやみになってしもうたと。
そのときじゃ、さんばばは、いきなり、
「そらきた、そらきた、きた、きたー。そらきた。きた、きたー。」
とおめえて(さけんで)、さらあ(新しい)ぞうりをひっかけて、暗やみの中へとびだしてしもうたと。
おたみがびっくりしてあとを追うてみたけんど、雨はザーザー降るばっかし。
まっくらやみで、さんばばはどこへ行ったのやら、かげも形もなかったと。
やがて、本宮神事へ行っとったしらも帰ってきて、おたみにおさんの話を聞いて、じげじゅう大さわぎになったと。
「いかに(たいへん)、きょうといことのーら(こまったことになった)。」
「なしたこっちゃろうのうーら(どうしたことだろう)。」
「天ぐにつれて行かれたんじゃろうかい。」
と、さわあで(さわいで)おるとこへ、津越[つごえ]の定治[さだじ]ちゅうしん(人が)、帰ってきて、
「おれん、『いだんだわ(果無山の地名)』まできたときの、どえらいしけぶりんしてきてのら、そこらん、くらがしゅう(暗く)なったとおもうたら(思ったら)、みしろ(むしろ)一枚ほどもあるまっ黒いもんが、ヒューヒュー、おれの頭の上を通ったんじゃ。ひょっとしたら、さんばばは、あれにのっとったんじゃなかろうかのー。」
ちゅうて、村じゅうそうででさがすことになったと。
みんな、かねやたいこをたたき、夜は、たいまつをふりかざし、
さんばば返せ、ドンドンドン
さんばば返せ、ドンドンドン
さんばば返せ、ドンドンドン
谷をわたり、山をこえて、夜も昼もさがしまわったと。
二日たっても三日たっても、さんばばは見つからなんだと。
そんでも(それでも)、村のしゅうらは、
さんばば返せ、ドンドンドン
さんばば返せ、ドンドンドン
と、さがしまわったけんど、山びこん(が)返事するだけじゃったと。
七日七晩、さがしまわったけんど、さんばばはとうとう見つからなんだと。
「かわいそうに、さんばばは、ほんまに天ぐにつれていかれたんじゃろうか。」
「さんばばは、むかしから薮平で、ようひるねをしよったが、あのじぶんからなんぞん、ついとったんじゃなぁかしらん(ないかしら)、ふしぎなこともあるむん(もの)じゃ。」
と言うて、じげのしらは、空を見上げてため息をついたと。
それから十日ほどたって、源治ちゅうしん(人)、果無山の大平[おおだいら]という山へ行ったら、大きなトガの木の根もとに、さらあぞうりがおちとるんじゃあと。ふしぎにおもうて、そのトガの木を見上げると、木のえだに着物のきれがかかっとったと。
「あっ、ありゃあ、さんばばの着物のきれかもしれん。」
そうおもうて、するすると、その木によじのぼってみたと。
ようみると、源治がおもうたとおり、たしかにそれは、さんばばがいっつも着とった、しまの着物のきれじゃったと。
「さんばばよー。さんばばよー。」
と、木の上から、大声をはりあげておめえてみたけど、おさんの声もせんし、すがたも見えなんだ。
源治は、そのぞうりと着物のきれとをもっていんで(帰って)、みんなでさんばばの墓を作ってまつってやったと。
それから何十年もたっての。若かったおたみも、どおんど(ずいぶん)、年をとったと。
おたみが、のおなる(なくなる)ちいと前、家のしらをまくらもとによおで(よんで)、
「いかい(たいへん)世話になったけんど、おれも、もうなごうはなあ(ない)。そんじゃすか(それだから)、言い残しておきたいことん(が)あるんじゃ。今まで言うたことのなあ(ない)話じゃすか(から)、よう聞いてくれえ。ほかでもなあ、あのさんばばのことじゃ。おれん若あ(若い)とき、さんばばの家におったんじゃ。さんばばが出ていくきわに、『おれは、人目には人間に見えるじゃろうが、どうから下はヘビなんじゃ。今夜は、連れにきてくれるすか出ていくが、行くさきゃ(先は)、横枕[よこまくら]の滝(上湯川にある滝)か沖の河の牛鬼滝[うしおにたき](上湯川にある滝)かの、ぬしになるかもわからん。このこたあ(ことは)、こんりんざい(絶対)だれにも言うてはならんぞ。もし、人に言うたら、三日のうちに、おまえもつれにくるぞ。』と、きつう言われとったんじゃ。まっこと(ほんとうに)、おとろしい(おそろしい)ことじゃったよ。」と言うて、ブルブルッとみぶるいうして(をして)、間ものう(なく)息[いきゅ]う引きとったと。
話者 勝山 やさ子
再話 勝山 やさ子(日本標準社刊「奈良の昔話」から)
(64) おにといりマメ
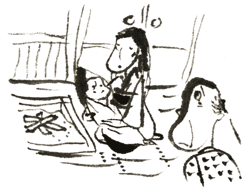 ずっとずっとむかしのことじゃがな。
ずっとずっとむかしのことじゃがな。
ある年の夏、いかい(ひどい)日照りつづきでな、村の田んぼという田んぼ、みーんなカラカラになってしもうたんじゃ。
ひとりの百しょうが、ひびのはいった田んぼ見ちゃあ、ためいきばっかりついていたんじゃ。
ほて(そして)、つい、
「だれそ、水くれんかの。ほたら(そしたら)、むすめくれてやるんじゃが…。」
と、ひとりごというたんじゃ。
ほたら、どっからか、若い男がやってきて、
「おまえさんのたのみ、聞こう。そのかわり、きっとむすめをくれるな。」
と、いうたかと思うたら、あっという間に、田んぼいっぱいに水がたまったんじゃ。
きもっ玉ぬかれて(きもをつぶすほどびっくりして)おった百しょうが、やっと、われにかえったときにゃあ、もう、若者は、どっかへいてしもうて、そこらにゃあおらなんだと。
「こりゃあ、えらいこというてしもうた。ほんまにむすめくれえいうてきたら、どがあにしよう。よわったことになった。」
百しょうが、しょぼ、しょぼ、うちへ帰ってくると、それを見たむすめが、
「おとう、どうなさった。えらく顔色わりいようじゃが…。」
「ほんまに、どこぞ、こころわりいか(気分がすぐれないのか)。」
と、やかましいよってに、百しょうはかくせんようになって、田んぼであったことを話したんじゃ。
むすめは、
「そんなら、わたしはおよめにいきます。じゃが、どうかトシゴイ(節分)まで待ってもろうてくだされ。」
といい、それから百しょうはないておったんじゃ。
そうこうしているうちに晩がきて、昼間の男がむすめをつれにくると、百しょうは、
「昼間の約そくはちゃんと守ります。けんど、どうかトシゴイまで待ってくだされ。」
と、手を合わして、いっしょうけんめいにたのんだんじゃ。
すると、男は、だまって、さっさともどっていってしもうたんじゃ。
やがて、約そくのトシゴイの晩がやってきて、百しょうがマメをいってエベッサマにそなえておるうちに、むこがきてむすめをつれていてしもうたんじゃ。
むすめは、うちを出るきわに、
「おとう、わたしは一町(一〇九メートル)ごとにマメを植えていきます。マメに花がさいたら、それをたよりにさがしにきてくだされ。」
と言いのこして、マメをもって行ったんじゃ。
むすめはとついで間なしに、みごもって、かわいげな(かわいい)ほうし(男の子)を産んだんじゃ。
三年たって、百しょうの家の庭にマメの花がさいたので、百しょうはむすめをさがしに出かけたんじゃ。一町めごと、花をたどっていくと、今までいた(行った)こともないおく山にはいり、とうとう、大きな岩屋にいきついたんじゃ。
そこに、むすめとはじめて見るまごがおったんじゃ。むすめは、
「おとう、わたしの夫は、ほんまはおになんです。おとうがきたと知ったら、きっと、むり難題をいうでしょう。じゃが、おとう、どうぞきばって(がまんして)おくれ。」
晩になって、おには大きなシカをかついでもどってくると、
「じじい、あしたは、アワ一斗まく畑(一八リットルまく広さ、二五〇アール)をきれ(開け)。」
と、いいつけたんじゃ。
あくる日、じいさんは、山をひらいて畑をこしらえにかかったが、なかなかうまいぐあいにしごとがはかどらず、よわって(こまって)おると、そこへまごがやってきて、
「じいちゃま、おらもやる。」
いうて、ふたりで、せえだあ(いっしょうけんめいに)したので、やっとのことできりおえたんじゃ。
おには、こんどは、その畑にアワをまけといいつけたんじゃが、また、まごが手つどうて、まきおえたんじゃ。
おには、おもしろがって、つぎは、
「きんのう(きのう)まいたアワを一つぼ(一つぶ)のこさんとひらえ。」といいつけたんじゃ。
じいさんは、あんまりきつい仕事にきばりかねて、
「もう、かなわん。はよう ここをにげだそう。」
と、むすめと相談して、まごをつれて岩屋をこっそりぬけだしたんじゃ。
ところが、それを知ったおには、ドシン、ドシンと追いかけてくるんじゃ。そのときじゃ。まごがかくしもっておったトシゴイのいりマメを、おにめがけて、てっつけた(投げつけた)んじゃ。マメがバラバラとおににあたると、ポキッと角が折れてしもうたんじゃ。ほしたら、今までの元気もどこへやら、「助けてえ。」と頭をかかえておには、にげてしもうたんじゃ。
まごは、にっこりとして、
「わしは、ほんまはエベッサマじゃ。おまえさんら親子がふびんにおもえて、助けてやろうと、子どもに生まれ変わってきたのじゃ。もう案ずることはない。これからはあんきに(気楽に)くらせよ。」
といいのこして、ぱっと消えたということじゃ。
ほんでおには、いりマメがおとろしいんじゃと。それから、節分にはマメまきをすることになったんやということじゃ。
話者 上垣 なお
採集者 林 宏
再話 大野 寿男(日本標準社刊「奈良の昔話」から)
(65) ミミズの丸薬
昔、あるところに、貧乏なやぶ医者がおったんや。
あるとき、その医者のそばに住んでた貧乏な母さんが病気になってな。子供が、その医者へ薬をもらいに行きよったんや。せやけどなあ、その医者も、どだい(さっぱり)はやらん医者じゃもんで、薬はたんと(多く)なかったんやと。医者が子供に、母さんの様子を聞いたら、どうやら熱病らしい。
「さあ、こらあえらい(たいへんな)ことになった。薬はないし、どうしよう。」と考えこんでしもうた。
そんなこと知らん子供は、なんぼたのんでも、薬を出してこないのは、「こりゃ薬の値段が高うて、わしが貧乏で金が払えんからやろう。」と考えよった。
それで、「こりゃあかん。金を用意せにゃ。」と、親類の家々を回って、金を用意しようと考えよったんや。どないしても母さんを助けたいと子供は走り回りよった。
医者は、「あの子が金を用意してきたら、どうしよう。」と心配やったが、どうしようもないし、なんとかうまい考えは、ないものやろかと、外へ出ていかはってなあ。
気が重いまま、畑仕事をしょったら、メメズ(ミミズ)がチョロチョロ出てきよった。
「うんうん、これでも、薬にならんことは、ないじゃろ。」
と言うて、炊[た]いてあった飯にすりこんで、丸薬みたいなものを作りょったんやと。
そうこうしているうちに、子供が金をこしらえて走ってきたんで、医者は、作った丸薬を子供に持たせて帰さった。(帰らせた。)そうしたものの、もし、あの薬が効かなんだら、どうしたものかと心配やった。
それから何日かたって、子供がまたやってきたんで、医者は、さあたいへん、どない(どのように)言いわけしようかと、オドオドしてると、
「先生、おかげで、お母[かあ]の熱が下がって、命が助かりました。」
と子供が礼を言うので、あの薬を飲んでからの様子を聞いてみやはったら、
「しっぽり(たくさん)汗をかいて、熱が下がりましたんや。」
と言うたので、さてはミミズの丸薬で人助けができたのかと、貧乏医者は、
「こりゃ、おれも、じっとしておれんわい。」
そう言うて、あっちこっちとたずね、勉強しよったんで、とうとうりっぱな医者になったと。
こんなわけで、ミミズは熱冷ましによう効く妙薬になってんと。
再話 後木 隼一(研秀出版刊「日本の民話」から)
(66) けちんぼと山女
 昔、一人の樵[きこり]がおった。この男、村一番のけちんぼうで、名を知らないものはなかった。男は、かねがね、働き者で飯をあんまり食べない嫁はいないものか、と探していたという。
昔、一人の樵[きこり]がおった。この男、村一番のけちんぼうで、名を知らないものはなかった。男は、かねがね、働き者で飯をあんまり食べない嫁はいないものか、と探していたという。
ある日のこと、男が山から帰ってみると、家の中から何やらプーンといいにおいがした。「あれっ、おかしなこともあるもんだ。」といぶかり、戸を開けて中をのぞくと、見たこともない女が、台所でかいがいしく働いていたと。ポカーンとして女の後姿をながめていたら、ひょいとふりむいて女がニカリと笑った。そして、「お前さん、よう働いて飯をあんまり食わん嫁さんを探していたらしいから、今日からわしが来たんよ。」と言う。
こういうことで、この女と夫婦[めおと]となったのであるが、まことに良く働く女で、飯もほとんど食わんかった。男はほくほくしていた。
ところが、男は妙なことに気がついた。女が来てから数日しかたっていないのに畑の野菜が急になくなった。池に飼っていたコイも少なくなっている。
「お前、知らんか。」と聞いても
「わしは知らん。サルがもっていったんだろう。トンビがさらっていったんだろ。」
というばかり。
そこで男は、山へ行くふりをして、そっと台所をのぞいてみた。
そこで男がみたものは……。
なんとなんと、女は大なべ一杯に、大根とコイをみそだきにして、もう一つのかまどには、いつ、からうすでついたのか、大がま一杯に飯を炊いている。さて、どうするのか見ていると、女は耳まで裂けた大口を開けて、湯気のいっぱいたっている飯やら大根をどんどん口へほうり込んでいる。何しろ男は「けち」の上に「ど」がついたような男だから、いきなり台所へとびこんだ。
「お前、よくもおれをだましたな。こんな大食らいだとは知らなんだ。むだ飯食いに用はない。とっとと出て行け。」と、どなりつけたんだと。
なんと女はまだ口をもぐもぐさせて、それでも、ニカリと笑って、
「ええとも、出ていってやるよ。だがひとつだけ頼みがある、聞いてくれるか。」
「あつかましい奴だ。ただ飯を食うて、まだ頼みごとがあるというのか。だがな、食いもんは一切れも一粒もやらんぞ。」と、おめいた。
「あいかわらず、どけちな男じゃ…。頼みというのはな、わしが背負う大おけを作ってほしいんじゃ。ちゃんとしょいなわもつけてな。」
女は、ニカニカ笑いながらそういった。
男は、おけくらいお安い御用だ、大飯をくらわれるよりましだ、と思って、早速、おけづくりにかかった。
材料があったので大おけはじきにできあがった。
「さあ、これをせったら負うて早よ、どこそへ行ってくれ。」
と、できたおけを女の前につき出すと、女は、やにわに男のえりくびをつかんだ。
「なにをしくさる。」と、手をふりはだこうとしたが、もうその時は遅かった。女は、見上げるような大女になって、男をひょいとおけの中につかみ入れると、
「みやげがいるんでな。」と、いった。女は、かけるような速さで山の中へわけ入った。なにしろ大股で歩くもんだから、その速いこと速いこと、あっという間に自分の村が見えなくなった。これはえらいことになった。こいつがうわさに聞く山女に違いない。男は揺れるおけの中で生きた心地もしない。
そのうち雷が鳴りだした。雨も降ってきた。大粒の雨である。山女はおれをどうしようとするのだろう。食おうとするのだろうか、そう思うと、ますます心細くなってきた。
やがて、おけの中に雨水がたまり始めた。すわっている男のへそのあたりまでたまってきた。水の冷たさと恐ろしさに歯がガチガチなった。山女は歩く速さを一向にかえようとしない。水が大部たまって重いはずだが、えらい馬力である。
一体どこらへんだろうか。おけの中でのびあがってあたりを見ると、一度しか来たことのない遠い山であった。そのうち山女はバシャバシャと谷川を歩きだした。ふいに山女は、
「おい、どけちよ、わしの家はもうすぐだ、わしの子どもが腹をすかせて待っているだろうよ……」
そして、「ケケケケ」と笑った。男はぞーっとした。
「やっぱり、こいつらに食べられるんだ。なんとかしなければならん。かといって、このおけの中、どうしようもないなあ。」
男は、おけの中で空中をにらんでおった。いい考えもなく雨にうたれている男の目に、ぱっと見えたものがあった。あれはなんだろう、のびあがってよく見ると、それは、谷をまたいでのびている藤カズラであった。ワラをもつかむ思いであった。
そのつぎにもあるかも知れない、谷わたり藤を目を皿のようにして探した。女に、そんな気持ちをさとられないように必死で前方を見つめていた。あった。一かばち(八)か。山女が藤カズラに近づいたとき、よし助かる方法は、これしかない。のびあがって、しっかり藤カズラをつかんだ。そして魚のように、するりとおけの中から脱けだした。
山女は、男が抜け出たのも知らずにズンズン先へ行ってしまった。
やれやれ。谷わたり藤にこうもりのようにぶらさがっていた男は一刻も早く逃げなければと考えた。地上に降りるが速いか、駆け出した。といっても、道のないやぶをかきわけて進むのだから、たやすいことではない。それに雨はいぜんとして降りやまない。
男は時々立ち止まった。そして、じっと耳を澄ませた。ザーッという雨の音だけだと安心して進んだ。しばらくして立ち止まる。今度は、確かに人の声がする。男を探している山女たちの声である。あわてて、あたりを見回すと藤カズラの下がった山ももの大木があった。とっさにそれにしがみつくように登った。下が見えないくらい葉の茂った場所までたどりついたとたん、下にどやどやと人が集まった様子である。
「まったく、あのどけちも命はおしいらしく、逃げ足の速い奴じゃ、ちくしょう。」その声は確かに山女である。
「おっかあ、うまそうな男だと言っとったのに……。」
「エイックソッ。この雨で人のにおいまで消されてしまったわい。よし、心配するな。あの男は今夜ごちそうしてやるぞ。わしがあの男の家を知っとるからな……。」
「おっかあ、もうその姿では男の家へは行けまい。」
別の子どもの声である。
「なあに、簡単なことだ。あの家の煙り出しからクモになって自在[じざい]をつたって降りていけばいい……。たやすいことじゃ……。」
「おっかあ、ほんじゃ暗くなってから出かけようか。」
山女の子どもは三、四人らしい。がっかりしたような足どりがしだいに遠のいて行った。男は、ほっとした。しかし これからが大変だ。あいつらは今夜やってくる。しかも、クモになってやってくるという。男は一計[いっけい]を案じた。
夕飯を早目に食べて、ねむい目をこすりこすり、クモはまだか、クモはまだか、と待っていた。大きなほたをくべてトロトロと火はいろりに燃えている。
真夜中ごろ、男は自在をつたって、降りてくる四匹のクモを見つけた。とうとう来たな。男は手で払いのけようとした。先頭の大きいクモが山女に違いない。そのクモをよく見ると、男はびっくりした。死んだ母親の顔そっくりなのである。男はひどく迷ってしまった。もしかしたら母親の魂[たましい]がクモになって現われたのかもしれん。山女ではないかもしれん。男はそう思った。そうとなれば火の中へ落とすわけにもいかん。クモはどんどん降りてきた。そのとき男は、クモがちょっとニカッと笑ったような気がした。
「くそっ、やっぱり。」
そう叫ぶと、つかむが早いか、火の中へ投げこんだ。後に続いているクモも火の中へ投げこんだ。クモは火の中で、声もなく消えていった。
このことがあってからである。十津川村では「谷わたりの藤」を切ってはならないといわれだしたのは。また、夜、出て来るクモは「親に似ていても殺せ。」、と言われるようになった。
ところで、この男がそれから後、けちんぼうでなくなったかどうか、とんとわからん。
再話 松実 豊繁(「十津川」から)
(67) キツネにだまされた五助
昔、村に五助という百姓がいたそうな。
ある日のこと、五助は隣村の親類へ遊びに行った。その帰りにナンバ(トウモロコシ)をたくさんもらったので、近道しようと山を越えることにしたそうな。汗をかきかき、きつい坂道を登っていくと、ちょうどいい具合にお地蔵様があったのじゃ。五助は、肩に食い込んだ荷物を下ろして一服することにしたのじゃ。木陰に寄って汗をふいているうちに、いい気持ちになって、ついうとうとと居眠りをしてしまったそうな。
どれくらいたったのか。やがて五助が目を覚ますと、これはしまった、とっくに日は落ちて、あたりはもう暮れようとしているではないか。驚いた五助は、急いでナンバを背負って歩き出した。どんどん山を下って、やれやれやっとうちの近くへ来たと、ほっとしてあたりを見ると、なんと、まだ、お地蔵様のまわりをうろうろしているのである。
「これはいったいどうしたことじゃ。」
びっくりした五助が、あわてて背負い袋を下ろしてみると、ナンバはすっかり消えて中はからっぽであった。
「この山には、古キツネがいて悪さをすると聞いていたが、さてはおれもまんまとやられたわい。」
五助は、舌打ちしながら気を取り直して家路を急ぐことにした。しばらくして五助は草むらの中で眠っているキツネを見つけた。五助は、
「しめしめ、このキツネめ、どうするかみておれ。」
やにわに石を拾って投げつけたのさ。
五助の投げた石が、うまい具合にキツネのお尻にドスンとばかりに命中したからたまらない。キツネは、ギャンギャン悲鳴をあげて奥山へすっとんで逃げたそうな。
「やれやれ、これで仇[かたき]討ちができたわい。」
「それにしても道草を食いすぎたなあ。」
ひとりごとを言いつつ、走るように帰り道を急いだのじゃが、とうとう長い夏の日もとっぷりと暮れて、暗い山道をとぼとぼと歩いて行く始末となった。と、行く手に、ちらちら灯[あかり]が見える。喜んだ五助は走り寄って、
「ごめん、道に迷って困っている者じゃが、一晩泊めてくださらんか。」
戸をたたくと中からきれいな娘さんが現われて、
「泊めてあげたいのですが、あいにく今晩は取り込んでいますので……。」
五助が家の中をチラッとのぞくと、座敷にまっさらな棺桶[かんおけ]が二つ並べてあった。
「実は、長い患いの果て、とうとうおじいとおばばは枕を並べて亡くなったのです。あとに残ったのは、このわたし一人、こうして夜とぎをしているのでございます。」
寂しそうに頭を下げる娘を見た五助は、
「それはそれはお気の毒に。そんなら、わしを泊めてくださらんか。ともども夜とぎをして進ぜよう。」
と言って、泊めてもらうことにした。娘は、大変喜んで夕ごはんの支度をした。二人で、夜のふけるのも忘れてよもやま話をしているうちに、五助は昼間の疲れが出て、いつの間にかコックリコックリ居眠りを始めたそうな。
娘が、
「お客さま、お疲れでしょ、どうぞこれへお休みくだされ。」
と、棺桶のそばに寝床をとってくれたのじゃ。五助は、言われるままに横になったものの、そばの棺桶がさすがに気がかりでなかなか寝つかれない。
五助が、見るともなしにそばの棺桶にそっと目をやると、その棺桶がゴソッゴソッと、少しずつ動く気配がするのじゃ。ますます奇妙に思った五助が、なおもじっと目をこらして見ると、棺桶は、確かに自分の方へ少しずつ寄ってくるようじゃ。五助は、ブルブルふるえながら出口の方へ後ずさり、棺桶に追われて、とうとう縁側までにじり寄ったかと思ったとたん、庭先へころげ落ちてしもうたのさ。その庭先と思うたは、実は川の中、ジャブンと大きな水音。五助は、やっと目が覚めたのじゃった。
あたりはかんかん夏の日が照りつける昼下がり。五助は、山を下った谷川の滝つぼの岩の上にずぶぬれになって立っていたということじゃ。
話り 滝川 下村 タカノ
再話 大野 寿男
(68) ひとつ目小僧
 むかし、むかしのある村の話じゃ。その村には、大きな寺があったんじゃ。その寺は荒れ寺でなあ、くもの巣がいっぱいはって、雑草がはびこり、屋根は今にも崩れ落ちそうじゃった。
むかし、むかしのある村の話じゃ。その村には、大きな寺があったんじゃ。その寺は荒れ寺でなあ、くもの巣がいっぱいはって、雑草がはびこり、屋根は今にも崩れ落ちそうじゃった。
この寺にも旅の者が泊まることが時々あった。ところが、まだ夜も明けないうちに、どの旅の者も「ギャーツ」と叫んで寺からとび出して逃げてしまうんじゃ。こういうことが何度もあったので、村の衆は誰も近づこうとせなんだ。
ある夕方のことじゃった。顔中、ひげもじゃの男が一人、村に入って来てな、
「どこか泊めてくれるところはないか。」と、えらそうに尋ねたそうな。村の衆は、
「あの寺なら泊まれるぜ……けんどやめといた方がいい。化けもんが出るらしいんじゃ。」と言ったんじゃ。
こんなに言われると向きになったのか、それともよっぽど気が強いのか、その荒れ寺へ行ってしまっての。
「大丈夫かのう。」と、村の衆は心配気に見送ったんじゃ。この男も真夜中ごろ、「ギャーギャー」騒いで村をとび出て行ってしまったそうだ。
この出来事も忘れられかけたある日のことだ。一人の、いかにも強そうな侍が村に入って来た。
「化けものが出るという寺は、どこじゃ。」
村の衆は、気の毒そうな顔付[かおつき]で、
「あそこじゃが……。」と教えたんじゃ。
「おお、あそこか。」侍は、のっしのっし歩いて行った。
「行かん方がいいぞ。」
と、村の衆はとめたが、そんなことは聞き流して、行ってしもうたんじゃあと。
なるほど、お化けの出そうな荒れ寺である。侍は、寺に着くやいなや、
「たのもう、たのもう。」と、
大声をはりあげたんじゃ。すると、ギシギシ床を鳴らして一人の小僧が出てきたそうだ。
「なんでしょうか。」という。見ると、小僧の顔のまんなかに小さな目がひとつついている。こんなに早く化け物に会えるとは………侍は、内心びっくりしたが、そこは侍じゃ、
「一晩やっかいになるぞ。」と言った。小僧の顔はぱっと明るくなり、「どうぞ、どうぞ。」と、中へ入れてくれたんじゃ。侍は、長旅で疲れていたのか、破れ畳にゴロンと横になるとすぐ、クークーと寝てしまった。どのくらい眠っただろうか。
「お侍さま、お侍さま」と、肩を揺する者があるんじゃ。侍は、めんどくさそうにうす目をあけて、声の相手を見たんじゃ。そこにはな、杯[さかずき]ぐらいの目をした小僧が、侍を見下ろしていたんじゃと。侍は、たいして驚きもせんと、
「何か用か。」と聞いた。侍が、全然驚きもしない様子に、小僧はちょっとがっかりしたようだった。
「ごはんにしましょうか、お風呂にしましょうか。」
と、おそるおそる尋ねた。侍は、
「飯を先にするぞ。」と、命じた。小僧は、ひょこんと頭を下げて部屋を出ていった。
しばらくして、
「ごはんをもって参りました。」と言って、
女が入って来た。女が、ひょいと上げた顔を何気なく見ると、女の目は湯呑みくらいあったんじゃ。侍は、心中、びっくりしたし、うすきみ悪くなった。それでも平気をよそおって飯をガツガツかきこんだんじゃ。みそ汁をズルズル飲みこんだんじゃ。侍が、いっこうに驚かないので、女も少々がっかりしたらしく、しおしおと部屋を出ていった。
ご飯を食べ終ったところへ、さっきの小僧が入って来たんじゃ。
「お風呂に入りませんか。」やはり、ひとつ目だったがその目は、お茶碗くらいの大きさになっていたんじゃと。侍は、両わきから脂あせがにじみ出るのを感じた。それでも小僧に案内されて風呂に入ったんじゃ。
でも、刀を自分のそばからはなさなかったそうじゃ。
風呂から出て、部屋で火鉢にあたっているとな、
「お布団を敷きましょう。」と、女が入ってきたんじゃ。
ひょいとふり返って女の顔を見た侍は、息も止まるほどびっくりしたんじゃ。そして、声にならん声を出して寺をとび出して行ってしもうたんじゃあーと。
その女も、やはりひとつ目じゃったが、その目はどんぶりぐらいの大きさだったそうじゃ。
話者 旭 中西 貞治
記録 上野地小学校
松実 豊繁
(69) 桂又妙権太夫の話
 伝え聞くところによると、昔、迫西川では松木平と則本の二つの姓だけじゃったらしい。
伝え聞くところによると、昔、迫西川では松木平と則本の二つの姓だけじゃったらしい。
則本の始まりは、則本桂又妙権太夫という武士で、たしか平家の落ち人の子孫じゃったちゅうことじゃあ。
ところで、桂又妙権太夫という人は、小次郎ちゅう家来を一人つれておったそうじゃ。この小次郎という家来は、非常に腕がたつし忍術も使ったらしいが、たちが悪るうてのう、桂又の家を追いだされてしもうたんじゃ。
ほんで、小次郎はいざさの谷の奥へ入って、大きな岩屋を築いて、そこに住いをしとったんじゃあと。
この男は、忍術をつこうていろんなものに化けて、魚とりに来た人や山仕事に来た人を殺したり、悪さばっかりしよったらしい。迫西川には、師匠の桂又妙権太夫がおるよって、悪さをしに、よう来んのじゃが、小又川の方へ行って悪さばっかりしよったんじゃあ。そんで、小又川の庄屋がかなわんようになって、迫西川の庄屋のところへ来て、「小次郎を征伐してくれるように、妙権太夫殿に頼んでくれんか。小又川の人間は、残酷な目におうてかなわん。」と言うわけじゃあ。さあ、それを聞いた迫西川の庄屋らも
「それは気の毒じゃよって、ほっておけん。」
と、桂又にこの話をした。
「三年ほど前から体がわるうて、よう起きんのじゃが、あいつは、おれの家来じゃったが、たちの悪いやつじゃよって、ひまをやったんじゃ。そがあな、悪いことをするんじゃったら、何とかせんならんのう、何とか方法がないものか、気の毒じゃあのうら。」
と言うて起きてきたんじゃあ。
その時分は、ねるときの枕は木枕じゃったが、桂又は、自分が宝として持っておったサイバコ剣、一名ツルベ太刀ともいう刀をひき抜いて、木枕を宙にほうりあげ、その落ちてくるやつをパッパッと三つに切り、「ようし、これじゃったら、おおかたいけるじゃろう。」ちゅうて皆に案内させて、ぼつぼつ歩いて小次郎の岩屋へ出かけたんじゃあ。
行ってみると、まあ大きな岩屋じゃったらしい。そして、小次郎は、アメノウオに化けて川でおよぎょうる。ハハン、小次郎のやつ、忍術を使うておるわいと師匠は見ぬいて、
「小次郎、小次郎、おれは桂又妙権太夫じゃあ、用事があってきたんじゃあ、ちょっと上がってこんか。」ちゅうたら、小次郎は「ハイ、ハイ、師匠、ようきてくれました。」ちゅうて、岩の上からつりさげた鎖にすがって、あがってきたんじゃ。
「お師匠さん、久々の対面じゃが、なにか用事がありますか。」と小次郎。師匠は、
「いや小次郎、今日おまえに会いに来たのは、ほかでもない。おれもこの頃、体がわるうて、そう長く生きておれそうにもない。いつ往生するかもしれん。生きているうちにと思って、わしの宝のツルベ太刀を、お前にゆずっておきたいと思うて持ってきたんじゃあ。」と言うと、小次郎が、「それは、ありがとうございます。」と言って頭をさげたところへ、そのツルベ太刀をさっと打ちおろして、みごとに小次郎の首を切ってしもうたんじゃ。
うまく計画どおりに小次郎を退治したので、皆よろこんで村へひきあげてきたんじゃあが、その後、妙権太夫は、どうなったのかわからんちゅうこっちゃ。
その時のツルベ太刀は、ずっと迫西川の氏神様の宝として伝えられてきたんじゃあが、水害で今のところへ氏神様を移したころから、わからんようになってしもうた。残念なことじゃあと、今でも思うとる。
話者 迫西川 松木平 数馬
再話 東 勇
(70) 百夜月
竹筒の少し南の北山川の対岸に、百夜月(三重県紀和町)というむらがある。そこに、光月山紅梅寺[こうげつさんこうばいじ]という古い寺があった。寺の庭には紅梅があり、春にはたいへん美しい花を咲かせ、よい香をあたりに漂わせていた。
寺には、一人の美しい尼さんが住んでいた。毎日、仏の教えを広めるために行をしたり、読書するなどして静かに暮らしていた。また、寺の周りを開いて、野菜も作っていた。
この尼さんは、近くのむらの若者たちのあこがれの的であった。しかし、真剣に仏の教えを広めたり、読書にうち込んでいる尼さんは、若者たちのことなど考えてみたこともなかった。
さて、対岸のむらに一人の若者がいた。かれは寺の畑でたち働く尼さんの姿を見てから、心の中は尼さんのことでいっぱいになってしまった。ぜひ会って話がしたいものだと思った。そして、月のない闇夜になる日を待った。
「よし、今夜こそ川を渡り、尼さんに会って来よう。」と決心した。やがて、夜になった。川の音さえもシーンとして流れているようであった。川底をつき刺す棹[さお]の音だけが闇の中に響いた。川の中ほどまで来たときである。対岸の山から突然、大きな月がヌッと顔を出して、あたりが急に明るくなってしまった。
「これは困った。こんなに明るくなっては、誰かに見つかってしまう。人に知れたら、尼さんにたいへん悪いことをしたことになる。」
と考え直した若者は、急いで舟をひき返し、とぼとぼと家に帰った。
次の夜も、その次の夜も、また次の夜も若者は北山川を渡ろうとした。しかし、川の中ほどまできたとき、月の光がまぶしくて、どうしても渡ることができなかった。
「今夜で何度めだろうか。」
若者は、一、二、三と指をくってみた。すると、すでに九十九日めであった。
若者は、このことを母親に打ち明けてみた。
母は、
「ああ、なんともったいないことを…。よりによって尼さんを好きになるとは……。あの方は、仏の教えをお守りし、広めている方だから、お前なんか、とてもとても……。そんな気持ちを持つことも恥ずかしいことだよ。」
「あのお月様は、悪いことを人間がしないように、いつも地上を照らしているのだよ。だから、お前が百夜通っても、川を渡ることは、できないのだよ。」と、諭[さと]した。
若者は、とても悲しんだ。
「お月様もあの尼さんを、お守りしているのか。」
それから、尼さんの住んでいるむらを百夜月と呼ぶようになった。
ところで、尼さんは、もっと仏の教えを広めたいと考えた。
そこで、寺に伝わる宝物を近くのむらむらへ分けて祀[まつ]ってもらうことにした。そうすれば、信仰も広まると考えてのことだった。
まず、花びんを川下の村に分けた。むら人たちは、紅梅寺の宝物をいただいた、というわけで、お堂を建ててお祀りした。そして、このむらを花井[けい]とよぶようになった。
川を渡ったむらには、九重[ここのえ]の重箱を分けた。このむらは、これにちなんで九重[くじゅう]という名をつけた。
上流のむらには、美しく磨かれた竹の筒が分けられた。ここは竹筒[たけとう]とよばれるようになった。
そのころ、都では戦が始まり、世の中が騒しくなってきた。
そして、この熊野の地方へも、ひそかに都から逃げてくる人が多くなった。
ある日、紅梅寺に一人の女が訪れた。気品のある顔立ちであるが、長旅で疲れ果てて、今にも倒れそうであった。
「しばらくの間、お寺にとめていただけないでしょうか。どんな仕事でもさせていただきます。」
あわれに思った尼さんは、
「おみかけどおりの寺ですが、どうぞお泊り下さい。」
と、中へ案内した。女の人は、仕事ができるどころか、その日から、二度と起き上がることもできず、とうとう死んでしまったのである。どこのだれであるのか、またどこへ行こうとしたのか、まったく不明のままであった。
それから、また何年かたった。
ある日、一人の老僧が紅梅寺を訪れた。この僧は、修業のため諸国を旅している人で、たいそう偉い坊さんであったそうだ。もちろん尼さんは、そんなことを聞きもしなかったし、老僧も何も話さなかった。
しばらく行をしているうちに、紅梅寺に仏像がないことに気がついた。
「こんな、りっぱなお寺に仏像がないとは…。」
寺をたつとき老僧は、
「たいへんお世話になりました。この掛け軸は、私が肌身離さず持っていた、たいそう由緒のあるものです。
このお寺には仏像がないので、この掛け軸を差し上げましょう。」
と言って、去って行ったのである。
若く美しかった尼さんも、すっかり年をとり、やがてひっそりとなくなった。むらの人たちは、尼さんのためにお堂をたて、お祀りした。春のお彼岸には、遠くの村々からも、たくさんの人たちが集まり、そのにぎやかさは、たいしたものであったと言われる。
記録再話 和歌山県熊野川町立九重小学校