(51) 西村後ろの苦竹
山手に西村という家がある。その後ろの石がきに、今も苦竹の一群が茂っている。
ずっと、むかしの話である。椋尾[むくりょう]に、椋尾長[おさ]という強力[ごうりき]の弓の名人がいた。あるとき、椋尾長は、ちょっとしたいたずら心から、椋尾峯[みね]の殿井のぞきから、西村の石垣めがけて苦竹の矢を放った。矢はみごとに石垣にささった。矢は生の苦竹であった。なぜか、そのままにしてあった矢から、不思議なことに芽が出てきたという。
その後、この竹は増えもせず、消えもせず、毎年数本の竹が生えているという。生えてきた竹がじゃまになれば切るが、根絶えがせん。不思議なことだ、と今に語り伝えられている。
話者 山手 栗栖 光春
記録 後木 隼一
(52) 熊谷の矢の子
昔、昔、内原奥里の平山[たいらやま]のみこどりというところで、巫女[みこ]さんが、石くど立てて湯を湧かし、矢を清め、熊谷の方角めがけてヒョウと力いっぱい射たそうな。
矢は、そのまんま一里(約四キロ)もあろうかと思われる、あの熊谷の丘まで飛んだ。
そして、熊谷の丘の地面にプスッーと、さかさまになって突っ立った。
やがて、その矢から根が下り、矢の子(たけのこ)がニョキッと生えたものだから、里の衆は大騒ぎ、
「矢の子が生えた。こりゃ、ふしぎ。」
「矢の子が生えた。こりゃ、おかし。」
と、うたいながら、下の谷川から砂を上げ、石を運び、その竹の周りに積み上げて記念の石塚を建てたそうな。
(わたしの母は、先年九十才で亡くなりました。
母は晩年、目を患い、とうとうめしいの身となりました。
母は、見えないさびしさをまぎらわすかのように、よく、何やら口ずさんでいました。それは唄っているかのようでした。
わたしが、時折たずねますと、たいへん喜んで昔の話を、まるで唄うような調子で語ってくれたのでした。)
話者 内原 高津 きく
記録 滝川 富沢 たね子
再話 大野 寿男
(53) ごうらご
 わしが、六十年余り前に聞いた話じゃがな。
わしが、六十年余り前に聞いた話じゃがな。
わしが湯之原[ゆのはら]で生まれた子供の頃、じいさん(当時八十四才)から「人間は生まれた時に、いつ頃死ぬかということが、神様に決められているんじゃ。」と、聞かされたものじゃ。
昔、ある家の主人が、遠くへ出稼ぎに行っていたが、
「ぼつぼつ、子供が生まれる時期じゃあ。ちょっと帰って見んことにゃ。」
と思い、一日の仕事が終ってから帰ることにしての。
夜通し歩いて帰る途中、雨にあってしまった。雨をさけるところはないか、と探していると、ちょうど、近くに地蔵さんをまつったお堂があったんじゃ。これは助けの神だ。良い所があったと思い、
「どうか、お地蔵さん、しばらくの間、雨やどりをさせて下さい。お願いします。」と、手を合わせ、そこで雨やどりをしたわけだ。そのうちに仕事のつかれも出たのか、つい、うつらうつらしてしまったんじゃと。どれくらい時間がたったかわからんかったが、話し声でふと目が覚めてしもうた。こんな時分に、今ごろだれだろう、と耳をすますとな、なんと、自分がもたれかかっている地蔵さんと、外にいるだれかがしゃべっているんじゃよ。
「できたわよう。」
外のだれかが言う。すると、お地蔵さんが、
「そりゃ良かったな、庚申[こうしん]様。」
と言う。また、庚申様が、
「うん、夜明けにできたが、男の子でなあ。五歳の七月七日十二時に、ごうらご(かっぱ)にやることにしたわよ、お地蔵さんも一緒に行くかね。」
「いや、今日、わしはふいのお客があってな。いけんわよ、すまんが庚申様一人で行ってくれんか。」
「そうか、じゃあ、わし一人で行ってくる。また、その男の子のようすを知らせることにしよう。」
と言って、どこかへ行ってしまったようすじゃ。
うつらうつら聞いていた主人が、ねぼけまなこであたりを見ると、夜が明けていたそうじゃ。
さて、今のことは、ひょっとすると俺の子供が生まれたのではないかと心配になり、お地蔵さんに手を合わせるのもそこそこに、一生懸命、家に帰ったんじゃ。着いてみると、丁度地蔵さんの所で聞いた頃に、男の子は生まれておった。さあ大変、生まれたことは嬉しいが、五歳の七月七日十二時が心配でならなかった。なんでも、この日を守らなきゃならんと、村の庄屋に相談したところ、庄屋さんは非常に心配して、村の代表者を集め、話し合ってくれたそうだ。
「よし、地蔵さんの所で聞いた話の五歳の七月七日は、村中総出で川原で御馳走をし、男の子を真中に置いて、酒盛りをしよう。そして、ごうらごの来るのを待ってみんなでやっつけよう。」
と相談がまとまった。
いよいよ、五歳の七月七日がやって来た。するとな、子供はいつとなく川へ行きたがる。どうしても言う事を聞かない。庄屋は、
「それでは皆の衆、申しあわせのとおり。」といって川原へ行き、車座[くるまざ]になって、酒盛りをはじめた。
しばらくすると、きれいな女が、どこからとなく現われた。庄屋は、
「これが、ごうらごだ。」と直感した。
「娘さん、よう来てくれたのら。さあ、一ぱい飲んでくれ。」
と酒をついで出すと、さも嬉しそうに頭を下げ、おいしそうに一息で飲んだ。
つぎつぎと村の衆も酒をついだ。そうしている内に、ついに十二時は過ぎてしまった。女は、村中の人達と時間のたつのも知らずに酒を飲んでいたことに急に気づき、
「ああ、しもうた。十二時が過ぎた。仕方がない、残念じゃが帰ろう。」
と言って、ふらふらしながら女の姿のままで水の中に「ザンブ」ととびこみ、そのまま姿を消してしまったんじゃ。
その子は庄屋のとんちにより、命は取られず、長生きしたそうだ。
話者 湯之原 宇城 源吉
記録 小井 天野 武春
再話 玉置 辰雄
(54) もずとほととぎす
ずっとむかしのこと、鳥が集まって、酒屋で酒を飲んだのだそうだ。良い機げんで飲んでいたが、さて、支払いというときになって、もずはほととぎすに借りをした。しばらくして、ほととぎすは、もずのところに行って、貸した金を返してくれるように請求した。ところが、ずるいもずは「きっちり払うた。」というもんで、言い争いになった。実際には、支払ってなかったんだと。
すごい言い争いの結果、負けたもずは、借りた金の支払いを、虫でするという約束をしたんだそうだ。
そのことがあってから、もずは「きっちり払うた、きっちり払うた。」と鳴くのだそうだ。ほととぎすにしてみると、なかなかきちんと支払いをしないものだから、今でも「ほっても(それでも)取ってやる、ほっても取ってやる。」と鳴くのだという。
話者 那知合 後木 たけ
記録 那知合 後木 隼一(日本標準社刊「奈良の伝説」から)
(55) 大蛇の鱗とり
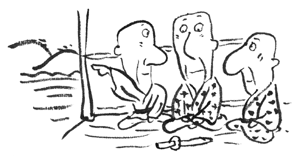 わしら子供の頃、うちのじいさんじゃった人が、ようつぎのような話をしてくれたもんじゃ。
わしら子供の頃、うちのじいさんじゃった人が、ようつぎのような話をしてくれたもんじゃ。
その話というのは、こうじゃった。
ありゃあ、なんでも天保か安政の頃のことじゃった。
ある年の、夏の日のことじゃった。その日も、お天道[てんとう]さまがようやく西の山かげに入ろうとするときじゃった。どこから来たのか、見馴れぬ旅人さんが三人、この中谷(旭)の在所にやってきてな、一晩泊めてくれというのじゃ。よくよく見ると、三人は思い思いに短い刀を腰に差し込んだ、つるつる坊主の男衆じゃ。
「いったい、お前さんら、こんな山奥へ、また、なにしに来た。」
ときくと、
「わしら、あしたこの奥へ入り大蛇をとるのじゃ。」
「なに、大蛇を。………してどうする。」
「それじゃあよ、大蛇の鱗は大金になる。わしら、大蛇を殺してうろこをはぎ、それを売ってひと儲けするのさ。」
「ふふん。……」
やがて、泊り込んだこの男たち、夕飯をすますと、大蛇とりのやりかたをぼそぼそ話してくれたものじゃ。
「わしら、大蛇の棲む岩ぐらに着いたら、笙[しょう]やひちりきを吹き鳴らすのじゃ。それから、持ってきた味噌を火でこんがり焼くのさ。笙やひちりきの音をきき、味噌のいい臭いを嗅ぐと、大蛇は岩ぐらの穴から出てくるのじゃ。大蛇はわしら三人を見つけ、大きな口をあけてひと飲みにしてしまうのさ。そして、そばにある焼味噌をペロペロなめるのさ。やがて、大蛇はのどが渇き、水を飲もうとするさ。
谷の水に大蛇が首を突っ込もうとする、そのほんの少し前に、わしら、この刀で大蛇の横っ腹を切り割って外へ飛び出すのさ。」
「もし、腹から逃げ出す前に、大蛇が水を飲んだらどうなる。」
「なに、そのときにゃ、腹の中のわしらは、とろとろに溶かされてしまうさ。」
「じゃが案ずることはない。そんなへまはせん。」
「腹から飛び出したわしらは、死んだ大蛇の鱗を一枚一枚はぎとるのよ。」
「ところでお前さん方、どうして坊主頭なのかね、つるつるじゃないか。」
「ああ、この頭か、これはな、大蛇の腹に入ったとき、まっさきに頭の毛がとかされるのよ。何回も飲み込まれているから毛が生える間がないのじゃ、ハッハハハハ。」
「ふへへ………。」
ほんまに、聞くだけで、ぞうっとする話じゃった。
翌朝、早くから起きた三人の男、用意をととのえると大蛇が棲むという岩ぐらめざして在所をたったという。
しかし、それから後のこの男衆らの音沙汰[さた]はぷっつり絶えて、今もってわからぬという。果たして、この男衆ら、首尾よく大蛇を捕ったのやら、それとも大蛇に飲み込まれ糊のように溶かされてしもうたのやら、だれも知らないのじゃと。
話者 旭 岸尾 ヒロノ
記録 上野地小学校
再話 大野 寿男
(56) 七本ひのき
 ずっと昔の話である。迫西川[せいにしがわ]に七本桧[ひのき]というのがあったという。七本桧は、元は一本だが、中途で七本に分かれ、その一本一本が二かかえも三かかえもある大変大きな木だったそうだ。もともとこの七本桧は、山の神の木として大事に祀[まつ]られていたものである。
ずっと昔の話である。迫西川[せいにしがわ]に七本桧[ひのき]というのがあったという。七本桧は、元は一本だが、中途で七本に分かれ、その一本一本が二かかえも三かかえもある大変大きな木だったそうだ。もともとこの七本桧は、山の神の木として大事に祀[まつ]られていたものである。
ある時、杣師[そまし]七人で、この七本桧を切り倒すことになった。なにしろ大きな木なので、近くの小屋に泊り込んで仕事をすることになったそうである。
さて、七人の杣師は、そろって仕事を始めた。みんなは懸命におのを振って切った。けれども、一日ではとうとう切り倒すことはできなんだと。
あくる朝、七人の杣師は、七本桧の元に行って大変おどろいた。昨日切ったはずの木っ端は一枚もなくなり、七本桧はすっかり元どおりになっていたんじゃと。
みんなは不思議でならなかったが、やりかけた仕事に取りかかった。その日も懸命に切ったが、とうとう倒すことはできなかったと。
次の朝、七本桧の元に行ってみると、やはり木っ端は一枚もなく、七本桧は元どおりになっていた。それでも、七人の杣師たちは、こりずに仕事にとりかかり、一心に切ったんじゃ。こんなことが六日間も続いた。
さすがに杣師たちも、不思議なことは夜のうちに起きるのだ、と気づいた。そこで、一度見ようではないか、ということになった。七人の杣師は、たいまつを明かして出かけて行った。七本桧に近づくと人声がする。あわててたいまつを消した。七本桧の見えるあたりまで近づいてみておどろいた。なんと不思議、七人の坊さんが
「それはこっち、これはそこへ、それはあっち……。」
と、それはそれはかいがいしく働いて、木っ端を桧の切り口にくっつけているのである。こうして七人の僧は、声をかけ合いながら仕事をすすめていたが、そのうち一人の坊さんが、
「この木っ端をもし焼かれたら困ることになるのだが。」
といったのを杣師たちは小耳にはさんだのである。だが、その時はあまり気にもかけず、ただもう七人の坊さんの仕事ぶりに見とれていた。そのうちに、とうとう七本桧は元どおりになっていた。あっけにとられているうちに七人の坊さんは消えていたそうじゃ。
七人の杣師は我に返り、今夜の不思議な出来事を話しながら帰った。そして、さっきの坊さんのことば「この木っ端を焼かれたら困る。」といったことばを思い出し、「そうだ、木っ端を片っ端から焼いていけばよいんだ。」と、よい思案も出たので、早々に床についた。
次の朝は、早くから仕事に出かけ、七人の杣師はおのを振り回し、できる木っ端をどんどん焼いていった。仕事ははかどり、夕方には、とうとう切り倒すことができたということじゃ。
その夜、七人の杣師は仕事の疲れと安心感で快い眠りについた。あけ方のこと、かしき(炊事をする人のこと)は、戸をたたく音で目を覚ました。戸を開けると、七人の坊さんが、小屋に入って来た。そして、坊さんたちは、眠っている杣師たちの頭をつぎつぎになでていった。
こうしてから、かしきに向かって、
「かしきさんは、毎朝ご飯を供えて下さるから助けてあげよう……。」
と言い残して、小屋を出ていった。
かしきは、七人の坊さんを小屋の外まで見送って行った。七人の坊さんは、小屋の近くのさいこの滝まで行くと、さっと金のにわとりに姿を変え、大空高く舞い上がったという。かしきは、この光景に見とれていたが、やがて小屋に帰ってみると、頭をなでられた七人の杣師は、みんな息がたえていたということだ。
(則本静明氏に確かめたことを一部入れた)。
話者 出谷 千葉 重実
再話 後木 隼一
(57) うさぎととちわら
ずっと、昔の話である。あるとき、うさぎがとちわら(ひきがえる)に出会って話を持ちかけた。
「とちわらさん、餅をつこうと思うとるんじゃが、いっしょにつかんかい。」
「よかろう。」
相談はすぐにまとまり、さっそく餅をつくことになった。
また、うさぎが相談をもちかけた。
「餅は山のてっペんでつきたいのじゃが、どうかい。」
「そいつは、おもしろかろう。」
と話はすぐまとまった。うさぎととちわらは、さっそく山のてっペんで餅をついた。
「さあ、餅がつけた。」
と、とちわらが喜んだとき、うさぎが、またまた相談をもちかけた。
「ここで食べるのは、ちょっとおもしろみがないじゃないか。ひとつ、この餅をうすごと転がして、先に餅を拾ったものが食べる。こうしては、どうかいな。」
「それもよかろう。やってみよう。」
ということになり、うさぎととちわらは、餅の入ったままのうすを谷底めがけて転がした。急な斜面のこと、うすは勢いよく転がっていった。その後をうさぎが勢いよく駆けていく。一方のとちわらは少しもあわてず、のっそのっそと歩いて追っかけていった。
まもなく、うすは大きな音をたてて谷底に落ちて止まった。うさぎが息せききって駆けつけてみると、うすの中はからっぽであった。びっくりしたうさぎ。
とちわらが、のっそのっそ歩いている途中に、餅が落ちていた。これはありがたいと、でんとすわりこんで食べはじめた。谷まで行ったうさぎは、なかなかもどってこない。やがて、息を切らしてうさぎがもどってきたころには、とちわらは、ほとんどもちをたいらげていた。
「とちわらさん、片方がたれているよ。」
とうさぎがいえば、
「たれててもだんない。(かまわないよ。)」
と、とちわらは食べている。うさぎは、気まずそうに残り少ない餅を傍[かたわら]で食べていたそうである。
話者 武蔵 中谷 久恵
再話 後木 隼一
(58) ワラビとハンビ
一、おしゃかさまとハンビ
ずっと、むかしのことじゃあが、あったかい春の日、おしゃかさまがくさわら(草原)を散歩しておったんじゃと。
おしゃかさまは、ひょいときれえなカタ(もよう)のついとるハンビ(マムシ)を見つけての、
「こりゃあ、かわいげなものじゃのう。(かわいらしいものだなあ。)」
と、つい、手のひらにのせてみたんじゃと。
そしたら、ハンビはなんとしたもんか、急におしゃかさまの手にかみついたんじゃと。おしゃかさまは、たいへんおこって、ハンビを地べたにたたきつけてしもうたんじゃと。びっくりして、どくろ(とぐろ)をまいとるハンビの上に、重たい石をのせてしもうたんじゃと。ハンビは、もう、動くこともどうすることもできなんだんじゃ。
何日も何日もたって、そこの地面から、なん本もなん本も、ワラビが芽を出したんじゃ。
なん本も、なん本ものワラビはの、その重たい石をそろそろ持ち上げたんじゃと。ハンビは、それで石の下からはい出して助かったんじゃと。
それから、ハンビは、ワラビに、命の恩があるんじゃあと。じゃあすか(そうだから)、村人は、山やくさわらなんかへ行くときにゃ、わかいワラビのしるをからだにぬって、
「ワラビの恩をわすれたか。」
と言うと、ハンビにかまれんいうことじゃ。
二、カヤの芽とハンビ
春さきに、ぬくうなってきたよって、土の中からハンビ(まむし)が出てきて、くさわらでどくろ(とぐろ)をまいて、ねておったんじゃと。
そしたら、カヤの芽がぐんぐんのびてきて、のんびりねておるハンビのどう中をつきぬいてしもうたんじゃと。ハンビはもう、前へも後へも、どっちへも動けんようになってしもうたんじゃと。
さて、ハンビは、びっくりしてしもうたのなんのって、くるいそうなぐらいじゃった。
「こりゃ、よわった(こまった)ことになってしもうた。どうしたもんじゃろう。」
ハンビが困りはてているところへ、ワラビがなん本もなん本も芽を出して、曲がってのびてきたんじゃと。
なん本も、なん本ものワラビが、ぐんぐん、ぐんぐんのびてきて、ハンビをおし上げてくれたよって、カヤの芽からぬけて、命が助かったんじゃと。
それから、ハンビはワラビに命の恩があるんじゃと。ほんで(それで)、春さきなんかに山やくさわらへ行くときは、ワラビのしるをからだにぬり、
「千早峠[ちはやとうげ]の初ワラビ、むかしの恩をわすれたか。」
と、となえもうて(ながら)行くと、ハンビに食われんいうことじゃと。
話者 上垣 なお
田中 資恭
採集者 林 宏
再話 後木 隼一(日本標準社刊「奈良の伝説」から)
(59) ネコとウリ
むかしあるところに、ばあさんがネコと住んでたんじゃ。
ばあさんは、ネコをえらいかわいがっとったんじゃと。
ある日のことじゃ、ひとりの旅人が、ばあさんの家へ来て、
「今夜ひと晩、とめてくだされ。」
って言うんで、ばあさんはとめることにしたんじゃと。
ほんで、旅人は、ばあさんの家へあがって、ばあさんがネコをかわいがってんのを見てたんじゃ。ほんで、その旅の人がの、
「ばあさんよ、かわいがっとるネコじゃが、そのネコかうなよ。」
って言うたんじゃと。ほいで、ばあさんが、
「なんであかんのじゃ。」
って言うたんじゃと。ほいたら旅の人はの、
「そのネコは、どうも気にくわん。」
って言うたんじゃと。ほいたらよー、ネコが旅の人の顔をじっとにらんでいたんじゃと。
旅の人は、ねるときに、
「どうも、あのネコ気にくわん。それに、わしが『どうも気にくわん。』言うたときに、わしをにらんどった。どうやら、わしがねこんだら、きっと、とびかかってくるんじゃろ。」
と思うてな、ふとんの中へ、さかさにねとったんじゃと。
ほいたら、あんのじょう、夜中にネコが旅の人の首のあたりめがけてとびかかってきたんじゃと。そやけど、さかさにねて、用心しとったよって助かったんじゃと。ほんで、旅の人は、ネコをたたき殺したんじゃと。
あくる日、ばあさんは、ネコの死がいをいけたんじゃと。
ほんでから、そのあくる年にな、また、その旅の人がやって来てとまったんじゃ、ばあさんはな、旅の人に畑でできたウリ出したんじゃと。
ほいたら、旅の人はの、そのウリ、手に持ってから、よう見とってな、
「ばあさんよ、このウリは、ネコをいけたところから、はえたウリとちがうか。」
って言うたんじゃと。
ほいで、そのウリの根ほってみたところが、そのウリは、ネコの目からはえとったんじゃと。ネコは、あだうちしようと思うとったんじゃが、旅の人が、気づいて食べなんだよってに命が助かったんじゃ。
話者 千葉 ふく
採集者 林 宏
再話 中上 武ニ(日本標準社刊「奈良の伝説」から)
(60) 山の神とかしき
 むかし、上湯川[かみゆのかわ]のうちこし(峰のすぐ向こうがわ)の紀州日高郡の小又川のおくに、ひようし(材木を切ったり、出したりする日やといの人)が、大ぜいで、山仕事に行っとったときのことじゃと。
むかし、上湯川[かみゆのかわ]のうちこし(峰のすぐ向こうがわ)の紀州日高郡の小又川のおくに、ひようし(材木を切ったり、出したりする日やといの人)が、大ぜいで、山仕事に行っとったときのことじゃと。
山があんまり遠いよってに(から)、ひようしらは、山小屋にとまりこんで仕事をしよったんじゃと。
山小屋では、若い男がかしき(すいじ係)をしとったんじゃ。男は、体は少し弱いが、まじめにはたらきよったんじゃと。
男は、毎朝、毎晩、めしをたくたびに、山の神に、供えりょったんじゃと。そして、お経をよう知らんもんじゃから、つい(ただ)、
「はんにゃしんぎょう、はんにゃしんぎょう……。」
とだっけとなえて、おがんでおったんじゃと。
ある晩のことじゃが、ひようしらの、いつもの、きょう一日のことを話しながらのゆうめしも終わり、かしきもなべのかたづけもすんで、みんなでしゃべりよったら、
「はんにゃしんぎょう、出てこーい。」
と、遠くで、大きな声で、おめく(さけぶ)のが聞こえたんじゃと。
ひようしらは、そりゃあ、ふしぎに思うたんじゃと。ほんで(それで)、耳をすまして、だまっておると、また、
「はんにゃしんぎょう、出てこーい。」
と、大きな声で、おめくのが聞こえたんじゃと。小屋の中で、ひようしらは、ちいそう(小さく)なって、
「だれん(だれが)、よびょうるんじゃろう。(よんでいるんだろう。)」
「何の声じゃろう。」
「はんにゃしんぎょう、おまえのことじゃろうか。」
なんとか、ささやいとると、またも、
「はんにゃしんぎょう、出てこーい。」
と、小屋のすぐ上で、おめくのが聞こえたんじゃと。さあ、いよいよ、ひようしらは、おとろしがって(おそろしくなって)、かしきをざしきのまんなかへすわらせて、考えたんじゃと。
いろいろ話し合ったすえ、ひようしらは、かしきを、小屋の外におし出してしもうたんじゃと。
ところが、外に出されたかしきは、ちっともおとろしゅうない。やがて、どこからともなく、
「わたしが案内します。心配せずに、ついて来てください。」
と呼ぶ声がしたんやと。かしきは、あかりも持ってないのに、道がわかるんじゃと。そして、何ものかに、心をぐいぐいひかれて、どうも、上湯川のわが家へと、どんどん歩いておったんじゃと。
しばらく歩いて、山のてっペんあたりに来たとき、ゆめうつつのように聞いたんじゃと。それは、
「やるぞー。やるぞー。」
という声と、少しして、ごろごろと石のまくれる(ころがる)音がしたかと思うと、バリバリーと小屋のつぶれるような音じゃったと。
それでも、かしきは、だれかにひかれるようにして、とうとう、家まで帰ってきたんじゃと。
こちら、ひようしらは、やれやれと思うとると、どこからか知らんけんど小屋の上あたりから、
「やるぞー。やるぞー。」
と、そりゃあ、大きな声で、おめく声が聞こえたんじゃと。
ひようしらは、なんとなく、さっきのおそろしさはのうなって、今は、ただおもしろくなって、
「やれー。やれー。」
と、だれいうとなしに、いうたんじゃと。
そしたら、また、
「やるぞー。やるぞー。」
と、聞こえたかと思うたら、ゴロゴロゴロゴロ、ドシンドシンという地ひびきといっしょに、大きな石がまくれてきて、あっというまに小屋はおしつぶされ、ひようしらは下じきになって、みーんな死んでしもうたんじゃと。
あとで、このことを聞いた村の人たちは、
「かしきは、体が弱いとか、お経もよくおぼえていない、とかいわれていたんじゃあが(いたのだが)、山の神や仏を心からおがんでいたから、あんなあぶないとき、神のみちびきで、命が助かったんじゃろう。」
と、うわさしたと、いうことじゃ。
話者 中本 豊太郎
採集者 林 宏
再話 後木 隼一(日本標準社刊「奈良の伝説」から)