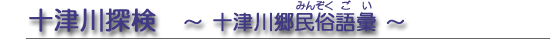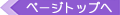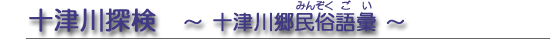| アイ |
①〔動〕貼。 ②〔般〕間 「アイの日に来てくれぇらよ」。 ③〔時〕普段、平日(旭・上葛川)。 |
| アイオイ |
〔名〕同年輩(小原・武蔵)「アイオイの年」。 |
| アイカケ |
①〔動〕川魚の一種。川底に棲み、鰓の下の鈎でアイ(鮎)を引っ掛けて捕るという。(小坪瀬・重里)。宇宮原ではチチカブという。田戸ではアイカケカブ。 ②鮎の友釣(今西)。 |
| アイカケカブ |
アイカケ(田戸)。 |
| アイカリ |
〔形〕相手を軽視して、「アイカリホウシ、何しくさっとる」。阿呆(平谷)。 |
| アイコニ |
〔副〕仲間で、代わるがわる。 |
| アイサ |
〔名〕①間(谷垣内・那知合)。空間的な隙間。 ②普段、平常(高津)「アイサにしてみるは、~」。 |
アイター
(アイヨー) |
(感)あらまあ。 アリャマアともいう。 |
| アイヅワリ |
〔産〕妻がツワリを病んでいるとき、夫もそれと似た症状を呈すること。(谷垣内)。この種の現象は大抵の大字で聞かれるが、特定の称呼をもたぬ場合が多い。今西ではツワリワケという。 |
| アイドリ |
〔狩〕小鳥を捕るための囮(上葛川)。 |
| アイナ |
〔族〕同名。 |
アイニエ
(相贄) |
〔信〕幾柱かの神々に一まとめに神饌[しんせん]を供して祭ること。本来は、祭日、祭場、供物を異にした神々を合祀して、祭りは著しく簡略化されている(内原)。 |
| アイヒキ |
〔漁〕鮎の釣り方のひとつ。友釣り。トモヅリともいう。 |
アオガエル
(青蛙) |
〔動〕雨蛙。これが鳴けば雨の兆し(旭)。 |
アオキ
(青木) |
〔植〕カシ、バベなど常線の広葉樹。和名アオキはアオキバという(旭の迫)。 |
| アオギ |
〔植〕ク口ガネモチか。大きくなればヤマノカミノキともいう(田戸)。 |
| アオキシバ |
〔植・農〕アオキの葉付きの枝。杉桧の播種[はしゅ]のとき畑のメクリ(縁)にモグラ避けに立てる(上葛川)。 |
| アオキバ |
〔植〕アオキ(谷垣内・旭・中谷)。モグラ避けに苗代の畦に立てる。 旭でアオキといえば、カシ、バベなどの常緑樹を指す。 |
| アオグチナワ |
〔動〕アオダイショウ(山手谷)。 |
アオクモ
(青雲) |
〔天〕青空。 |
| アオダイショウ |
〔動〕青大将(上湯川・松柱・山手谷・大野・玉置川)。異名多し。 |
| アオツ |
〔他〕火や穀物を煽る。小原湯之平ではヒアルともいう。 |
| アオヅル |
〔食・農〕里芋の一種。ツル(ズイキ)が青い。エグイモともいう。 →エグイモ |
| アオトリカゲ |
〔動〕尾の青いトリカゲ(トカゲ)。尾に毒があるという(上湯川)。 |
| アオナメスオウ |
〔動〕青大将、ネズミトリ、アオダイショウともいう(上湯川)。 |
| アオナメソ |
〔動〕青大将(今西・宇宮原・田戸・上葛川・旭・平谷・谷垣内・七色・山天・野尻・大野・折立ではイエマワリともいう)。
※他地方では、ナミサオ、ナムシャー(土佐佐川)、ナブサなどの方言あり。岡山県の一部の漁村では、ナメソといえば海上に漂う巨大な蛇形の偏平な?貝を指す。 |
| アオノメソ |
〔動〕アオダイショウ、イエマワリとも(松柱)。 |
アオバト
(青鳩) |
鳩の一種。畑には出て来ず、専ら山で樫の実を食べているのでカシバトとも謂い(高津・猿飼・上葛川・西川)、またその鳴き声がオアオー、ホアオー、アーオなどと聞こえるのでオアオと呼ぶ所もある(猿飼高森・野迫川村弓手原、オアオノトリとも)。鳩の仲間では一番おいしい。巣が棺桶に似ている(那知合・西中小坪瀬・重里・上葛川・田戸・旭)。 |
| アオビキ |
〔動〕アオガエル(出谷松柱・西川・上葛川)。アマガエル(玉置川)。 |
| アオム |
〔自〕アオ(緑色)が濃くなる。 |
| アガー |
〔代〕あそこ、あちら。「アガーキシヘイコウライ」(向こう岸へ行こうよ)。 |
アカゴリョウ
(赤御料) |
氏神祭に供える赤飯(谷垣内)。今西では、アズキゴリョウという。 |
| アカシ |
〔住〕(松明、蝋燭などの)照明、あかり(上湯川・西川・谷垣内)。 |
| アカシトボシ |
〔住〕照明用の種油(谷垣内)。トボシまたはトボシアブラともいう。 |
| アカシャゴマ |
〔植〕玉蜀黍の赤い毛(谷垣内)。単にシャゴマ、またはキビシャゴマともいう。 |
アカス
(明かす) |
〔他〕①照明のためにコカマツ(マツ)などを燃やす。「マツを明かす」。昔は、夜遅くまでマツをアカシてヨナベした。(一般)明るくすること。 ②線香、蝋燭(アカシ)を立てること(一般) ③秘密を暴く。 |
| アカセンバリ |
〔植・食〕タカナ(オオバカラシナ)。 |
アカダンゴ
(赤田子) |
〔信・食〕赤飯を握ったもの。山の神祭りには、これとシロダンゴ(白飯を握ったもの)を供える(樫原)。 |
アカツル
(赤蔓) |
〔農・食〕里芋の一品種。早生種でワリナによい。(『F吉野郡名山図誌』) |
| アカドヤ |
〔植〕ハナタデ(上葛川)。 |
アカバチ
(赤蜂) |
〔動〕シシバチともいう。蜂の一種。これが川の岩に巣をかけた年は大水がない。土中にスゴモッタ(巣篭もった)年は大風が吹く(田戸・上葛川)。刺されると一番痛い蜂で、先ず咬んでからそこを針で刺すという(田戸)。この蜂に刺されるとマグレル(失神する)人もいる。 |
| アカヒキ |
〔動〕赤蛙(上葛川)。食用にした。 |
| アカビキ |
〔動〕赤蛙。サンゲントビともいう(猿飼高森)。 |
| アカメシ |
〔食〕赤飯。 |
| アカリイ |
〔形〕明るい。 |
| アカリケ |
〔時〕夕方の未だ明るい時刻(松柱)。 |
| アガリト |
〔住〕踏込み(入口の狭い土間)から勝手への上がり口(上葛川)。 |
| アガル |
①〔自〕田畑の仕事を終えて家に帰る。学校から帰る。卒業する。 ②尽きる。無くなる。 ③〔信〕正月様が帰る(正月25日)ことをこう言う(上葛川)。 |
アキ
(秋) |
〔農〕米麦の収穫期。ムギアキ。 |
| アギ |
〔体〕顎。 |
アキカワ
(秋皮) |
〔住〕屋根用のカワ(杉・桧)は、8月から後に剥いだアキカワが一番良い。 |
アキタビヨ
(秋田日傭) |
〔林〕白谷(芦廼瀬川源流)の初期の出材には、秋田木材など秋田のヒヨ(日傭=人夫)が多く、これらをこう呼んだ。 |
アキトンボ
(秋蜻蛉) |
〔動〕赤トンボに似て群がり飛ぶトンボで、これが飛び出すと蕎麦を播くのでソバマキ、ソバマキトンボともいう(平谷・重里)。 |
| アキノクニ |
〔年〕明きの方(平谷)。 |
| アキビ |
〔植・食〕木通。谷瀬ではハダスともいい、小原・小井・武蔵ではハンダツと一緒だといい、秋実るからアキビだという。アケビと呼ぶところも多い(小原・小井・玉置川)。 →アクビ |
アキマツリ
(秋祭) |
〔信〕内原で奥里のトウダマツリに倣って始めた祭。 |
| アキモンズ |
〔動〕アキモンズといって百舌は秋になればやって来る。 |
| アク |
〔名〕灰。「煙草のアク」など。 |
アクニチ
(悪日) |
〔年〕①シカノアクニチ(小山手)。 ②正月三日をアクニチといい、神祭はせず休む(上葛川)。 |
| アクビ |
〔植・食〕木通(田戸)。田戸ではハダツと区別し、菓はハダツより長日で実も細長い。cfアキビ、アクビ |
| アゲ |
①〔食〕油揚げ。アゲズシ、稲荷鮨(那知合)。 ②〔地〕川の縁、側。アゲラともいう。 |
| アゲズシ |
〔食〕稲荷鮨(那知合)。 |
| アゲツク |
〔食〕大豆を油で炒めて砂糖をつけたもの(小坪瀬)。 |
| アゲッサラ |
〔形〕さかさま、仰向け。「アゲッサラ泳ぎ」=背泳ぎ。 |
| アケノヨーサ |
〔時〕明晩(串崎、那知合)。 |
| アゲラ |
〔地〕→アゲ |
| アコ |
〔代〕あすこ。アッコとも。 |
| アサイ |
〔食〕朝飯(谷瀬)。 |
アザカブ
(字株) |
〔名〕ムラカブともいう。同項参照(谷垣内)。 |
| アサギ |
〔食〕朝餉、朝食。 |
| アサゲバチ |
〔動〕蜂の一種(字宮原)。 |
| アサケンズイ |
〔食〕日の長い頃のアサイとケンズイとの間の間食(谷瀬・長殿・旭・野尻)。 |
| アサズミ |
〔林〕榊、シデ、オジコロシなどを焼いた炭(小山手)。 |
アサゼック
(朝節句) |
〔年〕節句は朝祭る。「ヨイイノコ(宵亥の子)にアサセック」という(谷垣内)。 |
| アザトイ |
〔形〕こざかしい、小利口な(あさはかな)。 |
| アサドリ |
〔動〕稲、栗、唐黍の害鳥の一、朝晩群れをなしてよく来たが、今は殆ど見ない。頬白よりやや大きく黄色い鳥(上葛川・下葛川・天川村の三名郷)。 |
| アサノカケ |
〔狩〕その日の最初の猟。アサノカケにキネズミ(栗鼡)を捕れば、その日は猟果がないという(小坪瀬)。 |
アザフシン
(字普請) |
〔村〕大字の公役。ホンコは下刈りや棺林など月に2ク(日)アザブシンに出ねばならぬ(谷垣内)。 |
| アサメシ |
〔食〕朝飯。五百瀬では4時から4時半頃にとった。 |
| アサリ |
〔林〕鋸の歯の目。アサリを分ける(鋸の歯を広げる意味)。 |
| アサリヅチ |
〔林〕大きな鋸のアサリを分けるための鋼(ハガネ)で作った槌(小原・小井)。 |
| アサリワケ |
〔林〕小さな鋸のアサリを分ける鉄製の小道具(小原・小井)。 |
アシ
(足)葺足 |
〔住〕杉桧皮を重ねて葺くとき(タケブキ)、下にならぬ部分のこと。金持ちは4寸とか5寸とかのアシだけ残して厚葺きにする。これを「四寸アシ、五寸アシニフク」という(小原)。 |
| アシカケ |
〔族〕妾。テカケとも。 |
| アシガヤ |
〔植〕芦の葉。粽[ちまき]を包むのに用いる(上湯川・重里)。寺垣内では端午に屋根に葺く。 |
アシナカ
アシナカゾウリ
(足半・足半草履) |
〔衣〕ミチユキ(道中)の時に履くと足が速い。但し用いぬところが多い。尤も水切りが良いので、筏師や舟方で穿いている人もいた(田戸)。 |
| アシノトモ |
〔体〕踵[かかと]。単にトモとも(谷瀬・山天・野尻・武蔵・大野・山手谷・猿飼・平谷・重里・出谷殿井・大桧曽・寺垣内)。 |
| アジメル |
〔他〕片づける。仕舞う。「アジメ過ぎて判らんようになった」。一部地域では、ヨジメルともいう。 |
アシモト
(足許) |
①〔農〕脱穀のとき足許に落ちた籾。 ②〔名〕アシモトノヨイ人と言えば、平衡神経が発達して一本丸太に乗っても引っ繰り返らない人。こういう人はカリカワ(一本流し)のノベになった(宇宮原)。 |
| アシラウ |
〔他〕接待、饗応[きょうおう]する。「神さんにアシラウ」(猿飼)。 |
アズキガユ
(小豆粥) |
〔信・食〕十津川郷では、小正月にも小豆飯を炊き、小豆粥など食べたことがないという所が多い(今西など)。正月様を送る弁当に赤飯を炊くからである。玉置川では、小正月にヨツギサマの残りを焚いてアズキガイ(アズキガユ)を作り、家の内外の神々に供えるが、成木責めはない。 |
アズキゴリョウ
(小豆御料) |
〔信・食〕神供用の糯米[もちごめ]の赤飯(今西)。谷垣内ではアカゴリョウという。 |
| アズキジンダ |
〔植〕ジンダ(イイギリ)の一種。小豆のような実がなり、モズが好んで食う(松柱)。 |
アズキダンゴ
(小豆団子) |
〔信・食〕①小豆と精米を一緒に炊いて餅に搗き、押餅にして四角に切ったもので、小山手片川の日光神社で撒いた。 ②ボタモチ。彼岸に作って供える(谷垣内・那知合)。 ③団子に小豆餡をつけたもの。山の神に供える(高滝・追西川)。 |
アズキメシ
(小豆飯) |
〔食〕粳(ウルチ)の赤飯。松柱・五百瀬ではオオツゴモリに必ず炊いて元日に食べる。上湯川ではイワタリの祝にオコワかアズキメシを炊く。「食うて喜ぶアズキメシ」。アズキメシといえばタダマイ(梗)に限る。稀米のオコワは聞かぬ(上葛川)。 |
| アスブ |
〔自〕遊ぶ。 |
アゼ
(畦) |
〔農〕田の下側の畦。上側のヨギに対して言う(今西)。 |
アゼカリ
(畦刈り) |
〔農〕田の畦草刈り。 |
| アゼクリムシ |
〔動〕ケラ(西川)。アゼトオシとも。 |
| アゼソリ |
〔農〕畦の草を削り落とす作業(竹筒)。 |
| アゼトオシ |
〔動〕ケラ。アゼクリムシとも(玉置川)。 |
| アゼヌリ |
〔農〕畦塗りの作業。6月上旬にやる(竹筒)。 |
| アセリ |
〔動〕鹿の牡が秋口にサカリがついて、体に泥を塗り付けること(出谷)。 |
| アソバカス |
〔他〕遊ばせる。機嫌をとって宥める。「子供らアソバカシてくれんか」。 |
アタ
(仇) |
〔名〕自分に害をするもの。怨みとなるもの。仕返し。「あのガキャー、アタするかもしれんぞ」。 |
アタマイシ
(頭石) |
〔葬〕①死者を埋葬する際に、その名を記した紙で包んで棺の上に載せる石(上葛川)。②自然石の墓標(谷垣内)。 |
| アタマノツジ |
〔体〕つむじ(寺垣内)。 →ツジ |
| アツサゲバチ |
〔動〕蜂の一種(今西)。 |
| アッチャコッチャ |
〔副〕あべこべ。右往左往する。 |
| アッパイシ |
〔葬〕埋葬した上に載せる磧[かわら]の白石(出谷小壁)。 |
| アッペ |
〔副〕あべこべ 「アッペになっとる」(小坪瀬)。 |
| アテ |
〔林〕①材(立木)の谷側、即ち陽のよく当たる面、マミに対して言う。 ②木を切り倒すとき、倒す側に深く切り込んだ切り口。ウケグチとも言う。 ③筏師用語。水勢が突き当てる所を通り抜けるためにサンカクを立てて、それに材木を編みつけて筏を通らすことを「アテつくる」と言う(宇宮原)。 |
| アテマキ |
〔林〕架線を締めるのに使った仕掛け。一端の穴に杭を突っ込んで巻きながら締めた。 |
| アトイリ |
〔族〕後妻。 |
| アトキビス |
〔体〕踵[かかと](旭、上野地、河津谷、高津)。 →キビス |
アトザン
(後産) |
〔産〕胞衣(よな)。エナ、ノチモノともいう。 →ノチモノ、ユツボ |
アトザンツボ
(後産壺) |
〔産〕自家の墓地の一隅に埋めておいて、産後にアトザンを捨てにいく(上葛川)。 |
| アトスル |
〔狩・自〕犬がシシなどの嗅跡を蹤ける。 |
アトヅレ
(後連れ) |
〔族〕夫が死んで、代わりの亭主を貰うこと。後妻はアトイリ。 |
アトトリ
(後取り) |
〔族〕後嗣ぎの息子。相続人(谷瀬)。 |
アトトリヨメ
(後取り嫁) |
〔族〕後嗣ぎ息子の嫁(谷瀬)。 |
アトノリ
(後乗り) |
〔林〕筏のナカトコに乗る役。サオを使いシモ(下)ではカイを使う。川況の悪い所ではサキ(サキトコ)の加勢にゆく(宇宮原)。 |
アナクボ
(穴窪) |
〔地〕オトシ(陥穽[かんせい])のあとなどのような凹み(出谷)。 |
| アナズル |
〔他〕侮[あなど]る(那知合)。 |
アナヅリ
(穴釣り) |
〔漁〕ウナギの穴に餌をつけた針を細い竹に付けて突っ込んで釣る仕掛け。 |
アナホリ
(穴掘り) |
〔葬〕埋葬の穴掘り(谷瀬)。 |
アニ
(兄) |
〔族〕①兄 ②長男の三人称 ③親しみをこめた年上への尊称。 |
アニゴ
(兄子) |
〔族〕アニの②のことを、こうとも呼ぶ(宇宮原)。 |
アニジャ
(兄者) |
〔族〕兄の二人称(上葛川)。 |
アネ
(姉) |
〔族〕①姉・長女。 ②女性を親しみをこめて呼ぶ言葉。 |
アネガカ
(姉嬶) |
〔族〕姉女房。「七つ違いは泣いてでも連れよ(連れ添えよ)」(重里)。 |
アネラ
(姉等) |
〔族〕女性に親しみをこめて呼ぶ言葉(平谷校区)。 |
| アノシ |
〔族〕あの人。複数形でアノシラと用いることもよくある。 |
| アバ |
〔漁〕①浮き。 〔動〕②蜘蛛の糸、良くひっかかるから筏のアバ(ブナ)に譬[たと]えていうらしい(串崎、那知合)。蜘蛛の糸のことをクモエ、グモエとも言う。 ③〔林〕アバヅナ。 |
| アバケル |
〔自〕①腫れ物などがただれる。 ②撒き散らかす。 |
| アバヅナ |
〔林〕カリカワ(狩川)の材木を集め、また筏の流失を防ぐためにドバ(土場)の川幅一杯に張り渡す太い綱。棕櫚[しゅろ]・スグリで綯る。略してアバともいう。 |
| アバナウ |
〔自〕注意して大切にする。庇[かば]う。 |
| アババン |
〔筏〕ドバ(土場)の川幅一杯にアバヅナを張り渡して、これに筏を繋ぎ、これに乗ってカマカギで材木をドバへ誘導する人夫。 |
アバラ
(肋) |
〔体〕胸。 |
アバラボネ
(肋骨) |
〔体〕肋骨。 |
アバリ
(網針) |
〔漁〕漁網編み用の竹製の針(小井)。 |
アブ
(虻) |
〔動〕一番普通の虻。他にウシアブ、コサブロウの種がある(那知合)。 |
| アブライチベ |
〔植〕イチベの一。ヤブジラミか、ウラジロともいう(上葛川)。 |
アブラウリ
(油売り) |
〔名〕山仕事を怠ける男。種油でも冷たい時は沈んでいて、午から暖かくなると一升の油が一升一合にもなる。それで、仕事を怠けて午頃から出て来る者をアブラウリという(神納川)。なお、アブラウリの油を取るアブラトリの伝承があった(那知合)。 |
| アブラカブ |
〔動〕川底に棲むカブ(鯊[はぜ]の類)の一種。15cmぐらいで、背に薄い横縞があり、脇腹あたりが飴色に透きとおった感じの魚。美味で鰻のような味がする。明治の末頃から見なくなった(田戸)。 |
アブラサシ
(油差し) |
〔林〕キンマヒキ(木馬曳き)がマクラ(枕木)に油をつけるための道具で、竹の棒の先にボウセキ糸の束を巻いたもの。 →アブラツボ。 |
アブラツボ
(油壺) |
〔林〕キンマヒキがマクラの辷[すべ]りを良くするための種油を入れる太い竹筒。キンマの先に吊るし、アブラサシを突っ込んでマクラに油を塗る。 |
アブラドックリ
(油徳利) |
〔住〕種油を入れておく壺(谷垣内)。 |
アブリ
(焙り) |
〔食〕鮎を串に刺してユルリの周りに立て並べて、遠火で焙[あぶ]り、更にツト(スド)に挿してユルリの近くに吊り下げて乾し、あとは6、7尾ずつ藁で編んで屋内に保存する。煮ても食べるが、素麺などのダシにしたら殊に美味しい(田戸)。 |
| アブリコ |
〔食〕鉄灸(上湯川・五百瀬)。 |
アホウノタカアガリ
(阿呆の高上がり) |
〔住〕資格のない者(戸主以外の者)がオクザ(横座)へ回ると、こうして嗤[わら]われる(小坪瀬)。 |
アホウダラ
アホウダラボウシ |
〔人〕馬鹿者、アホンダラ。 |
| アホウダラアマ |
〔人〕馬鹿女。 |
アホウドリ
(阿呆鳥) |
〔動〕カタカタと鳴く青い小鳥で、ルリとも違う。人おじせず捕り易いので、こう呼ぶ。アホドリともいう(松柱・田戸)。 |
アホクサー
(阿呆臭さ) |
〔形〕ばからしい。 |
| アホダラツツジ |
〔植〕ツツジの一種で年中咲いているから、こう呼ぶ。メクサリともいう(松柱)。沼田原ではボケツツジ。 |
| アホドリ |
→アホウドリ |
| アホンダラ |
〔名〕阿呆。アホンダラホウシ。アンダラともいう。 |
| アマ |
〔名〕女への卑語(出谷・串崎・那知合)。これ対して男にはホウシという。女の子はアマノコ(西川)、強調してクッサリアマとも(串崎・那知合)。アマビンタレ。 |
アマー
(甘い) |
〔形〕安易な、甘い。 |
| アマウチ |
〔住〕軒下の土間(串崎、那知合)。 |
アマオチ
(雨落ち) |
〔住〕雨垂下(今西)。 |
アマガイ
(甘粥) |
〔食・信〕甘酒の異称(高滝)。 |
| アマカゴ |
〔動〕アリマキ(輩)(西川)。 |
| アマカシ |
〔植〕樫の一種(那知合)。 |
アマゴイ
(雨乞い) |
〔農〕田畑が日照りで焼ければ谷瀬・旭・西川筋など各地で盛大にやった。例えば、谷瀬では洞川の龍泉寺までヒタバリ(火貰い)に行って、夕方から裏山に登り、各自この火を松明に移し、般若心経をくり、夜中に「アメヲ タモレ タモレヨ クモノウエノ龍王サン」と唱えながら上谷を下り、大川(十津川)の畔で磧石を打合せながら、また般若心経をくり、大川に松明を投げ込んだ。内原のようにアマゴイナガシと言って毒流しをやる所もあれば、北山川筋のようにスズキオイをやる所もあった。願が叶って雨が降れば、アメヨロコビとて村中休んで氏神へお礼参りをし、アマゴイオドリを踊る所もあった。旭では釈迦岳へ登った。 |
アマゴイオドリ
(雨乞踊り) |
〔年〕氏神の拝殿で村中が踊る。「雨はシゲシゲ、稲穂はさらり、さあ良い世の中をこの村へ」(上湯川)。 |
アマゴイナガシ
(雨乞流し) |
〔農〕大ヒヤケ(旱魃)の年には、内原奥の里の2~30町上ミのガンケツ( )のしりの長淵で大字中が寄ってオニドコロの揉み汁を流した(内原)。 |
| アマゴエ・ヒゴエ |
〔農〕雨乞い、高野山奥之院の火を戴いて松明に移して氏神に供え、それから各大字に分けて田畑を回る(重里)。 |
アマザケ
(甘酒) |
〔食・住〕 |
アマザケマツリ
(甘酒祭り) |
〔信〕山天の旧住吉社の祭。このような特定の名称はなくとも、神祭に甘酒を供えて相饗するところが極めて多い。 |
| アマシダレ |
〔住〕雨垂落ち。この線から敷居までの間をカケリという(上葛川)。 |
| アマダケ |
〔植〕竹の一種。これで吹矢を作った(田戸)。葬送のとき、モチカタは、七節のアマダケを杖にした(重里)。また、玉垣内では祭のトウヤ行事の矢を作る。 |
| ……アマッテ |
〔副〕……余。……以上(竹筒)。 |
| アマノコ |
〔名〕女の子。単にアマとも使う。 |
アマハダ
(甘肌) |
〔植〕樹皮の表皮の下の木質部との境の皮。 |
| アマビキ |
〔動〕雨蛙(今西)。 |
| アマビンタレ |
〔族〕女性の卑称。 |
アマブタイシ
(雨蓋石) |
〔農・信〕 |
| アマメ |
①〔体〕火痣。長時間、火にあたった部分の皮膚にできる斑(出谷)。 ②〔動〕アブラムシ(ゴキブリ)のこと(西川・那知合)。那知合ではヘイハチとも言う。今西などでは、ヘイハチアマメと言う。 |
アマヤスミ
(雨休み) |
〔農〕ヒヤケの折りに夕立が降るとネンギョウジ(触れ役)がオカに立って「明日はアマヤスミじゃぁぞー」と喚いて大字中に知らせ、半日なり1日なり休んだ。こうして大声で雨休みを知らせることを「アマヤスミをホメク」と言う(谷瀬・宇宮原)。 |
アマヨロコビ
(雨喜び) |
〔農〕ヒヤケ中に待望の雨が降るとジゲ中お宮へお礼参りする(谷瀬・宇宮原・旭)。 |
| アマル |
〔自〕「火がアマル」と言えば、、他に燃え広がる、延焼すること。 |
アミタテ
(網立て) |
〔狩〕谷垣内椋尾切の小地名。ここに網を張って鳥を捕らえたという。 |
アミダサン
(阿弥陀さん) |
〔信〕新興宗教の一。戦後、十津川村に入って来た。 |
| アメ |
①〔食〕飴 ②〔動〕アマゴ。アメノウオの略。滝や急湍にアメドマリ、アメダマリの名がある。 |
アメグリヒガキ
(雨栗日柿) |
〔農・天〕栗のよくできる年は雨が多く、柿のよくなる年はヒデリが多いと言う(重里)。 |
| アメダマリ |
〔地〕急湍や滝などのため、アメノウオが遡上できずに留まる箇所につく地名。今西川の上流にもある。 |
| アメドマリ |
〔地〕同上。大抵、滝になっている。 |
| アメノウオ |
〔動〕アマゴ(山女魚)。略してアメとも言う。幼魚はコサメと言う。 |
| アメマサ |
〔動〕アメノウオの特に大きなもの。滝川のソウハン淵にいたという伝説がある(内原)。 |
| アメマス |
〔動〕鱒科の魚でアメノウオの大型のものくらいに成長するが、味は少々劣る。昭和15年頃から増えている(田戸)。 |
| アヤカス |
〔他〕①(子どもなどの)機嫌をとる。あやす。タバケルとも言う。 ②お邪魔する。 |
| アヤチ |
〔名〕差別。区別。 |
| アヤテン |
〔衣〕下着の名。昔は売りに来た(五百瀬)。 |
| アラ |
①〔農〕ヒラタヒキのあと、2度目に牛を使って田をヒキ(犁き)起こす作業(竹筒)。 ②〔地〕セー(瀬)のきつい箇所。例えば西川の真砂瀬[まなごぜ]付近の赤崎アラ、串崎アラなど(重里)。 ③〔地〕急流の中間の流れの静かな箇所(田戸)。 |
| アライイネ |
〔信〕神供の洗米(上湯川寺垣内)。 |
アライシ
(粗石) |
〔地〕川原の大粒の石(平谷)。 |
| アライネ |
①〔信〕神に供える洗米(内原)。 ②〔信〕神供用の切餅(小坪瀬)。 |
アラガミサン
(荒神様) |
〔信〕ご利益も大きいが、崇りの多い怕い神様。 |
アラカワ
(粗皮) |
〔植・製〕一番外側の樹皮。カミソ(楮)の場合、内側のカミソ(真皮)に対して言う。 |
| アラキ |
〔植〕木の名(松柱)。 |
| アラク |
〔他〕→アラケル |
| アラクタイ |
〔形〕粗暴な。荒っぼい。 |
アラケル
|
①〔他〕片づける。整理する。アラク。ミケアラケ。 ②転じて、草や潅木を伐り除いて整地すること。 →ボサアラケ。 ③また、墓所の草を除き、綺麗に清掃すること。墓掃除をハカアラケと言う(小坪瀬)。 |
アラタ
(荒田) |
〔農〕土がよくこなれていない田。田植えに具合が悪い。田植え唄に、「わが殿御が鋤かく御[おん]田はアラタであれど植えよい」とある(上湯川寺垣内)。 |
アラタオコシ
(荒田起こし) |
〔農〕田に水を入れる前に、まずカラスキで鋤き起こす作業をいう。 |
| アラン |
〔語〕無い。「アラン方がよい」(内原)。 |
| アリガタサンド |
二度あることは三度ある(諺) |
アリクイ
(蟻食い) |
〔動〕アリジゴクのこと。トトムシともいう(玉置川)。 |
| アリャー |
〔感〕あらっ。 |
| アリャマァ |
〔感〕あらまぁ。 アンダ、アイヨ。 〔注〕アンダー、アイヨーと語尾を伸ばすことによって話者(聞き手)の複雑な感情が表現される。 |
| アルグ |
〔筏〕大水で筏が岸に乗り上げることを言う(重里)。 |
アワ
(粟) |
〔農・食〕 |
| アワイ |
〔名〕間(谷瀬)。 |
アワイチゴ
(粟苺) |
〔植〕5月頃にできる黄色いイチゴ(上湯川)。 |
| アワコ |
〔動〕鮎の卵(はららご)。谷のイオ(魚)はアワコで釣るが、大川(十津川本流)のイオはケラ(川虫)で釣る(宇宮原)。 |
アワシマサマ
(淡島様) |
昔、訪れた旅の下級宗教家の一。人形を入れた箱を背負って門付けし、くるりと背を向けて拝ませた。 |
| アワス |
〔食・他〕(あくの強い食物を)灰汁で中和すること。 |
アワメシ
(粟飯) |
〔食〕粟飯といっても麦など混ぜて炊いた(上湯川)。 |
アワモチ
(粟餅) |
〔食〕 |
| アンキ |
〔形〕安心、安楽に何の気苦労もなく。「アンキに暮らす」。 |
| ア(ン)グラ |
〔住〕胡座。アグラカクともアグラクムともいう(旭・谷瀬・内原・上野地・高津・平谷・山手・西中・小坪瀬・松柱・寺垣内)。 |
| アンコロ |
〔食〕ボタモチ(小坪瀬)。 |
| アンコモチ |
〔食〕(餡餅)。 |
アンザンキガン
(安産祈願) |
〔産〕 |
| アンジョウ |
〔副〕うまい具合に。「アンジョウせーよー」。 |
| アンダイ |
〔形〕心配無い。安心な。無事な。(安泰の訛か)。 |
| アンダラ |
→アホンダラ |
| アンチン |
〔職・鉱〕アンチモニー。村内数箇所にアンチモニーを採掘したシキ跡がある。高津では、明治の大水害後発見され、最盛時には従業員1000人に達した。高森にもその跡がある。 |
| アンド |
〔住〕行灯[あんどん]。カクアンド、マルアンド、テアンドなどの別がある。アンドーともいう〔小坪瀬〕。 |
| アンドー |
→アンド |
アンバヨウ
(案配良う) |
〔副〕→アンジョウ |
| アンビ |
〔食〕餡入りの餅。昔は塩味のものが多かった。 |