

| 文久3年(1863)9月、天誅組の首領中山忠光が天ノ川辻の本陣から十津川郷士に贈った趣意書。日付の下に花押(書き判)を据えているが、これは「忠光」の二字の合字体であろう。文章および筆蹟は伴林光平のもの。 同3年8月18日、天誅組は五條代官を屠り、代官所陣屋を焼き払い、桜井寺を陣屋として五條新政府を樹立した。そして民心の収攬につとめたが、18日の政変が平野国臣によって五條にもたらされると、義兵の募集や討幕の拠点としての要害をおさえる必要から、評定一決して本営を天ノ川辻に移した。 8月23日、吉村寅太郎(総裁、土佐藩士)は保母健・乾十郎を十津川郷にいれ、義兵を募った。朝命による旗挙げと信じ、郷民1500名が応じ、天ノ川辻の本陣に馳せ参じ、やがて高取城攻めに参加し、大敗する。その後、和歌山・彦根・藤堂・郡山藩などの追討軍に天誅組は包囲され、ついに十津川の天険を扼して最後の一大決戦を試みる外なく、9月14日天ノ川辻の本陣を焼き捨て、上野地村の東雲寺を本陣に屯営するさい、天ノ川辻から十津川郷士へ贈った趣意書である。 伴林光平(1813~64)は通称六郎、屋号をきせる屋ともいう。国学者、歌に能く、書にすぐれた。「河内国陵墓図」「吉野道記」「月瀬紀行」などをあらわす。天誅組では記録方と軍議衆(参謀)に推された。9月16日中川宮の令旨で十津川郷民の撤兵を説かれたので平岡武夫(北畠治房)らと南山を脱出、駒塚(今の斑鳩町のうち)にたどりついたが、同月25日、京都に赴かうとして岩船山で幕吏に捕えられ、奈良奉行所に護送された。獄中「南山踏雲録」を執筆、元治元年(1864)2月16日、京都六角の獄で同志らと斬首刑に処せられた。享年52歳。明治24年従四位を追贈される。 |
|||
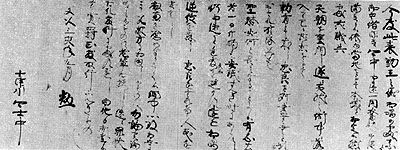 |
|||
  |