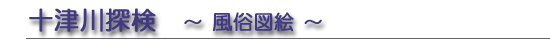

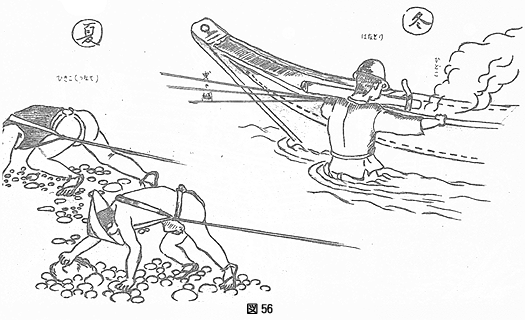 (56) 荷舟乗り 舟一艘に二人のカ子(舟夫)、二艘で一もやい(ヒトモヤイ)と云ふ。この一もやいで三人が綱引きをし、一人が鼻取りをする。 父が若い頃は、新宮通ひの荷舟乗りであった。団平舟(ダンペイブネ)に米や塩、雑貨を積み込んで、一晩又は二晩泊まりで登って来たのだ。引子(ヒキコ=綱手)は夏の眞っ盛り、やけ入って陽炎の立ってゐる磧を石に噛りつく様にして、重い舟を引っ張る苦しさ。それに引換え、舟の鼻取りは水へ這入り、荒瀬を越してアラ(川水が静かなところ)では、舟に乗って棹で操作だから至極楽なり。だが、眞冬になると水量が減り、川辺が遠浅になり、舟の座礁度が多いので水中深く入らねばならぬ。だから大抵の場合、素足である。それで舟の中に火床と云ふて、鍋の古いものなどに石礫を入れて、その上で焚き火をしてゐた。そこで使ふ薪を「火の子木」と云ふた。主に樫、馬目(バメ=バベ)の堅木の半枯れに少々生木を加へて焚いてゐた。 鼻取りは、背丈の高い人又は力の強い人が当たる。鼻取りと引き子は、夏冬に於いて苦労さが反対だ。冬季遠浅の為、舟が岸に接岸できず引子の足が濡れる時は、鼻取りに負ぶさって岸に渡してもらふ程なり。 鼻取りの使ふ張り出し棹は、遠浅のところでは差し棹よりずっと長いものを使ふが、特に急流の荒瀬で力のいるところでは、図の様に短いものを使ひ、肩にかけ精一杯の力業である。 |
||
 |