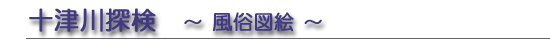

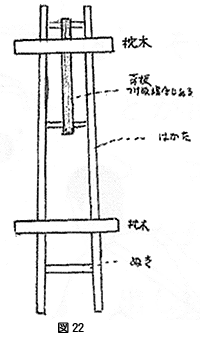 (22) 木馬-用材としてバベ(バメ=ウバメガシ)・樫が用いられた。 (22) 木馬-用材としてバベ(バメ=ウバメガシ)・樫が用いられた。牛曳用-長さ7尺、厚さ2寸、高さ5寸(最大品)、これに枕木(3寸角、長さ1尺)を付ける。 道路面に並べる盤木 徑2寸5分~3寸5分が標準、4寸以上は二ツ割とする。長さ4尺。 樹種の良質順-馬目(バメ=ウバメガシ)・ソバ=カナメモチ・マッコ=シキビ榊・ホウソ=クヌギ・桜その他、雑木(2級品) 杉、椎は急勾配の所にのみ敷く、辷りが悪いから速度抑制になる。  |
||
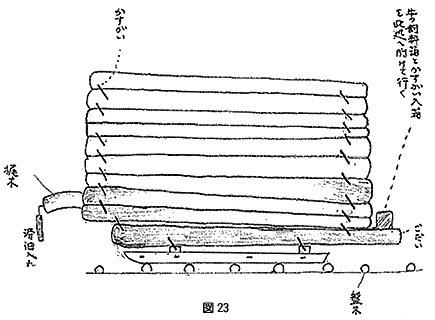 (23) 材木の側面に打ちつけて組み上げを固めるカスガイを止めるに定石がある。即ち、図の通りにする。逆に打って急停止したとき、突き上げて荷崩れの恐れあり。 (23) 材木の側面に打ちつけて組み上げを固めるカスガイを止めるに定石がある。即ち、図の通りにする。逆に打って急停止したとき、突き上げて荷崩れの恐れあり。 |
||
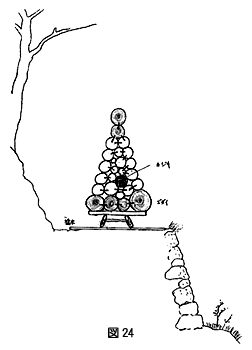 (24) 一番下の材木を「ご台」と呼ぶ。同量の材を積んでも高い方が曳き易く、荷重が少ないと云う。梶を取るにも、この辺に木馬方法の入り来る当時は、積み荷の脇にいたが、その後、積荷の中央に一本抜き出して操作するようになった。(23図) (24) 一番下の材木を「ご台」と呼ぶ。同量の材を積んでも高い方が曳き易く、荷重が少ないと云う。梶を取るにも、この辺に木馬方法の入り来る当時は、積み荷の脇にいたが、その後、積荷の中央に一本抜き出して操作するようになった。(23図)斯すれば、梶も良く利き、万一転覆したときも避難容易である。 我々が小学生当時の通学路はこの盤木を並べた林道であったので、二人並んで歩くと盤木を踏んだとき一方の端が跳ね上がって片側の一人が躓いて倒れた。雨天、下駄履きで歩むと下駄の歯に盤木を踏み込んで倒れることあり。なお盤木と盤木の間が牛の足跡で低く窪み、雨水が溜まって泥を跳ね、まことに歩行困難であった。 |
||
 |