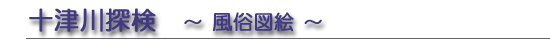

 (17)~(20) 北山の奥地より筏にて下す場合は、幾つもの激流を通るためカン止めでは抜けて用を弁じないため、陸運になる最終まで「メガ」止めにより下していた。昔は材木の両端共「メガ」を通してネジ木で組み上げた。そして大体4尺~5尺巾に仕上げる。つまり細いものは本数を多く、太いものは数少なくして調節する。そうしたものを一床(トコ)と云い、床と床を繋ぐには樫の細い棒(3尺位)を通して、捻じをかける。(図17) ネジを縛るには1型(図17)と2型(図18)がある。 時を経て力ンを案出するに至り、筏の前方になる梢口(ホボクチ)の方だけメガにして元口の方は力ン止めするものあり。又、両端共力ン組あり。なお又、床と床とを繋ぐにも両方へ小玉を打って捻じがけにするようになった。(図20) ・〔注〕力ンには、円鉄の直径二分のものを二分力ン、三分のものを三分力ンと云い、大抵の場合二分力ンと二分半力ンを使用した。(図19) 捻じ木とは、欅が第一等で、ホウソ(コナラ)、エンタ(ヒメシャラ)等、夏は檜の枝もよく使う。檜以外の枝は不可。すべて主幹を使う。檜枝は湿気あって夏は使えるが、冬は使えない。欅のネジの良品は、新宮から網と一緒に持ち帰ったと云う。それは筏の内でも要所へ使うためであった。 |
||
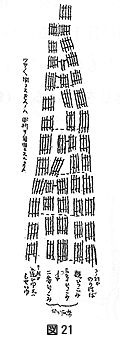 (21) 床は八ツを以て「一乗り」と云ふ。瀞からの分は15床位に長くし、それに幾乗りも合わせて惣床80に及ぶものもあった。一番長い筏〔列〕を「乗り巾」、それより一床短いものを「違い巾又はモヤイ巾」と云う。主引っ込み(オヤヒッコミ)は、乗り巾より四床下げて違い巾に吊る。その際、一床の内より二本を割り出して前に置く。二番引っ込みは主引っ込みより三床下げて主引っ込みに吊る。 (21) 床は八ツを以て「一乗り」と云ふ。瀞からの分は15床位に長くし、それに幾乗りも合わせて惣床80に及ぶものもあった。一番長い筏〔列〕を「乗り巾」、それより一床短いものを「違い巾又はモヤイ巾」と云う。主引っ込み(オヤヒッコミ)は、乗り巾より四床下げて違い巾に吊る。その際、一床の内より二本を割り出して前に置く。二番引っ込みは主引っ込みより三床下げて主引っ込みに吊る。これが下乗り筏の編製定法である。斯することにより右曲がり、左曲がり、柔軟に操作し得るのである。 ・注-吊る=つなぐ ・注-川の水は冬は細るが、筏は水を堰いて川一杯にすれば後ろから押してくれるから大きく作り、夏は水が増すので大きいと操縦し難いので却って小さく作る。 |
||
 |