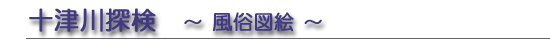

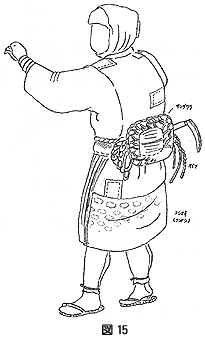 (15) 左図の女人は、藤かずらを採取に行く寒い朝の母の晩年の姿を想起して描いた。(かずらを切りに行くことを「かずら断ち」と云う。) (15) 左図の女人は、藤かずらを採取に行く寒い朝の母の晩年の姿を想起して描いた。(かずらを切りに行くことを「かずら断ち」と云う。)頑丈な体に普通の手拭い被りだけでは頬が寒いのと樹間を抜けるのに手拭いを取られぬようにと、更に上に手拭いをかけた姿は自分ながら良く描写し得たと、描き上げたとき思った。オイソ(背負い綱)は、布切れと藁の混ぜ合わせ、ない上げたもの。肩と胸に当たる部分は、組んで平たくしてある。端は普通の縄のない方である。腰当ては「サンダワラ」と云い、藁で自作したもの。脚絆は木綿の紺又は織色と云う生地製。上下は紐縛り、うしろ側は空いていた。 腰巻と云う褌は、冬はネル生地ものを下に、木綿の縞物か紺物を上に纏うているのみで、ズロースなし、自分らも文武館へ入学するまでサル股をはいたことはなかった。手甲は自家製で紐で巻いていた。 |
||
 (16) 大正5年、自分の尋常6年生当時、冬の通学途中図。右肩から風呂敷包みの教科書。左肩から両口と云う弁当入れ、中にはサイコワツパへお粥しぼりや麦飯が詰めてある。短い袷にハンチャの上着である。女の子も持ち物はこれと同様。 (16) 大正5年、自分の尋常6年生当時、冬の通学途中図。右肩から風呂敷包みの教科書。左肩から両口と云う弁当入れ、中にはサイコワツパへお粥しぼりや麦飯が詰めてある。短い袷にハンチャの上着である。女の子も持ち物はこれと同様。〔両口の説明〕 両口弁当入れは、木綿で両方共紐で絞れるようになっている。雪しぶち(吹雪)の日、濡れると口が堅く締まり、手がはぢかんで(かじかむ)いるため、ちよつと開けにくく,1年生などよく泣いたものだ。 |
||
 |