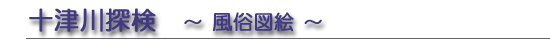

 (12) シゲ笠(菅笠)について 昭和2、3年頃の自分を筏師風体を想起して描いた図である。夏の盛りでも、脛6分位の繋ぎ綱一本と4分位の張り綱三本位と斧(ヨキ)を桿と櫂に括りつけ雨天の時は笠蓑を着用した。、帰途はそれも括りつけて担ぎ、相野谷道7里(約28km)を歩いて帰った。 図12のようなシゲ笠(菅笠)は、少々重いという欠点はあるが、丈夫な竹の骨が張ってあるので、檜笠のようにペラペラと風に吹き返されることがなくて都合よく、筏師の多くは是であった。 宮井下流に行くと風の強いこと、いつでも難所の瀬を下るとき、笠が裏返しのようになると本当に困ったものだった。 蓑は、シゲ(菅)作りと藁作りが主であった。 斧(ヨキ)は株ヨキと云っても四角株の低いものが一般的であったが、力ン(?)を抜くに都合のよい株の長いものを作った。自分の知る範囲では、長株斧の作りは自分が嚆矢であると思う。 足は単袴に素足、草鞋ばき(知恵の一つである権三草鞋)。 ・注-嚆矢(コウシ)-ことの始まり |
||
 |