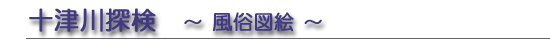

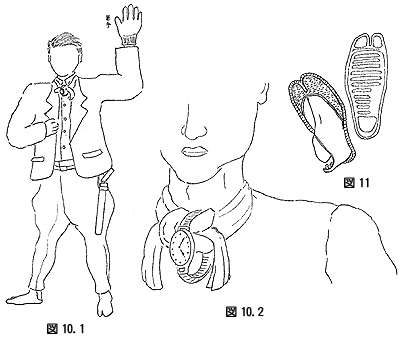 (10.1) 前にも書いたごとく、日常着が老若共洋服化したため、その古着を作業用にする結果、ズボンも上着も立派になった。しかも腕時計を持たない人が不自然に見えるようになり、作業中も手拭い、ハンカチで首に括りつけている若人が多くなった。 (10.1) 前にも書いたごとく、日常着が老若共洋服化したため、その古着を作業用にする結果、ズボンも上着も立派になった。しかも腕時計を持たない人が不自然に見えるようになり、作業中も手拭い、ハンカチで首に括りつけている若人が多くなった。(10.2) 昔の手甲は、手袋(軍手)に変わり、夏・冬ともに若人の殆どが使用するようになった。ゴム引き軍手を履くことは、滑り止めの効果があるから普及が多くなる訳だ。手袋使用は、草刈り、薪切りの女人にとっても、必ず使用しなければならない有り様である。底のない足袋をはいた祖母の若い頃から約100年の経過は、こんな変遷を見たのである。 昭和20年の敗戦から数年を経て物資豊富となり、生活にゆとりを生ずるようになるにつれ流行もあって、男子の長髪と女子のパーマ掛けが97・8%まで普及する。斯く云う自分も32~3年振りで長髪のハイカラに扮する踏ん切りをつけた。(1962年1付記) (11) 地下足袋の出初めは、大正10年からである。最初の物は足袋の裏はゴム底を外縫いに付けたものであった。それまでは、足袋でも労働用として外縫い型があった。普通型でも専売足袋と云うて図のような物があった。ネル裏でないから、温味が少なかった。 |
||
 |