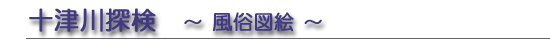

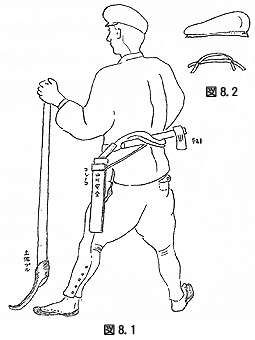 (8.1) 自分の青年時代(20歳頃)は、図のように市木木綿のハンチャを着て、腰鋸(コシノコ)と手斧(テヨキ)を持ち、足に単袴を履いた。左手にもっている土佐ヅルが出現してから大トビが廃れたとのことである。 (8.1) 自分の青年時代(20歳頃)は、図のように市木木綿のハンチャを着て、腰鋸(コシノコ)と手斧(テヨキ)を持ち、足に単袴を履いた。左手にもっている土佐ヅルが出現してから大トビが廃れたとのことである。竹柄の信州トビは軽くて使用便利である。 信州トビでも直径1寸2分位から1寸以上が普通であった。これは材木が一般に太かったから道具も大きなものが必要であった。現在は材木もだんだん小さくなって、従って道具も一寸ものが少なく、8分位が一般化した。 (8.2) その頃の若人に鳥打帽子を前高にすることが流行したことがあった。帽子の中に?型の物を入れて高くしたものだ。 |
||
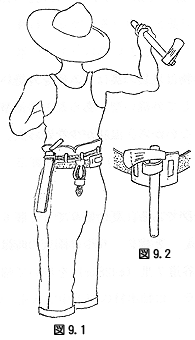 (9) なお、又その頃は架線工事も少なく、スラ出しにも藤かずらを使用する場合がかなり多かったから、ペンチの必要を感じなかった。されど今は、急激に針金使用が多くなったため、図のようにペンチは必須道具となった。服装も洋服着用が殆どとなったため、古着を作業用にしてズボンはきの姿が多くなる。ヨキを差すのも帯のときは良かったが、皮ベルトになれば差し難く、(9.2)のような特殊ベルトが考案された。夏のランニング姿も今時のことなり。裸以外は単襦袢で働いた。 (9) なお、又その頃は架線工事も少なく、スラ出しにも藤かずらを使用する場合がかなり多かったから、ペンチの必要を感じなかった。されど今は、急激に針金使用が多くなったため、図のようにペンチは必須道具となった。服装も洋服着用が殆どとなったため、古着を作業用にしてズボンはきの姿が多くなる。ヨキを差すのも帯のときは良かったが、皮ベルトになれば差し難く、(9.2)のような特殊ベルトが考案された。夏のランニング姿も今時のことなり。裸以外は単襦袢で働いた。ハンチャは、木綿手縫い、縞物、絣が多かった。 帯は普通巾の紺木綿そのままで使った。勿論一般の人みんなまでが同じ服装でないことは申すまでもなく、クケ帯は道具を差すのに都合がよい。 |
||
 |