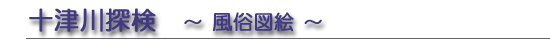

 (6) 皮羽織とカルサは、猟師に多く、山行き労働にも多し。雨に濡れて硬化するので晴天に使用した。もっとも古くなると硬化度が少なくなるが、新品は困るから突然の雨には脱いで持ち帰る父を度々見かけた。手甲も皮製のものがあった。カルサのコハゼ(鞐)も皮製。カルサの腰紐を縛るには、図に描いたごとく折り返して巻付けている。脛の方は片方が穴あき、紺木綿の衿かけ。包丁と呼ぶ山刀を腰に帯びること常なり。 (6) 皮羽織とカルサは、猟師に多く、山行き労働にも多し。雨に濡れて硬化するので晴天に使用した。もっとも古くなると硬化度が少なくなるが、新品は困るから突然の雨には脱いで持ち帰る父を度々見かけた。手甲も皮製のものがあった。カルサのコハゼ(鞐)も皮製。カルサの腰紐を縛るには、図に描いたごとく折り返して巻付けている。脛の方は片方が穴あき、紺木綿の衿かけ。包丁と呼ぶ山刀を腰に帯びること常なり。 |
||
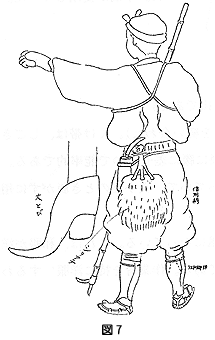 (7) 昔は竪縞の大トビと云うものを使ったとのこと。ツルの代用になる。出材夫を日傭師と云う。 (7) 昔は竪縞の大トビと云うものを使ったとのこと。ツルの代用になる。出材夫を日傭師と云う。自分の少年時代、葛川谷を黒木の堰ぎ出しをする人夫には、袂付きの着物を着て、赤い紐の襷をかけた人がいた。信州袴と云うて、今時の土方人夫が多くはいているような膝頭下までのものをつける。江戸脚絆をつける。履物は草鞋。山稼ぎと道行き、又は敏捷を必要とする狩川出しの人は、草鞋でも両側に二つ宛の紐かけ(チチと云う)を用ゆ。 船頭と筏師は一つ宛の「ゴンゾワラジ」を用いた。これは磧で小石が足裏に入ったとき手を使わずに出し易いからだと云う。後で出てくる筏師の図のところに描いてあるので参照してほしい。 尻当は尻皮とも云う。ニク(カモシカ=羚羊)の皮である。 |
||
 |