
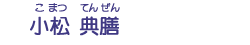
 江戸末期(1800年代)神納川に生まれる。 江戸末期(1800年代)神納川に生まれる。幼年のころより、武を好み義侠心に富んでいたという。若くして江戸にのぼり、御徒士組[おかちぐみ]の井上傳兵衛に剣法を学んで帰る。 天保9年(1838)2月、天保改革に権勢を振った鳥居甲斐守の家臣、長崎人本庄辰助(元茂平治)が貸金の取り立てを傳兵衛に依頼したが、拒否された上意見されたことを根に持ち、傳兵衛を闇打ちにした。傳兵衛の弟、伊務松山の藩士熊倉傳之丞は主家を辞し、江戸に出て傳兵衛の一子傳十郎と共にその仇討ちをはかったが、傳之丞は返り討ちにあってしまった。一説には、既に仇として狙われていることを知った本庄は、傳之丞を誘い出し殺してしまったともいう。これを知った典膳は師の仇をとり、又傳十郎の親の仇討ちを助けるべく、江戸へ行き傳十郎と力をあわせ百方探索すること数年に及んだ。たまたま弘化2年(1845)水野老中が失脚、鳥居甲斐守も捕えられた時、本庄もこれに関係して捕えられた。弘化3年(1846)8月6日、取り調べを終わり護送中の本庄を、傳十郎・典膳両名が襲撃、護持院二番ケ原で討ち果たし本懐を遂げた。 この仇討ちは、“日本最後の仇討ち”と呼ばれ、これを主題にして森鴎外は大正2年(1913)岩波書店「ホトトギス」から「護持院原の敵討」を発表、歴史考証的な文章で書かれているものの、内容は完全な創作である。 小松典膳のその後の動静は不明、生年・没年共に不詳。 (注) 人物としては不明の点が多く、取り上げることが果たして適当かどうか苦慮したが、「十津川郷士傳・歴史大辞典・森鴎外年譜」等に名前の出ていることでもあり、何より“日本最後の敵討”と呼ばれる仇討ちに十津川郷士が加勢していたことに興味を引かれ、番外として取り上げることにした。 |
|||
 |
 |