
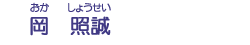
| 明治18年(1885)10月25日、父岡文昇の長男として旭に生まれる。 生家は代々林業を営む村の旧家であった。 照誠は小学校を卒えるや、五條中学校(現五條高校)に入学、更に上京後日本中学に転校、明治38年(1905)3月同校卒業、同年6月アメリカに渡り以来16年間同国に留まった。その間メッドホードのハイスクールを経て、カリフォルニアの名門スタンフォード大学に学び、後庭園樹の栽培及び種苗の育成等を研究し、一大庭園樹園を経営した。一方著述も手掛け事業と共に確固たる地歩を築いた。 大正11年(1921)7月郷里の家庭の都合上急遽廃業整理して帰朝。 以来村にあって家業に従事するかたわら、村会議員を始め方面委員・学務委員・人民総代を務めた。 十津川の支流旭川の上流宇無川峡谷は、天下の奇勝でありただ交通不便のため訪れる人は極めて少なく、隠れた景勝地となっているのを残念に思い、これが顕彰を企て、それには道路開通が先決と考え、併せて地方開拓事業を起こすため、旭西部土工森林組合を組織しこれが実現に力を尽くした。 米国において著述にも才を発揮していた照誠は、村にあっても彩雲と号し、郷土の史跡等を調査研究し出版した。即ち昭和10年(1935)「長慶天皇と楠正勝」を著した。当時長慶天皇御陵説が全国60余箇所あり、その確定をめぐって論争があった。十津川にも長慶天皇の御陵と称する南帝陵(高津)が存在したため、役場内に「長慶天皇御陵顕彰会」を設け、積極的にその正当性を主張した。彩雲著「長慶天皇と楠正勝」始め史料を整え宮内省に提出したが御陵指定には至らなかった。又古来皇室と関係の深い十津川との歴史的史実について考究を試みた文献「神武天皇と大和十津川」(昭和12年(1937)発行)、「神武天皇大和入御聖蹟考」(昭和14年(1939)発行)を十津川村史顕彰会から出版した。昭和15年(1940)紀元2600年記念事業に際し、村から史跡調査委員を委嘱された。 昭和36年(1961)12月3日、若き日には海外雄飛の夢を抱き北米に渡り、大学に学び事業を成功させ、郷里にありては地域の開発、村の歴史の解明を試みた76歳の生涯を閉じた。 |
|||
 |
 |