
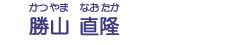
 明治33年(1900)11月14日、勝山兵吉の長男として永井に生まれる。 明治33年(1900)11月14日、勝山兵吉の長男として永井に生まれる。文武館・正気書院を経て奈良師範学校に入学、大正9年(1920)卒業と同時に折立小に赴任、以後下市・平谷各小に奉職、昭和7年(1932)、小原尋常高等小学校長となり、後折立・平谷各小学校校長に、昭和22年(1947)戦後の学制改革により誕生した第五中学校の初代校長に就任する。 早くより郷土の歴史に関心を持ち、師範学校在学中既に独自の史観を有していた。学校卒業後は、教職のかたわら村の史料を渉猟、実地に史跡を踏査するなど郷土史研究に情熱をそそいだ。 昭和11年(1936)十津川村教育会(会長榎光麿呂)より、郷土を理解し報本反始[ほうほんはんし]の風を振興するため、郷土誌編纂を委嘱され、2年余心血を注ぎ、「十津川読本」を著わした。小学校で使用する目的で、併せて十津川の地史・人文全般に亘る一般の読み物として適するよう配慮され、終戦の年まで副読本として使用された。 昭和15年(1940)折立小学校校長在勤中、紀元2,600年記念事業として、村会議員寺尾務氏と発起し、折立小学校校庭に「文武館創設地記念碑」を建立した。昭和18年(1943)村から十津川村史編纂委員に任命された。翌年(1944)高等官六等となり正七位に叙せられた。 昭和20年(1945)終戦となり、教育改革による新学制への対応、校舎の建築等諸問題の処理に追われる中、不幸病に冒され入退院を繰り返す事となった。病床常に“職員や生徒父兄に迷惑を掛けて済まない”と漏らしていた。また委嘱された村史編纂のことが絶えず念頭を離れることがなく、“息が絶えるとともに筆を置くことが出来たら本望である”とペンを執り、郷土史の構想を死の直前まで書き綴った。昭和24年(1949)8月2日、任地平谷において、寡黙にして辺幅を飾らず親に仕えて至孝、終生郷土の教育と歴史探求に情熱を傾けた49年の生涯を、現職のまま終えた。 四村学区葬の礼をもっておくられ、生地永井に帰葬された。 没年(昭和24年)正月の感懐 “四十九(始終苦)の闇の坂道よじよじて 五十路(いそじ)の光仰ぐ今日しも” (注)報本反始(礼記) 本に報い始にかえる意で、祖先の恩に報いること。 |
|||
 |
 |