
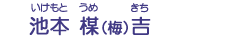
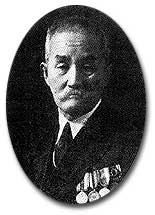 万延元年(1860)10月大字山崎に生まれる。青年時代数年間教鞭を執るが、明治22年(1889)紀和大水害による北海道移住の際は移住事務会計係として渡道、移住後は組長を務め、26年(1893)推されて移住総長となり、戸長(後の村長)と協力して村の開拓・財政・衛生更に新開地特有の浮動的人情の沈静化に努めた。27年(1894)日清戦役に際し村を代表、広島大本営に天機を奉伺、帰途東京の品川子爵を訪ね、農村振興には信用組合を設立することが肝要という論を聞き共鳴して帰る。後年全国に先駆けて信用組合を組織した構想はこの時楳吉の胸に宿ったという。28年(1895)戸長西村皓平等と図り新十津川製麻工場設立、亜麻作を奨励、村の重要な産業とした。同年、′教育にも深く留意し文武館を開設、館長の任に当たった。30年(1897)戸長となり、シシュンに未開地9万500坪・奥徳富に89万6,000余坪・上徳富に21万余坪の貸付を得て村の基本財産に編入した。34年(1901)新十津川郵便局長となり、退職の大正2年(1913)まで12年の間に公設電話の架設、局の増設等をみるなど郵政事業に尽くした。同年、開拓の一段落着き一段の進展が望まれる時期、長く胸中に秘め時期の来るのを待っていた信用組合(産業組合の始め)の設立を唱導、翌年3月創設、爾来前後30余年理事・監事としてその進展に尽くした。明治38年(1905)頃より徳富川より引水、水田開発の計画があり着々進捗しつつあったが、40年(1907)推されて組合長となり10年間その職にあった。 万延元年(1860)10月大字山崎に生まれる。青年時代数年間教鞭を執るが、明治22年(1889)紀和大水害による北海道移住の際は移住事務会計係として渡道、移住後は組長を務め、26年(1893)推されて移住総長となり、戸長(後の村長)と協力して村の開拓・財政・衛生更に新開地特有の浮動的人情の沈静化に努めた。27年(1894)日清戦役に際し村を代表、広島大本営に天機を奉伺、帰途東京の品川子爵を訪ね、農村振興には信用組合を設立することが肝要という論を聞き共鳴して帰る。後年全国に先駆けて信用組合を組織した構想はこの時楳吉の胸に宿ったという。28年(1895)戸長西村皓平等と図り新十津川製麻工場設立、亜麻作を奨励、村の重要な産業とした。同年、′教育にも深く留意し文武館を開設、館長の任に当たった。30年(1897)戸長となり、シシュンに未開地9万500坪・奥徳富に89万6,000余坪・上徳富に21万余坪の貸付を得て村の基本財産に編入した。34年(1901)新十津川郵便局長となり、退職の大正2年(1913)まで12年の間に公設電話の架設、局の増設等をみるなど郵政事業に尽くした。同年、開拓の一段落着き一段の進展が望まれる時期、長く胸中に秘め時期の来るのを待っていた信用組合(産業組合の始め)の設立を唱導、翌年3月創設、爾来前後30余年理事・監事としてその進展に尽くした。明治38年(1905)頃より徳富川より引水、水田開発の計画があり着々進捗しつつあったが、40年(1907)推されて組合長となり10年間その職にあった。大正2年(1913)村長に就任、玉置神社社殿造営村社昇格・開村記念碑及び忠魂碑の建立・村の発展繁栄は人物養成を先決とするにありとして社団法人報恩社を設立。上徳富に官有林約114万坪の払い下げを受け、村の基本財産に編入。道路の開削難所の切り下げ・橋、電灯の架設等々在職3年の間に大いに村の治政向上をみた。村長退任の後は一意産業組合の発展に力を尽くした。昭和8年(1933)春全く公務より離れ、悠々自適の生活に入った。9年(1934)農村功労者として新宿御苑観桜会に招かれる光栄に浴した。 14年(1939)3月、開村50周年記念式典挙行の日を待たずして逝く。享年79歳。新十津川開拓・発展に生涯を捧げた功績に報いるため村は村葬の礼をもって葬る。 |
|||
 |
 |