
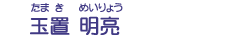
 嘉永5年(1852)12月4日重里に生まれる。 嘉永5年(1852)12月4日重里に生まれる。生来思慮深く、経理に長じていたという。18歳のとき王城警固のため、郷の先輩に連れられ上京するが、この直後兵制の改革があり、御所警衛の者は残らず伏見練兵場にて洋式訓練を受けることとなった為、明亮も直ちに伏見に入隊する。入隊後程なくして戊辰の役起こり、伏見練兵場にいた十津川兵は十津川御親兵として出陣、各地に転戦、偉功を樹てた。戦いおさまり明亮は帰郷する。 帰郷後明治16年(1883)7月、選ばれて郷中共有物取扱副幹事に当選する。因に幹事は更谷喜延であった。喜延は明治14年(1881)郷中共有物取扱幹事に当選するや、深く我が郷の疲弊窮乏を憂い、政府に士族勧業資金3万円の拝借を願い、政府の要人に働きかけまた郷の先輩の力を借りるなど、努力すること数年に及び遂に明治20年(1887)に至って許可を得た。この時幹事喜延の目的をよく理解し、陰にあって力を尽くした副幹事明亮のあった事を忘れてはなるまい。又明亮は喜延と相計り、勧業資金全てを玉置山に植林することに費やす事にあて、一村経済の基礎と為すこととした。村では勧業山と称し杉檜の植栽に努めた。明治22年(1889)8月、郷中は大水害に見舞われ死者168人・家屋の全半壊600戸に及ぶ大災害を受けた。この時川津にあった郷中会議所も難に遭い、倉庫にあった10万余円の郷有公債証書も悉く流失した。時に明亮、たまたま自宅にあったが、証書の番号をすべて自分の手帳に控えていたので、いささかの損害もなかったという。まさに用意周到“治にいて乱を忘れず”というべきか。自己の職責に忠実なることかくの如く、村治に意を用いることかくの如くであった。 明治22年(1889)全国町村制自治体改革により十津川郷は合併六ケ村となり、明亮は西十津川村長となった。間もなく水害のため6ケ村では立ち行かなくなり、1村となり、やがて推されて第2代十津川村長の職に就いた。明治26年(1893)より8ケ年間、村宰として村民に奢侈[しゃし]を戒め、勤倹を説き大いに治績を挙げた。又この間文武館館主として中学校としての基礎を確立した。(この時期、県立中学校は1県1校の為、奈良県では郡山中学校のみ、私立中学校は文武館のみであった)。 大正3年(1914)62歳をもって没した。 |
|||
 |
 |