
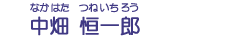
 明治5年(1872)1月28日父中畑重光の長男として折立に生まれる。 明治5年(1872)1月28日父中畑重光の長男として折立に生まれる。幼少のころより利発にして学問を好み、小学校卒業後も読書を怠らず、広く知識を求め自己の修習に努めた。 家業の農業の他、村の基幹産業であった木材業を営む。長じて木材業界から推されて木材同業組合会長となり業界の発展に尽くした。 又、東区区長を務めること6年、十津川村議会議員に3期連続当選、区や村政に貢献するところ大であった。 大正14年(1925)折立小学校改築に当り建築委員長となり、建築に力を尽くし完成に導いた。この校舎は総檜造り壮麗な威容を誇ったが、昭和26年(1951)夏、類焼により惜しくも焼失した。 大正10年(1921)4月、村立十津川中学文武館(現十津川高校)が火災により焼失した。当時の経済状態も反映し、廃館ないし休館論、移転新築して存続する再建論等議論沸騰、村を二分する数年に及ぶ大論争となった。やがて大正15年(1926)に至り、意見も移転再建にまとまり、位置も込之上浦地平に決まった。 このとき恒一郎は推されて建築委員長となり、昭和3年(1928)に至り完成をみた。 新校舎は周囲の景観にマッチし、本館・講堂・武道場等配置よく考慮され、流石十津川の最高学府に相応しい木造建築物であった。 この校舎も戦後の学制改革と共に姿を消した。 奇しくも小学校・中学校2つの校舎の建築委員長に推され、これを見事に成し遂げた恒一郎の手腕は高く評価されるべきであろう。 たとえその校舎が共に今やこの世に現存せずとも、そこに学んだ幾百幾千の生徒の胸に、木の香り、木の温もりは生きている。“為されたことは、為されている”と言うべきか。 昭和9年(1934)10月文武館理事長となり、経済的経営困難な学校運営に当たった。昭和11年(1936)6月退任。 太平洋戦争の終結を半年後にした昭和20年(1945)2月28日、聡明にして温順、人望高き73歳の生涯を生地折立にて終えた。 養嗣子政信(東京高師卒)は、長く母校文武館の教諭を務めた。 |
|||
 |
 |