
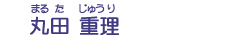
 文政8年(1825)10月19日、丸田藤左衛門を父として込之上に生まれる。 文政8年(1825)10月19日、丸田藤左衛門を父として込之上に生まれる。幼少のころより学問を好み、初め郷人西佐平太に、後山形の人清水馬之助について学んだ。天保13年(1842)郷人乾丘右衛門・深瀬茂助等と埼玉の杉山弁吉に剣術を、次いで高取藩士杉野猶助(後年元治元年文武館剣道教師となり来郷)について剣術及び柔術を習う。弘化4年(1847)三州田原藩士中村助吉にオランダ流銃練を、文久2年(1862)には郷友中藤助等、弟連[むらじ]と共に大阪の萩野正親を招き砲術を習う。重理18歳の時の鹿島神伝15代杉山弁吉の名による、直心影流の免許皆伝書が大砲模型・砲術書等とともに現在村の歴史民俗資料館にある。文久3年(1863)4月京に上り、中川宮執事伊丹蔵人はじめ諸国の志士と交わり、相会して密に国事を談じた。8月、十津川郷士は御所警衛のため入京した。しかし着京直後8月18日の政変(薩摩と会津が手を結び長州を排除した)起こり、郷士支配の七卿が長州に落ちたため、混乱を生じたが、重理は父藤左衛門と共に善後策を講じ、引き続き警衛に当たることになった。一方同時期、天誅組の乱起こり、十津川郷は義によりてこれに参加、高取城等を攻撃した。 しかしながら政変により情勢一変、天誅組は逆賊となり、幕府諸藩の追討を受けることとなった。この情報に接した藤左衛門は、急ぎ帰郷の途についたが、重理もまた父に随従し、北山郷より十津川に帰り収拾に努めた。その結果十津川は尊皇の大義により天誅組と離れることとなった。 慶応3年(1867)12月、鷲尾侍従内勅を奉じて高野山に出陣、この時多くの郷士がこれに従ったが、重理は病のため参加することが出来なかった。やがて郷士の活躍を聞くにつけ、病床にいたたまれず病をおして、藤井織之助・深瀬省吾等と幕兵残党の逮捕、軍費調達等を支援した。 その後京に帰り軍防局に大村益次郎を訪問、郷中経済向きの事に就いて陳情した。明治元年(1868)2月、御親兵人選方、軍事会計、郷中人数監察等を命じられた。明治3年(1870)積年王事勤労に付き金200両を、明治36年(1903)特旨をもって従六位に叙せられた。 明治37年(1904)10月3日、生地込之上において、文武の道に通じ、至誠一貫邦家に尽くした79歳の生涯を閉じた。 長男丸田秀實、三菱造船所長となる。 |
|||
 |
 |