
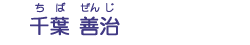
 明治18年(1885)9月6日折立の旧家新坊(姓玉置)に生まれる。長じて結婚により大字重里に居住し、千葉姓となる。文武館卒業後、兵役に服し近衛兵となり勤務成績優秀により善行賞を受ける。除隊後奈良師範学校に入学、卒業と同時に平谷小学校勤務、大正2年(1913)学校卒業後わずか3年にして校長に任用され、玉置川小学校に赴任する。8年(1919)出谷小学校に転じ、在職中昭和2年(1927)十津川村教育の為に尽力、特に地方女子の社会教育を企画実践、成果極めて顕著の故を以て十津川村教育会長より表彰をうけ、7年(1932)同上理由により奈良県知事より表彰される。同年3月重里小学校長に転任する。12年(1937)正七位高等官六等となり、14年(1939)勲七等に叙せられ、瑞宝章授章。15年(1940)奈良県教育会長より教育功労賞を、文部大臣より教育功労顕著の故を以て表彰状を受ける。 明治18年(1885)9月6日折立の旧家新坊(姓玉置)に生まれる。長じて結婚により大字重里に居住し、千葉姓となる。文武館卒業後、兵役に服し近衛兵となり勤務成績優秀により善行賞を受ける。除隊後奈良師範学校に入学、卒業と同時に平谷小学校勤務、大正2年(1913)学校卒業後わずか3年にして校長に任用され、玉置川小学校に赴任する。8年(1919)出谷小学校に転じ、在職中昭和2年(1927)十津川村教育の為に尽力、特に地方女子の社会教育を企画実践、成果極めて顕著の故を以て十津川村教育会長より表彰をうけ、7年(1932)同上理由により奈良県知事より表彰される。同年3月重里小学校長に転任する。12年(1937)正七位高等官六等となり、14年(1939)勲七等に叙せられ、瑞宝章授章。15年(1940)奈良県教育会長より教育功労賞を、文部大臣より教育功労顕著の故を以て表彰状を受ける。重里小学校在勤中のエピソード:某日低学年を校庭の一隅に集め、小さな箱を朝会台の上に置き「静かにするんだよ」と言ってやおらスイッチをいれた。かすかな声が聞こえた時の子供達の驚き、ラジオというものをはじめてみた一瞬だった。箱の後ろにまわり、横にまわり、どんな小さな人間が入っているのか懸命に眺めたものだった。 またラジオの天気予報を学校前の駐在所の壁に掲示した。当時のイカダ師はその予報を見て、「明日は午後雨だから合羽を持っていかんなあかんぞ」と合羽を持って行くとカンカン照り。「明日は曇り後晴れ、合羽はいらんぞ」といって持って行かないと午後はザンザン降り。そんなことがしばしばあったので、よくウソをつく人のことを「あれは天気予報じゃあ」という造語までうまれた。しかし昭和初年のこの時期、果たして十津川に何台のラジオがあったであろうか。重里小学校が存在した西川には電気すらなかった、そんな時代、子供の家庭に無い物が学校には有り、しかもあまりあてに出来ないとはいえ天気予報(予報の確率が上がったのはつい最近のことである)という最先端の情報発信の基地が学校にあったということは素晴らしいことではないか。校長の科学に対する先見性に敬服の他ない。 16年(1941)退職後、推されて村会議員2期勤め、38年(1963)1月22日温厚篤実、教育者として多くの功績を残し78歳の生涯を閉じた。 |
|||
 |
 |