
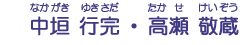
  中垣行完は文久3年(1863)1月、込之上丸田藤左衛門を祖父に、重理の次男として、敬蔵は明治16年(1883)11月16日行完の次男として出生。行完は中垣家を継ぎ、敬蔵は高取の叔父の家高瀬家を継いだ。行完は第5代村長となる等優れた人物であったが、敬蔵は幼少より極めて腕白、郡山中学に進むが、寮で規則違反を起こし処分される直前、東京へ脱走した。京華中学に籍を置いたが、素行相変わらず喧嘩に明け暮れ、正に“天下に敵なし”の気概に満ちあふれた手のつけられない暴れん坊であった。この様な子供の先行きを最も気掛かりにしていたのは他ならぬ父行完である。そしてこの子を語る時、この親を語らざる得ない出来事が起こった。たまたまこの時期、上市町の吉野郡内村長会の席上、「国策として朝鮮白頭山の森林伐採をするため、林業夫150名・筏師100名、吉野地方より斡旋して欲しい。」という要請があった。朝鮮の詳しい事情が解らず、唯命懸けの仕事であると聞かされた村長達は、反対の為喧喧囂囂[けんけんごうごう]であった。この時沈思黙考していた中垣村長はやおら席を立ち大喝一声、「これは国家の大事業だ、徒に議論をしている時ではない。私は先祖伝来の勤皇村の名誉に懸けてもこれを引き受ける。」と断言したので一同中垣村長に一任した。帰村した中垣は早速人夫の募集に掛かり、一方東京の敬蔵を迎えに行き、行完の代理人の助手とした。朝鮮に渡った敬蔵は、これこそ“命懸けの男の仕事”と惚込み事業に打ち込んだ。しかしこの時期、白頭山中は文字通り千古斧を知らぬ原始林で、匪賊[ひぞく]が出没し、軍隊に守られての危険な仕事であった。やがて幾多の困難を乗り越え、一切を取りしきることになった敬蔵は、昭和10年頃には、木材商として朝鮮全土の多額納税者第1位となり、また鴨緑江の筏流しは“流す筏は5万石”と歌われる程に発展し、郷人の面倒等よく見、侠気[おとこぎ]に富み、豪傑といわれる大実業家となった。しかし敗戦により、生涯懸けて築いた巨万の富も一瞬にして失い、無一物となって帰国した。帰国後の事業等はかばかしくなく、晩年吹田市山田弘済院にて過ごし、昭和40年(1965)12月3日、波乱に満ちた生涯を閉じた。享年82歳。 中垣行完は文久3年(1863)1月、込之上丸田藤左衛門を祖父に、重理の次男として、敬蔵は明治16年(1883)11月16日行完の次男として出生。行完は中垣家を継ぎ、敬蔵は高取の叔父の家高瀬家を継いだ。行完は第5代村長となる等優れた人物であったが、敬蔵は幼少より極めて腕白、郡山中学に進むが、寮で規則違反を起こし処分される直前、東京へ脱走した。京華中学に籍を置いたが、素行相変わらず喧嘩に明け暮れ、正に“天下に敵なし”の気概に満ちあふれた手のつけられない暴れん坊であった。この様な子供の先行きを最も気掛かりにしていたのは他ならぬ父行完である。そしてこの子を語る時、この親を語らざる得ない出来事が起こった。たまたまこの時期、上市町の吉野郡内村長会の席上、「国策として朝鮮白頭山の森林伐採をするため、林業夫150名・筏師100名、吉野地方より斡旋して欲しい。」という要請があった。朝鮮の詳しい事情が解らず、唯命懸けの仕事であると聞かされた村長達は、反対の為喧喧囂囂[けんけんごうごう]であった。この時沈思黙考していた中垣村長はやおら席を立ち大喝一声、「これは国家の大事業だ、徒に議論をしている時ではない。私は先祖伝来の勤皇村の名誉に懸けてもこれを引き受ける。」と断言したので一同中垣村長に一任した。帰村した中垣は早速人夫の募集に掛かり、一方東京の敬蔵を迎えに行き、行完の代理人の助手とした。朝鮮に渡った敬蔵は、これこそ“命懸けの男の仕事”と惚込み事業に打ち込んだ。しかしこの時期、白頭山中は文字通り千古斧を知らぬ原始林で、匪賊[ひぞく]が出没し、軍隊に守られての危険な仕事であった。やがて幾多の困難を乗り越え、一切を取りしきることになった敬蔵は、昭和10年頃には、木材商として朝鮮全土の多額納税者第1位となり、また鴨緑江の筏流しは“流す筏は5万石”と歌われる程に発展し、郷人の面倒等よく見、侠気[おとこぎ]に富み、豪傑といわれる大実業家となった。しかし敗戦により、生涯懸けて築いた巨万の富も一瞬にして失い、無一物となって帰国した。帰国後の事業等はかばかしくなく、晩年吹田市山田弘済院にて過ごし、昭和40年(1965)12月3日、波乱に満ちた生涯を閉じた。享年82歳。父行完は明治43年(1910)1月、郡会出張中上市で逝去。47歳。 行完の敬蔵に与えた教訓、“鶏口となるも牛後となるなかれ” |
|||
 |
 |