
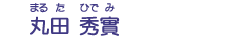
 安政6年(1859)1月22日、込之上丸田重理の長男として生まれる。 安政6年(1859)1月22日、込之上丸田重理の長男として生まれる。祖父丸田藤左衛門は幕末十津川郷士のリーダーとして活躍した。 明治初頭、維新新政府は国防の充実を急務と考え、兵制改革を行い、明治3年(1870)東京に海軍兵学寮(後の海軍兵学校)を創設したが、丸田は明治5年(1872)9月、年僅か13歳にして入校する。成績優秀であったが、特に英語は抜群であったという。在学中のエピソードとして、「一級下に後に海軍大将・総理大臣となった斎藤實がいた。英語の成績が悪く退学を免れなくなったので、教官に相談すると、“一級上に丸田という大変英語のよく出来る生徒がいるからこの人に教えてもらえ”といわれ、それで丸田さんについて英語を習い、やっと卒業することが出来た。丸田さんは私の恩人ですと後年斎藤は語っていたという。」 明治初年、丸田の兵学寮入学のこのころは日本海軍の創設期に当たり、海軍では兵学寮の俊秀を選んで海外に派遣、将来の海軍の支柱と為すことを考えていた。明治8年(1875)9名の留学生が派遣され、機関科研究のため英国2名の中に丸田がいた。丸田は7年の英国留学中、海軍造船所・グリニッジ海軍大学校に学び、明治17年(1884)1月帰朝、海軍大機関士(大尉相当)に任ぜられ、その後機関学校教授・磐城機関長・海軍兵学校教官等歴任、明治26年(1893)1月退官、同年5月三菱造船所技師長・明治38年(1905)副所長・翌年第3代三菱造船所長となる。明治44年(1911)三菱重工本社勤務・翌造船部長・大正5年(1916)専務・2年後(1918)退職する。 退職後、日本工学の重役等を務めた。明治40年(1907)飽の浦に本邦初の船型試験水槽が出来たが、丸田の建言によるものという。 海のない山国生まれの丸田が、海軍を志向し、幼にして兵学寮に入り、刻苦勉励、選ばれて海外に学び、草創期の旧海軍の艦船整備充実に力を注ぎ、無敵海軍と謳われるまでに至ったその礎を築き、あるいは我が国造船界の進展に果たした役割は誠に大なるものがあった。 三菱の創始者岩崎弥太郎は、丸田の三菱重工・三菱造船時代からの労に報いるため、東京西大久保に2,000坪の邸宅を贈った。この邸宅は太平洋戦争中惜しくも米軍の空襲により焼失した。 大正11年(1922)十津川郷士の血をうけ、誠実・豪放磊落[らいらく]・無欲恬淡の生涯を終えた。享年63歳であった。 |
|||
 |
 |