
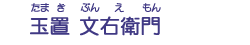
| 天保9年(1838)重里に生まれる。 文久3年(1863)8月、武力討幕の魁となった天誅組の乱には、文右衛門は檄文に応じ、進んで同郷の郷士と共にこれに参加、高取城の攻撃に参加する等活躍する。やがて京都における政変により天誅組が逆徒となるに及んで、これと決別郷里に帰る。 慶応3年(1867)将軍慶喜が大政奉還したとはいえ、会津・桑名や幕臣の中には不平を唱える者があり、当時の形勢は甚だ穏やかでなかった。そこで万一の場合に備えて、鷲尾侍従が内勅[ないちょく]を奉じて12月、高野山に兵を挙げたが、十津川郷士650人が出兵、文右衛門も参加する。12月のことであり、これを高野山義挙という。この義挙は戦闘には至らなかったが、京都と紀州の間に錦の御旗を翻し、親藩紀州や幕府軍を牽制し、官軍を有利に導いた功績は大なるものがあった。 明治元年(1868)、北陸を戦場とした討幕軍と幕府軍の戦いである戊辰の役には、討幕軍に230余人が十津川御親兵として加わり、越後に出兵する。文右衛門は越後口の出陣に郷兵と共に先鋒隊としてこれに加わり、又長岡城の奪回戦には勇戦奮闘活躍し戦功を収めた。その後各地に転戦、同年11月東京に帰還、明治2年(1869)1月、陸軍局より御親兵第1番隊散兵隊長を命じられた。6月戦功により高22石(1石:1升の100倍 約180リットル)が下賜された。8月伏見営所において、四条少将より職務勉励につき金一封が贈られた。10月小隊司令官補、明治3年(1870)3月、小隊司令官を命じられた。同年5月十津川郷親兵取締となり、同年7月大隊準四等士官を命じられ第一大隊嚮導官[きょうどうかん]を申し付けられた。明治4年(1871)陸軍少尉を命じられたが、同年11月病気の為職を辞した。 退職にあたり戊辰以来の職務精励が賞せられ、目録金60円が贈られた。 その後、明治5年(1872)奈良県庁に入り聴訴職に就くが、再び病の為職を辞し帰郷、同年8月15日、齢34歳不帰の客となった。 文右衛門は若くして明治維新の動乱期に際会、天誅組の乱・高野山義挙・戊辰の役等に従軍、軍務に服し、身命を賭して邦家[ほうか]の為に尽くした。病の為軍職を辞し、県庁に再起の道を見いだしたのも束の間、病の為道は閉ざされた。資性聡明にして剛毅、人皆前途あるこの若者の早世を惜しんだという。 (注)邦家=国、国家 |
|||
 |
 |