
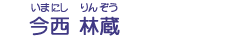
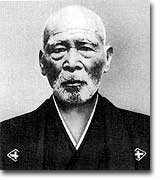 万延元年(1860)5月11日父喜代治の長男として出谷に出生、始め千葉林蔵と称したが、同じ出谷村に同姓同名の人が在ったため、紛らわしさを避けるため、姓を今西とあらためたという。 万延元年(1860)5月11日父喜代治の長男として出谷に出生、始め千葉林蔵と称したが、同じ出谷村に同姓同名の人が在ったため、紛らわしさを避けるため、姓を今西とあらためたという。幼にして寺子屋に学び、当時としては読み・書き・算盤の出来る知識人であった。その力量が認められ隣村の池津川村8か村の戸長となった。野迫川村は明治22年(1889)4月1日市町村制がしかれるまで今井村外4か村、池津川村外8か村に分かれていた。野迫川村として発足した同年6月、池津川外8か村(紫園村・立里村・中津川村・北股村・北今西村・平村・弓手原村・檜股村)の戸長であった林蔵が、玉置高良宇智吉野郡長の命で村長事務取扱となり、初代野迫川村長となった。北今西村は通称“今西”と呼ばれていたが、林蔵によって“北今西”となったという。(注 同じ郡内の十津川にも“今西”があったからであろうか。)やがて帰村した八月、西十津川村(当時の十津川村は風屋花園村・北十津川村・中十津川村・東十津川村・南十津川村・西十津川村の六か村にわかれていた)の収入役となる。役場は玉垣内の川合神社にあったが就任直後、明治の紀和大水害が起こった。この時、父喜代治はわが子の身を案じ、川合神社の対岸まで駆けつけ、林蔵の姿は認めることは出来たが如何せん濁流とうとうとして渡ることは勿論、荒れ狂う川音の為、声も届かない。一計を案じた父は無事でいることを示す為、踊りを踊って見せ、それを見た林蔵もまた無事を表すため踊ったという。未曽有の大災害の陰に川を挟んで踊りを通じて、親子の情愛を交わしたというエピソードである。26年(1893)より4年間十津川村の収入役、39年(1906)より3年間名誉助役、又総代、区長等を務め村・区・字のために尽くした。家にありては登記関係に詳しく、よく相談に応じていたという。文武館長浦武助とは親交あり、上京の行をしばしば共にしていたという。温厚にして真面目、几帳面な性格であった。 昭和18年(1943)10月27日83歳の生涯を終えた。 |
|||
 |
 |