
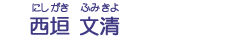
 明治32年(1899)11月21日、大字樫原に生まれる。 明治32年(1899)11月21日、大字樫原に生まれる。大正12年(1923)大日本武徳会本部剣道部聴講生として剣道への第一歩を踏み出す。 大正14年(1925)京都府巡査となり、勤務のかたわら武道に精進、剣道錬士・柔道三段となる。昭和5年(1930)退職。同時に同志社高商剣道師範に就任、昭和16年(1941)退任するが、この間に銃剣道練士・剣道教士となった。やがて同志社辞任、京都高等蚕糸学校・京都工専の剣道・銃剣道の師範となる。銃剣道教士を取得するが程なく終戦の為、武道禁止となり、師範の職を解かれる。一時同志社の農業担当教官・京都府立医科大学警備主任等を務めた。昭和33年(1958)9月、剣道再興を願う十津川村の要望を受け、十津川高校に迎えられ同時に村内中学校の剣道指導も行った。 耐えざる修練によって自己の技能を磨き、又同志社やその他の学校での指導の実績がここにおいて花開き12年の在任中、奈良県代表としてインターハイ出場連続9回という偉業を成し遂げた。 “博仙”と号し、多く和服を着用、泰然として温和明朗、指導技術に妙を得ており、生徒の持てる力を十分に導き出した。 教え子の多くは、警察官・教師として又夫れ夫れの職場において、師の教えを守り剣道を通して活躍をしており、有段者は数知れない。 教え子の中には日本の試験で最も難しいと言われ、毎年合格率僅か2%前後という八段昇段試験の難関を突破した者も2名いる。西田照夫(折立)千葉十一(出谷)である。又遠くブラジルにおいて果実園を営むかたわら、道場を開き剣道普及に情熱を燃やしている快男児、尾中弘孝(高滝)もいる。晩年歩行いささか不自由となり杖を用いていたが、一度[ひとたび]具足を着け竹刀を持って道場に立てば、足の不自由さは微塵も見せなかったのは流石であった。数々の栄光をもたらし、見事十津川剣道の復活を果たし、多くの後継者を育成、西垣剣道の名を成したが昭和45年(1974)職を辞した。余生を京都において静かに送り、昭和49年(1974)3月、剣一筋に生きた75歳の生涯を閉じた。没後七段範士が贈られた。遺言により墓は生まれ故郷大字樫原にある。教え子達は折に触れ、師の墓に詣で近況を報告し、冥福を祈ることを常としているという。 |
|||
 |
 |