
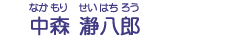
 明治38年(1905)2月25日、第13代十津川村長中森忠吉の長男として、名勝瀞峡の地、神下田戸に生まれる。葛川小学校を終え、文武館(現十津川高校)へ入学、2年の時和歌山県田辺中学へ転校するも、不幸病のため四年で中途退学し帰郷する。その後は自宅で療養に努める傍ら医学を独習した。 明治38年(1905)2月25日、第13代十津川村長中森忠吉の長男として、名勝瀞峡の地、神下田戸に生まれる。葛川小学校を終え、文武館(現十津川高校)へ入学、2年の時和歌山県田辺中学へ転校するも、不幸病のため四年で中途退学し帰郷する。その後は自宅で療養に努める傍ら医学を独習した。幼少のころより、豊かな才能に恵まれ、特に記憶力に優れ、研究心は極めて旺盛であった。小さい時は小鳥やウサギを、大きくなれば犬の解剖まで手掛け、解剖書と比較研究していたという。 機械類にも興味をもち、鉱物・化石・生物の造詣も深かったという。 やがて健康も回復、20歳後半から30歳位までの間、朝鮮に渡り、地域限定の開業医の資格取得。半年程の後帰郷、十津川村議会議員を1期務めた。 太平洋戦争中、航空食料の研究により賞金を得た事もあったという。 昭和25、6年ごろ、正式の開業医の免許を得たが、間もなく脊髄炎にかかり両足の自由を失った。病床にあっても枕元に書物を山と積み、読むこと、書くことを怠ることがなかった。 その中から東直晴の「風俗図絵」と共に民俗学上極めて貴重な文献「瀞洞夜話」が生まれた。「瀞洞夜話」がどんなものか、冒頭の一文を見れば凡の事が察せられると思う。 (冒頭文) 昭和二十八年四月六日 当時四十九歳の我 中森瀞八郎 今日よりは、我生まれてこの方見たること、聞きたること、読みたること、感じたることのうち、書き留むべしと思うものは、皆ここに記すことにせり。 この「瀞洞夜話」は、昭和36年(1961)10月16日、56歳の生涯を終える数日前まで書き続けられた。 遺文は教育委員会発行の「林宏十津川郷民俗採訪録 民俗4」に総て収録されている。尚生前、“歩くエンサイクロペディア(百科事典)”と呼ばれた和歌山県の生んだ世界的粘菌学者南方熊楠と学問的交流があったことを付記する。 |
|||
 |
 |