
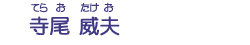
 明治38年(1905)4月5日、込之上北村文治の三男として生まれる。 明治38年(1905)4月5日、込之上北村文治の三男として生まれる。後に寺尾家の養嗣子となり寺尾姓を名乗る。幼年期、父の事業の関係で岡山県へ、次いで大阪豊中市で少年期・青年期を送る。父は非常に教育熱心で、折に触れ南朝の悲劇や、十津川郷士の維新時の活躍(威夫の祖父丸田藤左衛門は幕末十津川郷士のリーダーであった。)、天誅組の話等語って聞かせたというが、後年郷士的風格を形づくり、何事にも信念を曲げない、“剛直なバンクマン”といわれる素地となったのではあるまいか。やがて名門北野中学から京都第三高等学校を卒業したが、このクラスには湯川・朝永2人のノーベル賞学者、東大・京大の総長となった大河内・奥田の両氏を始め、その他政財界日本の各界に名を為した者は枚挙に暇がない。三高を卒え、東大法科を卒業、当初の目的とは違った野村銀行(現在の大和銀行で当時は三流銀行と言われていた)に入行、当座預金係として銀行マンの第一歩を踏み出す。やがて得意先係となり、大いに顧客を増やし、特に繊維業界へ進出した実績は“現在の大和銀行の歴史を作った”と評価された。その後太平洋戦争中の苛烈な状況のもとにあって、営業部次長、大宮・銀座の各支店長を務めた。戦後は本店総務部長に就任、占領軍による財閥解体、公職追放による混乱する銀行の中にあって諸問題に対処、解決に奔走、抜きんでてよくその職務を果たした。昭和22年(1947)2月、人事の大刷新に伴い取締役となり、3カ月後の4月には常務に登用された。昭和23年(1948)3月、創立30周年に当たり、寺尾等の意見により銀行名を大和と改称、この時専務取締役に抜擢される。 昭和25年(1950)8月、異例の45歳という若さで頭取というトップの座につく。頭取として幾多の業績を上げたが、中でも大蔵省の銀行信託分離の意向に従わず、10年余確固たる信念と先見に基づき大蔵省と争い、ついに我が国唯一の信託併営銀行と認めさせ、今日の大和銀行の基礎を確立し“大和の寺尾か、寺尾の大和か”と許された。個人的エピソードとしては、8時以降の如何なる宴会にも絶対に出ず、家に帰って読書を欠かさなかったという。昭和48年(1973)、頭取から会長となったが、この間大阪銀行協会会長をはじめ30有余の役職を兼ねた。昭和49年(1974)5月25日、惜しまれて病没。信念に生きた69歳の生涯を閉じ“銀行会の巨星落つ”と報ぜられた。生前、勲一等に叙せられ瑞宝章を賜った。 |
|||
 |
 |