
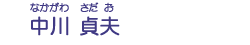
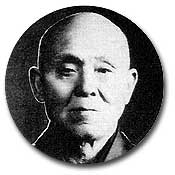 明治元年(1868)12月16日、中川行保の長男として、平谷に生まれる。 明治元年(1868)12月16日、中川行保の長男として、平谷に生まれる。中学校修業後、若くして木材組合の創立に発起人として功労があった。 村会議員・第16代・第18代村長として十津川村治に、郡会・県会議員として吉野郡・奈良県の治政に貢献した。又昭和信用組合幹事長・文武館中学理事・明治41年(1908)2月より大正11年(1922)7月まで、14年の長期間(途中約1年を除く)十津川郷木材同業組合の組長の職にあり、村の基幹産業を支える重要な役割を果たした。大正10年(1921)文武館が全焼、当時の経済情勢も反映し村を二分する休廃館論・再建論が沸き起こった。 たまたま県会議員在職中であった中川は、中等教育の重要性に鑑み再建を唱え県会に対し要約次ぎの陳情書を提出した。「県の予算を審議するに当たり文武館の補助額を増額されたい。理由は、今村では文武館の休廃館論が起こっているが、村内外の大勢はこの由緒ある学校を如何なる反対があっても、維持存続すべきと思っている、休廃館論を唱える者も所詮村の財政を憂えてのことである。補助金増額に就いて議員各位の御同情を乞う次第である。」翌年度より補助金は増額され長く続いた。かくて文武館は関東始め各地郷友会の支援もあり、移転再建に決まった。又文武館経営を安定すべく、時の村長・文武館主として財団法人化に努力成功した。 昭和3年(1928)10月、村長在任中、北海道に第2の新十津川村の建設を計画、手塩国上川郡等を視察、翌年より移住を開始した。しかしこの移住は諸般の事情から実を結ばなかった。中川は数多くの重職に在ると共に、文武館建築に当たり、山林6町歩と金5,000円、平谷小学校建築費に金5,000円、福山神社に山林3反歩を寄付する等の他、青年会・軍人後援会等を始め各種団体や公共事業に多額の寄付を行い、それが為各方面から数多く表彰された。因に中川家は屋号竹林と称し、大正12年(1923)7月、五新鉄道促進状況視察の為、奈良県成毛知事と共に来村した伯爵大木鉄道大臣が、また昭和7年(1932)11月には十津川村と文武館に差遣された子爵黒田侍従が宿泊された。貞夫の妻まさは、社会教育功労者として昭和7年(1932)昭和天皇に拝謁の光栄に浴した。養嗣子小四郎は、医学博士で日本の泌尿器学会の権威者となり、弟中川正左は、鉄道次官・交通短大学長となった。 昭和18年(1943)6月7日新宮市三輪崎にて村の発展に数々の業績を残し、75歳の生を終えた。 |
|||
 |
 |