
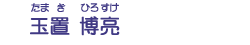
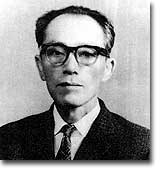 大正2年(1913)11月26日、玉置経太の長男として重里に生まれる。 大正2年(1913)11月26日、玉置経太の長男として重里に生まれる。重里小学校から十津川中学文武館(現十津川高校)を卒え、法政大学予科に入学し、昭和13年(1938)3月、同大学文学部を卒業する。 卒業後、日本ゴム工業㈱に入社、結婚、2度の召集を受け外地に勤務する。敗戦により外地からの復員後、終戦の混乱の中、役場に入り文化課長を務める。 昭和27年(1952)新しい憲法下に生まれた教育委員会制度により初代教育長に就任する。就任後、学制改革による6・3・3制の実施、教員の再教育や確保等々、幾多の困難な問題に対処してきた。 とりわけ特筆すべきことは、昭和38年(1963)に教育向上充実や教員の確保、父兄負担の軽減等を目指して「学校統合基本計画」を樹立し、43校もの小中学校を13校に統合したことである。 このことは、本村にとって文武館の創立・学制発布による各小学校の設立以来の教育上の大事業であった。村を挙げてのこの大事業には、村当局や議会を始め、村民各位の理解と協力があったことは勿論だが、反面様々な問題や障害もあった。しかし玉置は常にその先頭に立ち問題を解決し、障害の除去に努め、計画を実行に移し、遂に成し遂げる事が出来た。その功績は誠に大なるものがある。昭和43年(1968)9月、4期という長期に渡る職を辞するが、昭和46年(1971)村会議員となり、文教副委員長等を務める。しかし任期半ばの昭和49年(1974)2月2日、61歳の生涯を閉じた。 生前、痩身、眼光鋭く気骨あり、人に臆せず、歯に衣[きぬ]着せぬ発言は時に摩擦を生ずることもあったが、十津川郷士の末裔らしく悪意、私心、物欲のない性格は、多くの人の信頼を得ていた。又酒をこよなく愛した子煩悩の人柄でもあった。 読書を好み、“為された事は為されている”“人と話しをする時は相手の目をしっかり見て話せ”と常に人に説いた。 昭和37年(1962)全国教育長協議会による教育視察団に加わり、ヨーロッパを訪れ、紀行文「ヨーロッパ3週間」を出版した。 |
|||
 |
 |