
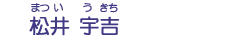
| 慶応3年(1867)4月、父青木良平母たかの五男として内野に生まれる。 幕末文久3年(1863)8月、中山忠光を首領とする“いわゆる天誅組”が五條代官所を襲撃、討幕の狼煙をあげた。決行後、天誅組は十津川に檄を飛ばし、援兵を求めた。内野村の里正(庄屋)であった父良平は、里民20数名を率いて、野崎主計・深瀬繁理・田中主馬蔵・前木鏡之進等郷士1,500余名と共にこれに応じ、各地に奮戦する。既にして京都に政変おこり天誅組は逆賊となるに及んで、十津川は離脱して郷に帰るが、天誅組追討の命を受けた紀州兵が入郷、内野に来り、良平等数名を捕らえて和歌山へ送り、獄に投じた。後放免されたが、帰国の旅費に窮し笠田村の弟に借り、漸く帰郷することが出来たという。その出陣の際における光景を字吉の兄岡豊若(郷土史家)は、「天誅組騒動の際は7歳であったが、ある夜夢の中で、人声がするので目覚め急ぎ起き上がってみれば、近隣の壮士8、9人が集まり、父はその車座の中にいて、松明皓々たる室内に盥を置き頻りに古刀を研いでいた…」と後年語っていた。 宇吉は郷里の小学校卒業後、誠之館・文武館に学び、折から文武館教授であった中沼清蔵(文武館開学の祖中沼了三の長男)・宇田康平に漢学を、桃井直正(江戸三大道場主の1人)・黒谷佐六郎に剣道の指導を受けた。長じて明治19年(1886)大阪府巡査となり職務に精励する。やがてその人となりが認められ、難波の紙商松井弥兵衛氏の養嗣子となった。 宇吉は資性温厚篤実な性格でよく養父に仕え、夫婦相和して3男4女をあげ、家業を益々隆盛に導いた。また家業の傍らよく学事・衛生・地方社会公共の為に力を尽くし、そのためしばしば表彰を受ける名誉をになった。日頃から愛郷心強く、郷里の小学校・文武館・婦人会・青年団・郷社等に多額の寄付を行った。帰郷に際しては、その都度老齢者のため浄財を惜しむことなく頒ったため、人皆その徳に敬服したという。 明治36年(1903)以来、宇吉は郷里内野に数千町歩にわたり植林したため、山形が改まったという。 昭和12年(1937)神納川区民が相はかり、その徳を永遠に伝える為頌徳碑を建立した。碑は県道川津高野線、大字五百瀬字三浦バス停横に建っている。 |
|||||
|
|||||
 |
 |
