
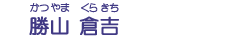
 明治15年(1882)1月、永井に生まれる。 明治15年(1882)1月、永井に生まれる。重里小学校を卒え、十津川中学文武館(現十津川高校)に入学するが、4年生のとき家事都合にて退学。20歳の時、西中次いで重里小学校の代用教員を勤め、明治36年(1903)5月、武蔵尋常小学校の代用教員となる。21歳であった。明治40年(1907)5月、本科正教員となり、6月訓導兼校長となる。時に年わずか25歳。以来他校に転勤する事一度もなく、明治・大正・昭和3代にわたり十年一日の如く30余年間、武蔵校に勤務、昭和8年(1933)8月末、惜しまれて退任した。退職前年1月、多年の教育功労が認められ、従七位に叙せられた。 在職中、学校教育においては勉学には勿論、特に徳育に厳しく、便所の掃除等は土曜日の午後、便器の枠を近くの谷へ持って行き洗わせた。 時間には厳格で、単身赴任であったが土曜日帰宅しても月曜日には、永井から武蔵まで山坂を越えて始業前に必ず出勤、袴をつけ威儀を正して授業に臨んだ。又現在の保護者会の先駆けとも言える「母子会」をつくり、毎年半夏至の日に学校と母親との懇親会を開いた。 尚、女子青年の教育を企図し、夜学「修養会」を開き“教育点呼”と称して学習達成度を調べ、教育向上を図った。又在任中、「報徳会」という会をつくり、大字民を教化したという。「報徳会」は毎月1回会合を開き、実践目標を定め実行を促し、目標を達成すれば次の目標をきめ、出来なければ出来るまで繰り返し、目標の達成に努めさせたという。 目標の例を挙げれば、 ・草履をそろえる ・時間厳守 ・病人の見舞いは短くする 等であり、これらのことは現在も守られているという。 退職後、文武館の会計等を務めたが、昭和41年(1966)7月27日、84歳で病没した。平成8年(1996)先生の全生涯をかけて慈しみ、大字の人々によって守られた学び舎は、村の文化財となり「教育資料館」として生まれ変わった。残された教えは、古き校舎と共に今も武蔵の人々の胸に残り脈々として生きている。 |
|||
 |
 |