
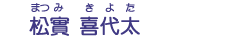
 慶応2年(1866)11月28日、樫原に生まれる。 慶応2年(1866)11月28日、樫原に生まれる。父は松實富之進又の名を漏器という。 明治8年(1875)5月より明治17年(1884)3月に至るまでの間、平谷小学校・堺師範平谷分校・文武館(現十津川高校)に学ぶ。 明治18年(1885)慶応義塾に入学するが、明治21年(1888)横浜商業学校に転じ、明治23年(1890)卒業する。同年北海道新十津川村へ移住し、農業に従事する。明治36年(1903)7月より、明治40年(1907)9月まで新十津川村長を務める。村長在任中は特に産業振興に力を尽くした。 明治38年(1905)12月より明治40年(1907)8月まで村農会の会長を務め、昭和2年(1927)4月から昭和4年(1929)3月まで再度会長職にあり農業の振興に努めた。 明治40年村長在任中の手腕が認められ、道会議員に当選、大正9年(1920)まで4期当選する。大正9年より衆望を担って国政に参画、昭和11年(1936)まで衆議院議員に当選すること5回。昭和7年(1932)功により勲三等に叙せられ、瑞宝章を賜った。昭和10年(1935)には旭日中綬章を授けられた。 松實は道会においては予算通として通り、しばしば予算委員長を務めた。国会においては終始政友会に籍を置き、財政通として予算委員・決算委員を度々務め、院内でも党内でも重きをなしていた。 代議士退任後は、札幌祖霊神社顧問、生長の家札幌相愛会長として宗教活動に従ったが、総じて家にあって晴耕雨読の生活を送った。 松實は村長、道会議員、代議士と生涯の大部分を村政、道政、国政に尽力し政界の舞台にあった。父富之進は自らを漏器と称し、明治維新という国の大変革に際会しながら、折角の機会を逃し、自らの志を遂げられなかったことを悔やんだが、その子が政治家として、父の夢を果たしたというべきではなかろうか。 松實は温厚にして親しみ深く、しかし政界では十津川郷士の末裔らしく硬骨漢で通り、直情径行の人と評された。昭和28年(1953)5月2日、87歳の生涯を閉じた。 |
|||
 |
 |