
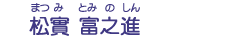
| 天保7年(1836)11月15日、樫原に生まれる。 生来資質剛毅で、幼年のころより学問を好んだという。安政5年(1858)8月より文久2年(1862)12月まで大西素堂に就いて学問を学ぶ。文久3年(1863)8月、天誅組の乱起こるや、直ちに檄に応じ、高取城の攻撃に参加するが、戦い利あらず敢え無く敗退。一方京都において政変起こり、天誅組は逆賊となり、大義名分を失った十津川は天誅組より離脱郷里に帰る。富之進は後上京、禁裏御守衛に従い、慶応元年(1865)5月、京邸執事となる。明治元年(1868)正月の鳥羽伏見の戦いには、中沼了三参謀のもと仁和寺征討総督の護衛を西村皓平・北村右京等と仰せ付かり、やがて京師に帰る。2月の天皇二条城行幸にも警護を仰せ付けられた。 同月、京都施薬院御親兵係万里小路博房卿より十津川御親兵人選方を仰せ付けられる。又同月軍事監司となり、ついで施薬院より郷中人数監察を命じられる。 十津川郷の玉置神社は崇神天皇の御代に創建されたと言い、郷社として郷民の尊崇を集めてきたが、中世に至り仏教の興隆と共に神宮寺が建てられ、神仏混淆となった。 明治維新時、諸事一新の為神仏分離令が出されたが、これにより廃仏毀釈が行われ、全国的に寺が廃された。 十津川においてはいち早く廃仏に決し、明治2年(1869)玉置神社復古の願いが許可されたため、富之進はこれが処理に当たり、丸田藤左衛門・更谷喜延等と京都を発し帰郷する。郷において聚議館役員及び郷中各組総代一名宛玉置山に集合させ、復古の報告祭を行い、諸般の処理を断行し、京に帰る。十津川における廃仏の最初である。 明治2年郷士の間に御所警衛の在り方に端を発し、新旧思想2派の間に抗争を生じ、そのため一方に属した富之進は郷中紛擾の罪により厳しい処分を受けた。明治14年(1881)宇智吉野郡書記となる。 明治22年(1889)の十津川大水害に際しては、難民の救済策として北海道移住が企てられ、600戸2,600人がこれに応じた。このとき富之進は、移民団の副頭取を務め、自らも新十津川に移住、開墾事業に従事、明治37年(1904)4月、68歳の生涯を終えた。富之進は維新の風雲に際し時流に乗り切れなかったという意味で、漏器と称した。 |
|||
 |
 |