
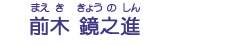
 天保11年(1840)風屋久保(前木家屋号)に生まれる。 天保11年(1840)風屋久保(前木家屋号)に生まれる。諱[いみな]は義照、通称鏡之進と称した。幼年より武技を好み、剣を館林の藩士に学んだ。郷内屈指の剣客と謳われ好んで赤鞘の大刀を腰にしていた。 文久3年(1863)8月、中山忠光を奉じた天誅組が大和五條において代官所襲撃挙兵、十津川に檄を飛ばすや、鏡之進は野崎主計・深瀬繁理・田中主馬蔵等と共に、天ノ川辻の陣営に馳せ参じた。時に鏡之進年24歳。 やがて京都の政変の報が伝わり、十津川郷は天誅組を離脱帰郷した。 既にして浪士追討令が発せられていたため、その善後策に努めた。 爾来、京都にあって御所警衛の任に従う。滞京中、七卿都落ちのことがあったが、五卿帰京の際同志と共に伏見にこれを出迎え、警護して入京した。明治初年御所警衛の郷士の間に意見の衝突があった。諸種の論争の要因があったが直接には、警衛中の郷士に伏見練兵場において洋式訓練を受けるように指示があったが、これに賛成反対の二流が生じた。 鏡之進は所謂従来どおりの御所警衛を主張する保守派であり、伏見練兵場に入り洋式訓練を受けることに反対であった。そのため帰郷謹慎を命じられたが、丸太町の剣客吉田数馬方に寄寓して帰郷しなかった。明治2年(1869)横井小楠要殺事件あり嫌疑をかけられたが容疑晴れて放免され帰郷した。郷里にあって鏡之進は保守派を牛耳り、前木党と呼ばれ開進派に対抗した。明治2年紛擾取り鎮めのため来郷の役人に呼び出しをうけた鏡之進は、たまたま和歌山県本宮に居たが、直ちに家に帰り衣服をあらため、決死の書をしたため、これを懐中にして召喚に応じるべく出発した。 三里山を越える時、前方より巡察使の来るを聞き、籠の中で切腹し、明治2年6月13日、西吉野村和田で絶命した。享年僅か29歳であった。 鏡之進は資性豪胆、勝ち気で人に屈することが嫌いであった為、しばしば知己とも離れることがあった。しかし奉公の念は極めて強くかつて画家をして自らの像を描かしめ、その上に「生者現天子御膝元奉仕…」と書していた。 切腹の際懐中にしていた書面には、「(大意):私のしたことは一途に皇国の御為にしたことである。ことここに至ったこと死をもって御詫びする。郷中永く勤王出来ますようよろしく。」 と記されていた。 死後、郷中紛擾責任者として厳しく処分されたが、明治22年(1889)許された。 |
|||
 |
 |