
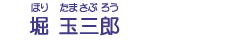
 明治38年(1905)和歌山県朝来村に生まれる。 明治38年(1905)和歌山県朝来村に生まれる。若くして十津川村の堀藤蔵の養嗣子となり、家業の建設業を継ぎ、努力を重ね業界の第一人者となった。 戦後の昭和22年(1947)推されて奈良県会議員となり、以来3期12年その職にあった。 議員在職中、各常任委員長・副議長を務め、昭和30年(1955)には、遂に議員最高の栄誉である議長の職に就き手腕を発揮した。 彼の議員在職中は、混乱した戦後の中にあって、吉野熊野地域総合開発にかかる電源開発、国道168号線の貫通、十津川分水の一連の事業にその完成を目指して積極的に努力した。 吉野熊野地域総合開発は奥吉野にとって、とりわけ十津川にとっては、正に村始まって以来の「秘境」あるいは「陸の孤島」という呼び名の返上を可能にする大きな開発事業であった。従ってこの事業にかけた玉三郎の熱意は並々ならぬものがあった。努力の成果は、昭和34年(1959)8月、168号線の新宮までの開通、10月より待望のバス運行、昭和35年(1960)10月、電源開発の第一歩である風屋ダムによる第一発電所の発電開始によって現れた。玉三郎は常に書に親しみ、研鑽[けんさん]を怠る事なく、とりわけ歴史を好み史実によく通じていた。 人とよく交わり、談論風発、歴史を語り、政治を語り、茶道等を語り、人を飽かせることがなかった。例えば若者には、“来客があり、客が帰るときは門に立ち、客の姿の見えなくなるまで見送るのがお茶の極意である”等、談笑の内に教え諭していた。 昭和34年(1959)政界から身を引いたが、世人は尚持てる政治力に期待する所が大であった。 昭和38年(1963)5月15日、学問を好み、誠実に生きた58歳の生涯を閉じた。生前の功績に対し従六位が贈られた。 没後、故人の功徳を慕う野迫川村・西吉野村・大塔村・十津川村の4村と有志の手によって昭和40年(1965)11月、頌徳碑が建てられた。 碑は国道168号線に面し、上野地駐在所の隣にある。 撰文は時の十津川村長玉置直通である。 |
|||
 |
 |