
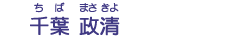
 明治43年(1910)8月30日、千葉芳治郎の長男として重里に生まれる。 明治43年(1910)8月30日、千葉芳治郎の長男として重里に生まれる。昭和3年(1928)十津川中学文武館(現十津川高校)卒業後、国学院大学入学、昭和8年(1933)同校史学科卒業。直ちに大阪毎日新聞社入社、ジャーナリストとして未来を約束され、日ごろの夢であった“無冠の帝王”への第一歩を、四国松山支局の新聞記者として大きく踏み出す。やがて本社に帰るが、時あたかも日中戦争に突入、記者の仕事は多忙を極め、加えて生来の勤勉さが無理の上に無理を重ね、疲労の為健康を害し、遂にジャーナリストヘの思いを断ち郷里に帰った。帰郷後しばらくして、請われて母校文武館で教鞭を執る。2年後、樟蔭女子専門学校の教授となり大阪に転居する。上阪後、太平洋戦争勃発、戦局の悪化と共に、日夜の空襲下、学校に、勤労動員先(大阪郵便局)にと心身を消耗、ようやく戦いの止んだ昭和22年(1947)、初春の寒気の厳しさに耐えられず2月18日、布施市(東大阪市)中小坂の仮寓にて不帰の客となった。齢わずか30有8。幼少時より理知的、探求心極めて旺盛な秀才であり、小学校より大学まで常に優等生であったという。因に中学校卒業の時は県知事賞、大学卒業の際は学長賞が授与されている。国史の研究に志し、とりわけ、郷土史に関しては郷友会誌、新聞紙上にしばしば該博な所論を発表した。又母校や樟蔭の教壇に立つや、厳格熱誠をもって指導に当たり、薫陶[くんとう]を受けた者、敬服して止まなかった。 昭和29年(1954)、政清の恩師元文武館長浦武助先生の編集により「千葉政清遺文集」が十津川村役場より発刊された。その序の最後に、時の村長、後木実氏は「・・・戦後既に十年を経過し、今こそ正しい歴史を求めて、新しい国造り、村造りをせなければならない時、彼の死こそ惜しみても余りがある。彼の生涯は長いものではなかったが、その遺された文献は村史完成への貴重な資料として後世に役立つであろうと信じて疑わない。」と結んでいる。限りなく学問を愛し、書架の一端に「万金の富も一巻の書に如かず」と記し、書籍には格別の愛着を持たれたが、今その蔵書は村に寄贈され教育委員会の一室に収納されている。 二津野ダムの湖水を見渡す平谷に墓地がある。浦先生の墓碑銘に曰く「資性忠純 好学直行心竊期大成 学於国学院大学 誨於樟蔭女子専門学校 昭和二十二年二月病没 享年僅三十有八 噫 天何奪斯人之急也」 没後50年になんなんとする時、「ああ天何ぞこの人を奪うことの急なるや」この思い正に切。 |
|||
 |
 |