

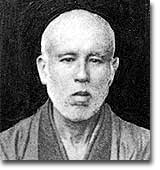 天保13年(1842)池穴に生まれる。 天保13年(1842)池穴に生まれる。文久3年(1863)8月、御所警護の為上京、元治元年(1864)蛤御門の戦いに出動する。明治元年(1868)2月、十津川御親兵人選の軍事書記を命じられる。同年4月伏見練兵場へ入隊、陸軍筆官を務める。明治2年(1869)3月、天皇再度の御東行に際し、伏見の十津川隊は供奉仰付かり、孝則は天皇に従い東上した。同年6月、役目を果たし伏見に帰営、明治5年(1872)兵制改革を機に帰郷した。 明治13年(1880)宇智吉野郡役所書記となる。郡役所在勤中の明治22年(1889)8月、未曽有の紀和大水害に遭遇、孝則は郷出身の西村皓平(山手)と共に十津川の罹災者救済、北海道移民に懸命に努力をした。 孝則は幼少より学問を好み、文才豊かであったが、郡役所在勤中は余暇を見つけ、郷土に関する史料を収集、岡嵩南著「吉野郡水災誌」の編纂に携わり、又「十津川記事」を著した。「吉野郡水災誌 全11巻」は明治大水害時の災害状況が克明に記録され、当時の実情を知る貴重な資料である。 「十津川記事 上中下3巻」は嘉永6年(1853)6月より明治41年(1908)末までの郷の出来事、郷人の人事等が記され、これ又水災誌と同様郷土の歴史を知る上で重要な資料となっている。 郡役所を退任した孝則は一時五條に居を構えたが、やがて郷里に帰り渓堂と号し文筆に親しみ、悠々自適の生活を送った。  晩年大正3年(1914)上杉直温(今西・3代村長)と相計り、村内の名所・旧跡・故人の事績・村の由緒並びに村内55か大字を和歌に詠み「十津川集」として発刊、村人の郷土知識普及に大いに貢献した。 晩年大正3年(1914)上杉直温(今西・3代村長)と相計り、村内の名所・旧跡・故人の事績・村の由緒並びに村内55か大字を和歌に詠み「十津川集」として発刊、村人の郷土知識普及に大いに貢献した。大正8年(1919)8月、77歳で没した。池穴に葬る。 十津川集より和歌2題 ☆湯之原 “いにしへは出湯のけぶり立ちしかど いまは名のみの湯の原の里” ☆竹筒 “とおくなり近く聞こゆるほととぎす ふた国かけて鳴きわたるらん” |
|||
 |
 |