
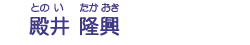
| 天保6年(1835)、天下の名勝瀞峡神下田戸の医師の家に生まれる。 隆興、幼時官平と称し才気換発気節あり、学問を好み学才衆にぬきんでていたという。慶応3年(1867)12月、高野山義挙に従い、明治元年(1868)4月、御親兵として伏見練兵所に入る。幕府軍と勤王軍の戦いである戊辰の役には明治元年6月、北越に嚮導官として出兵。越後各地において奮戦したが7月長岡千手口の戦闘において負傷、12月伏見に帰営した。 明治2年(1869)6月、戦功により高40石を賜った。 その後、新しく創設された日本陸軍の中にあって昇進を重ね、明治10年(1877)西南の役には陸軍大尉として出征し、戦後勲五等一時金500両を賜う。明治27・28年の日清戦役には少佐として従軍、功四級金鵄勲章を賜った。明治37・38年戦役には旅順攻囲軍に属し、激戦中負傷する。戦功により功三級金鵄勲章を授けられ、中佐に進み、正五位勲三等に叙せられた。しばらくして軍職を退き、爾来東京にあって悠々自適の生活を送った。 隆興は平生元気旺溢、読書に親しみ、談論風発、絶えず郷党に思いを寄せ、関東十津川郷友会には毎回必ず出席、後輩の為に懇々と訓話を試みることを常とした。 養斉と号し詩文を能くし80歳を迎えたる詩に 古希記我昨誇人 一笑今朝算八旬 回首波乱幾重畳 素襟誰識不留廛 の七言絶句がある。 又郷史に精通し、かつて明治初年の衝撃的大事件となった“横井小楠要殺事件”で小楠を襲撃し、事件後行方不明となった中井刀根男の甥中井哲太郎が、叔父刀根男の人物に関しての問いに対し、「前略……中井君は真に温厚の人で、かくの如き事に関係することは思いも寄らず当時皆意外の感をなせしことなりし、案ずるにその時の機でここに至ったので、如何にも中井君の本心に出でたりとは思われず、これらは人の持って生れた運命というものにて遅くることの出来ざることなりとす。後略…」と答えている。 昭和6年(1931)2月、病んで没した。天保・弘化・嘉永・安政・万延・文久・元治・慶応・明治・大正・昭和の波乱に満ちた長い世代を生き抜いた96年の生涯であった。 |
|||
 |
 |