
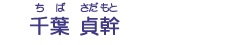
 嘉永5年(1852)2月10日、千葉清宗の長男として永井に生まれる。 嘉永5年(1852)2月10日、千葉清宗の長男として永井に生まれる。幼年より学を好み、5歳田良原村福田寺の住職に読書・習字を学ぶ。 12歳高野山に登り、三宝院主に講学する。13歳京都に行き中沼了三の門に入るが、やがて孝明天皇の勅命により中沼了三来郷、文武館が創立されたので帰郷、文武館に入学する。慶応3年(1867)12月高野山義挙には父清宗と共に参加。明治2年(1869)中沼了三の上京に従い西洋の法律を研究する。明治7年(1874)司法省に入り、以後裁判官の道を歩む。 明治24年(1891)5月11日、大津裁判所長在任中、折から来日中のロシア皇太子(後の皇帝ニコライ2世)が大津において、警備中の巡査津田三蔵に斬りつけられるという、日本中を驚愕させた大事件が突発した。千葉所長は直ちに大審院長児島惟謙に「津田三蔵の犯罪は、普通法律によるものとして、すでに予審に着手した」と報告、院長よりは「法律の解釈至当なり、この際他の干渉を顧みず予審を進行せよ」と返電があった。しかし司法の見解とは裏腹に、内閣は大審院に対し、「外国の皇太子に対しても、日本の皇太子に対する刑罰を拡大適用し、被告を死刑に処すべし」と圧力をかけた。恐露病という言葉が流布される程、強国ロシアに恐怖心を抱いていた当時の国内事情から、外交の悪化を恐れる余りの司法への介入であった。 このことは正に国を挙げての大問題となったが、大審院は司法の独立を堅持し、千葉所長の意見通り一般人の謀殺未遂罪を適用、無期徒刑の判決を行った。かくして当時の日本を震憾させた大津事件は決着をみ、児島惟謙は司法の独立を守った“護憲の神”と称せられるに至った。 その後貞幹は、大阪控訴院部長・岡山・神戸各裁判所長・行政裁判所評定官と昇進を重ね、遂に明治39年(1906)7月、大分県知事となった。 5年余の在任中、知事の大計による大分港の築港、産業振興に尽くし、日本一の知事とその名をうたわれた。明治44年(1911)7月、長野県知事に転任、河川事業等に治政の実を挙げたが、不幸病のため、大正2年(1913)3月23日、知事官舎にて現職のまま61歳の生涯を異郷にて閉じた。 葬送に際しては、祭祀料500円を賜い、勅使が差遣された。 貞幹、至誠一貫、清廉にして、情誼に厚く、皇室を敬い、常に郷党に思いを寄せていた。知事在職中の逝去、人皆これを惜しんだという。 |
|||
 |
 |