
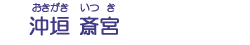
| 天保13年(1842)風屋に生まれる。 賀名生堀家を継ぎ重礼と称す。資性朴直にして胆力あり。文久の始めより京都・大阪の間を住来し憂国の志士と交わり国事を談じたという。文久3年(1863)8月、天誅組の変には野崎主計・深瀬繁理等と共に参加、一方の隊長として活躍したが、後これと離れ専ら禁裏御守衛の任に従う。慶応2年(1866)11月、幕吏の中傷により我が郷は支配庁の嫌疑を受け、紀州藩がその取り調べの命を受けたが、斎宮は郷人藤井織之助と共に、紀州藩の三浦久太郎等に面会弁明に努めた。又同藩の野口駒五郎等一行が入郷するや、丸田藤左衛門・吉田正義・前田正之等と郷中総代となり会見し、意見を交換し一行を引き上げさせた。 慶応3年(1867)2月、紀州藩の課した不当な新宮湊口銀問題につき吉田正義・千葉清宗等と紀州藩を訪い、撤廃の交渉を行った。同年12月鷲尾侍従内勅を奉じて高野山に立て籠ったいわゆる高野山義挙には、人数を率い軍監として出陣した。この義挙は徳川慶喜が大阪を出て江戸に去った為、華々しい戦闘には至らなかったが、京都と紀州の間に錦旗を翻し、親藩紀州を牽制し官軍を有利に導いた功績は大なるものがあった。 斎宮はその後、御親兵人選方・軍事監司・郷中人数監察・伏見二番中隊補助官に任ぜられた。 明治2年(1869)伏見練兵場繰り込みを命じられたが、郷中紛擾事件(郷中新旧二派に分かれて争った事件)に関連して謹慎申し付けられる。 明治5年(1872)3月、創立間もない海軍兵学寮生徒取締となったが、同年10月24日東京にて病没した。時に年わずか30歳、芝高輪泉岳寺に葬る。 明治31年(1898)7月従五位を贈られた。 斎宮体躯短小なれど弁舌鋭く、渾名[あだな]を“釘抜き”と称した。 酒を好み、酔えばしばしば奇行にはしったという。 (注)斎宮の継いだ堀家は賀名生の名家で南北朝時代行宮[あんぐう]となり、今も「皇居」の扁額が掲げられている。斎宮の弟重信又堀家を継ぎ賀名生村長となる。 その子丈夫は陸軍中将、孫栄三は大本営参謀、戦後駐在武官としてドイツ大使館勤務、のち西吉野村長を務める。 |
|||
 |
 |