
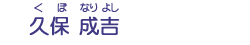
 天保9年(1838)11月1日、平谷に生まれた。 天保9年(1838)11月1日、平谷に生まれた。嘉永6年(1853)米艦来航天下騒然たるとき、成吉は丸田藤左衛門・藤井織之助等と共に全郷を激励、武器を購入して防御の策を講じ他日の用に備えた。文久3年(1863)8月、五條において討幕の狼煙[のろし]を挙げた天誅組には、いち早くこれに応じ、各地に転戦する。然るに8月15日の政変により天誅組は朝敵と化し、諸藩の軍勢は追討の為十津川郷に迫った。 この時、紀州藩は特に多数の兵を率いて、日高郡丹生川に陣を構え、四村組に使者を送り「十津川郷が紀州藩に降参し、以後我が藩に従うことを誓約するならば朝廷や幕府に対して、紀州藩においてしかるべく取り計らってやろう。」という意味の書状を送って来た。 これを読んだ成吉等は憤然として「十津川郷は目下幕府軍の包囲下にあるが、固より朝廷直轄の地である。何故に他の藩に従う事ができようぞ。」と断固としてこれを拒否、使いを追い返したという。 元治元年(1864)5月、禁裏御守衛の為上京、これに従う。 高野山義挙には東四番隊副長を命ぜられ出陣。暫くして京都に帰り伏見練兵場にて洋式訓練を受ける。明治元年(1868)6月、御親兵第一番中隊大伍長となるが病の為職を辞して帰郷する。明治3年(1870)壮兵募集に応じ再び伏見兵営に入り、陸軍一等伍長として大阪鎮台へ転営、11月退営帰郷する。帰郷後地方自治制度の実施に伴い、成吉は新制度の副戸長・戸長等を務めた。明治22年(1889)6月には、町村制施行により郷内59ケ村が6ケ村になったが、成吉は南十津川の名誉村長となった。 この年8月、村は大水害に見舞われ壊滅的被害を受け、この為止む無く北海道へ分村移住のことがあり、成吉は移住地までの総取締役を委嘱され、移住民600戸・2,600人を率い渡道、現新十津川町を開墾永住の地となす計画を定め、帰郷した。明治23年(1890)6月、村は再度合併、「十津川村」となり成吉は初代村長となった。9月、名誉村長に推挙され文武館主を兼任した。明治26年(1893)2月病におかされ、村長・館主を辞した。 同年7月県知事より褒状と木杯一組が贈られた。 明治35年(1902)12月2日、資性思慮周密・決断力・人望あり、国事に、地方自治に奔走した64歳の生涯を終えた。 |
|||
 |
 |