
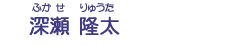
 明治15年(1882)6月7日、重里に生まれ、長じて永井深瀬家を継いだ。 明治15年(1882)6月7日、重里に生まれ、長じて永井深瀬家を継いだ。資性頭脳明敏、雄弁家であった。 明治31年(1898)3月、郷校文武館(現十津川高校)を卒業、医学を志し大阪あるいは愛知の医学校に学んだが、日露戦争従軍の為、業半ばにして退学した。除隊後帰郷、文武館会計、木材同業組合の業務等に従事する。 大正5年(1916)十津川村会議員に当選、大正10年(1921)名誉助役、大正11年(1922)村民の輿望[よぼう]を担って村長に推された。 隆太は村長となるや、行政の中心課題に道路整備を置き、村内各所の道路開発を計画した。今日村内の主要道は当時の計画によるものという。とりわけ五條新宮間を結ぶ鉄道を敷設する、五新鉄道法案を国会で通すべく、あたかも同時期、同じ計画をもつ奈良県(十津川村折立出身)選出、代議士玉置良直と相呼応して運動を展開した。玉置は国において鉄道省その他に、深瀬は村や沿線関係町村に強力に働きかけた。深瀬はこの鉄道の国策上、また観光上、産業上極めて有用性の高いことを力説、文字通り政治生命を賭けて取り組んだ。長く東京に出張滞在し、陳情活動を行ったが、これが国会での法案通過には尋常一様の努力ではその成果を見ることが出来なかった。 時に深瀬は運動の効現れず悲観の極に達し東京より役場、玉置神社に宛「万策尽キタ 一村ノ興廃コノ一挙ニアリ 村民挙テ祈願セヨ」と打電、村よりは「斎戒沐浴祈願ニ努ム 最後ノ五分間極力奮闘ヲ乞ウ」と返電。または代議士玉置は病躯をおして、村長深瀬の肩にすがって鉄道省の階段を昇降したという。かくして猛運動の結果、大正12年(1923)法案通過、悲願達成へ大きく前進した。しかしながら国内外の情勢変転に伴い、幾度か予算化着工の繰り延べが行われ遅々として進まず、(戦後僅かに阪本までの半完成をみたが、)遂に戦後の鉄道合理化案により、日の目を見る事なく「幻の鉄道」と化した。深瀬はこの運動の為自らの資産ことごとくを費やし、昭和22年(1947)鉄道にかけた夢を抱いたまま、報われる事なき生涯を閉じた。享年65歳。 昭和51年(1976)西川区民は深瀬の情熱を偲び、遺徳を後世に伝えるべく頌徳碑を建立した。碑は国道425号線沿い西川を臨む川合神社前にある。 |
|||
 |
 |