

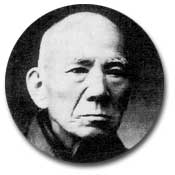 天保12年(1841)11月5日内原に生まれる。初め数男、後喜延と改める。 天保12年(1841)11月5日内原に生まれる。初め数男、後喜延と改める。文久3年(1863)8月上京、御所警衛に従う。明治になり神仏分離による玉置神社の廃仏毀釈に当たっては、丸田藤左衛門・松實富之進等と帰郷、聚議館役員・郷内各組総代等を玉置山に集め、復古の報告祭をなして滞りなく処理を終えた。その後文武館執事・勧業係・郷金担当役・郷中共有物取扱幹事・花園村長等歴任した。喜延の多くの業績の中で特筆すべきことは旧郷十津川においては、勧業資金の拝借による勧業林への杉・檜の植栽、新十津川においては、創業の基礎を築いたことであろう。即ち明治維新後十津川郷は、幕末の勤皇運動の結果、公私の出費かさみ山林伐採後の植林等手入れに力及ばず、山林は荒れ、加えて不況の為失業者続出、村は疲弊した。この窮乏を救うため、明治15年(1882)喜延はじめ同憂の士が政府に働きかけ、勧業資金の貸付けを請願した。しかし事は簡単には捗らず、喜延等は日夜東奔西走、20年(1887)に至って漸く士族授産資金3万円の貸与が許可された。村はこの全てを産業復興資金としてこりかき・北又山554町歩、300万本の杉檜の植栽に充て、27年(1894)完成をみた。後年この山林は勧業山と呼ばれ村の基本財産となり、一部は文武館財政の基盤となった。尚、借り受けた資金は年々返済の予定であったが、22年(1889)8月村は大水害に見舞われた為免除された。大水害の羅災者は北海道への移住を余儀なくされた。喜延はこの時推されて移住総長となり渡道した。23年(1890)1月、新十津川創立と共に初代戸長に任命され、滝川戸長を兼ねる。当時移住民は故郷を離れ、極寒の地に移り、境遇の急転風土の激変により、不安焦燥の念に駆られ、目前の事に気を取られ、永遠の計を忘れる者があった。喜延は深くこの事を憂い、「移民誓約書」を作り一致団結を強調、風紀の粛正を呼び掛け、且つ基本財産蓄積の計を確定し、各戸主に署名捺印させ厳守することを誓約させた。思うに今日新十津川発展の基礎は、喜延の高遠な識見による所が極めて大きいといわねばなるまい。 創業3年、故郷に帰ったが新十津川は、銀杯一組を贈り謝意を表した。帰郷後、村議会議員2期、41年(1908)には第7代村長に当選。 大正11年(1922)10月1日、病没。資性温厚にして謙虚、思慮周密忍耐心強く、新旧両村の治世に大いなる功績を残し、81歳の生涯を終えた。 |
|||
 |
 |