

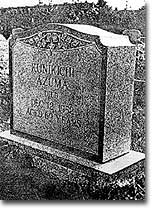 明治15年(1882)5月18日、東義次の三男として永井に生まれた。 明治15年(1882)5月18日、東義次の三男として永井に生まれた。郷校文武館に学び、北海道に移住した長兄東武(後の農林政務次官)を頼り渡道、その後妻子を残し単身北アメリカに移住した。 北アメリカにおいて、裕福なアメリカ人家庭の料理人をするなど、勤勉努力すること40余年、質素倹約孤独の生活を送り、昭和27年(1952)12月12日、フィラデルフィア市ハーネマン病院にて70歳で病没した。 臨終に当たって知人平田三郎博士(三重県人)に「遺産の全てを十津川村の医療施設と、教育施設を整える目的の為に寄付する」と遺言された。 村は寄付された800余万円を、医療施設として小原診療所を、教育施設として十津川高校に図書館を建設、残金を奨学金として故人の遺志を生かすこととした。 小原診療所はその後改築され内容が充実され、診療活動も活発化し故人の目的とした医療施設としての役割を果たしている。  十津川高校の図書館は、校舎の改築により図書室が新設されたため、「東記念館」として多目的に使用されている。 十津川高校の図書館は、校舎の改築により図書室が新設されたため、「東記念館」として多目的に使用されている。没後、営々として蓄積した汗と脂の結晶である“遺産の全て”を、村に寄付するなどという奇特な行為は、村始まって以来のことであったのではないか。このような行為の持ち主である國吉とは一体どのような人であったろうか、二、三の人物評を紹介する。 國吉と同じ永井の竹馬の友である勝山倉吉(元武蔵小学校長)は、「彼は寡言で大胆で短気で意志強固であった。人に対して上手は言わぬが親切であった。兄富七君が長兄武君に頼り北海道に移住するので、國吉君は文武館を半途退学して同行した。」と語っている。 臨終に立ち会ったドクトル平田三郎は、「同氏は年来の胃病で始終青ざめて貧血で随って身体も余り強い方でなく、体重も軽く年齢の割りにずっと老けて見えました。中略…東氏は下宿住居しながら自炊して居られ所持品としては懐中時計一個さえ持たない奇人でした。自己所有の荷物や容物用器等一つもなく唯古い手提げ鞄と写真数枚と一通の故国からの古手紙だけでした。」と言っている。 昭和29年(1954)12月、村は永くその徳を後世に伝える為、小原診療所前に遺徳碑を建立した。國吉の墓は北アメリカフィラデルフィア市にある。 |
|||||||
|
|||||||
 |
 |

