
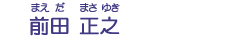
 天保13年(1842)正月4日、風屋に生まれる。父は前田清右衛門。初め清三、次いで雅楽[うた]と称し、後正之と改める。幕末嘉永6年(1853)米艦来航により天下騒然たる時、父清右衛門の感化指導を受けた正之は、年少ながら国事に力を尽くさんと心に期していたという。安政4年(1857)8月、長沢俊平・上平主税・丸田藤左衛門等と相計り、護良親王御詠の碑を小原滝峠に建立した。文久3年(1863)4月、丸田藤左衛門・上平主税・深瀬繁理・千葉左中・田中主馬蔵等と上京して、中川宮に十津川郷由緒書を奉呈した。かくて同年6月禁裏御守衛の恩命を拝するに至り、8月郷士170余名上京御所警衛の任に就く。同時期、8月15日の政変により十津川支配の七卿落ちあり、十津川の加勢した天誅組の変あり、郷士は大いに動揺したが正之は同志と共に事態の収拾に努め事なきを得た。 天保13年(1842)正月4日、風屋に生まれる。父は前田清右衛門。初め清三、次いで雅楽[うた]と称し、後正之と改める。幕末嘉永6年(1853)米艦来航により天下騒然たる時、父清右衛門の感化指導を受けた正之は、年少ながら国事に力を尽くさんと心に期していたという。安政4年(1857)8月、長沢俊平・上平主税・丸田藤左衛門等と相計り、護良親王御詠の碑を小原滝峠に建立した。文久3年(1863)4月、丸田藤左衛門・上平主税・深瀬繁理・千葉左中・田中主馬蔵等と上京して、中川宮に十津川郷由緒書を奉呈した。かくて同年6月禁裏御守衛の恩命を拝するに至り、8月郷士170余名上京御所警衛の任に就く。同時期、8月15日の政変により十津川支配の七卿落ちあり、十津川の加勢した天誅組の変あり、郷士は大いに動揺したが正之は同志と共に事態の収拾に努め事なきを得た。天誅組の騒動以後、京にあって御守衛の任に従う。 慶応3年(1867)10月、京邸の総代となり帰郷し、折立松雲寺に各村の代表1名宛を集合せしめ、郷中役人人選方に関する京都における邸議を披露し、討議の結果、十津川郷由緒復古以来の事務に熟練せる者30名を挙げ、これを評定衆と名づけ、郷中内外の事務を担当せしむることとした。 同年12月、高野山義挙に際しては、郷士650余名が参加したが、正之は補翼兼参謀としてこれに従う。明治元年(1868)2月、十津川御親兵人選方・軍事管轄及び郷中人数取締を命ぜられる。同年戊辰の役には十津川第一御親兵補助官となり北越に従軍する。明治2年(1869)7月、戊辰の役の戦功により永世高60石を賜う。明治3年(1870)6月兵部省出仕となる。 同年8月艦隊筆記となり甲鉄鑑乗り組みを命じられる。同年11月海軍兵学寮(海軍兵学校の前身)権充、明治4年(1871)7月兵学寮権大属、翌4月大属(教頭)となる。明治9年(1876)9月、兵学寮廃止により解任される。明治17年(1884)皇宮警察官宮内門監長となる。皇宮警察史によれば、皇宮警察の草創期門部(皇宮警察官)採用の内規に、 ・門監長2名の内、1名は十津川郷士前田正之とする ・門部の半数以上は十津川郷士を採用する と記されている。明治25年(1892)6月従六位に叙せられ、7月京都にて病没、享年50歳であった。 正之は友誼[ゆうぎ]に厚く、文久3年(1863)天誅組に加わり各地に転戦、風屋で病死した知人で熊本の志士竹下熊雄(正しくは竹志田)を風屋の共同墓地に葬り、碑を建て手厚くその霊を弔った。 |
|||
 |
 |